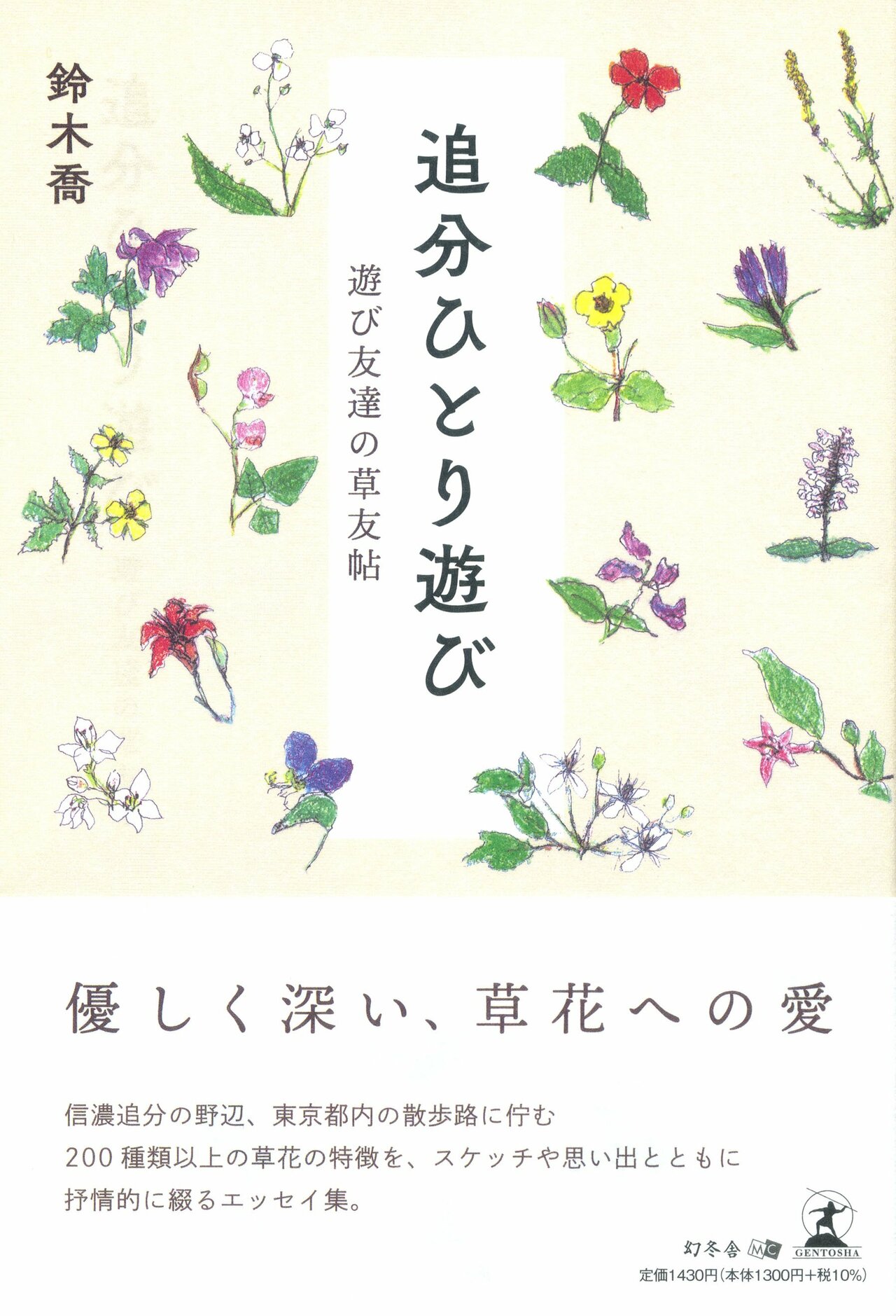挨拶もそこそこに、2階の部屋に案内された。荷を解いて下に降りると、ミセス・ミッチェルが紅茶を入れてくれていた。しばらくお世話になると挨拶し、持参したちょっとした土産を渡すと彼女は大喜びで、こちらが気恥ずかしくなるほどであった。彼女は私の名前の一部をとって、タック(Tak)と呼ぼうと勝手に決めて1人で頷いていた。私はその後のヨーロッパ滞在中、タックの名で通すことになった。
ミセス・ミッチェルは1人暮らしで、家に何人かの下宿人を置いているようだった。実は私はロンドンの研修先が決まった時、滞在先は働く設計事務所の世話によるものだろうと思っていたから、事務所の関係者の誰かの一般家庭にホームステイするのだろうと勝手に想像していたのだ。
ところが旧式の列車に揺られて郊外へ来てみたら、そこは寡婦が営む下宿先だったので、予想外でちょっと驚いた。しかし、ミセス・ミッチェルの笑顔に迎えられ、紅茶をご馳走になるうちに、彼女とならここで楽しくやれそうだと思い直した。むしろ、市中の一般家庭より、日本ではあまり知られていないような環境の暮らしが体験できていいかもしれないと思った。
夕食の時紹介された下宿人は、いかにも労働階層風の中年の独り者の2人のイギリス人だった。2人とももうここに長く住んでいるようであった。ミセス・ミッチェルは、明日にでもタックと同じような若者が2人来る予定だといっていた。彼女は、主にロンドンで英語を習得するために短期留学する外国人を受け入れていたのだ。私もそういう1人だったということで、私はここに3ヶ月いたが、その間人の出入りも何回かあった。
イギリス人の2人はミセス・ミッチェルと同じ3階の夫々の個室にいたようだが、他は2階の2部屋で2人ないしは3人で寝起きしていた。彼女は巨体を揺すり、息を切らし、脚を引きずるようにしながら階段を上り下りして、そういう皆の世話を1人で切り盛りしていた。
イギリス人の1人はジョージといって、もう40歳ぐらいと思われた。私より小柄な体格であったが、深い皺に刻まれた顔は日に焼けて、腕は筋肉でひきしまり大きな手をしていた。聞くと、鉄道の保線の仕事をしているとのことだった。彼は人懐こくて大声でよく話し掛けてきたが、私は癖のある彼の英語がよく判らない場合が多かった。
もう1人のイギリス人もジョージと同年配と思われる、寡黙でおとなしい人だった。2人のイギリス人が早口で話しているのを聞くと、とても我々の習った英語とは思えなかった。2人が何ゆえに独身なのかは知る由もなかったが、2人にとってはミセス・ミッチェルとのここでの暮らしが彼らの家庭であったようだ。