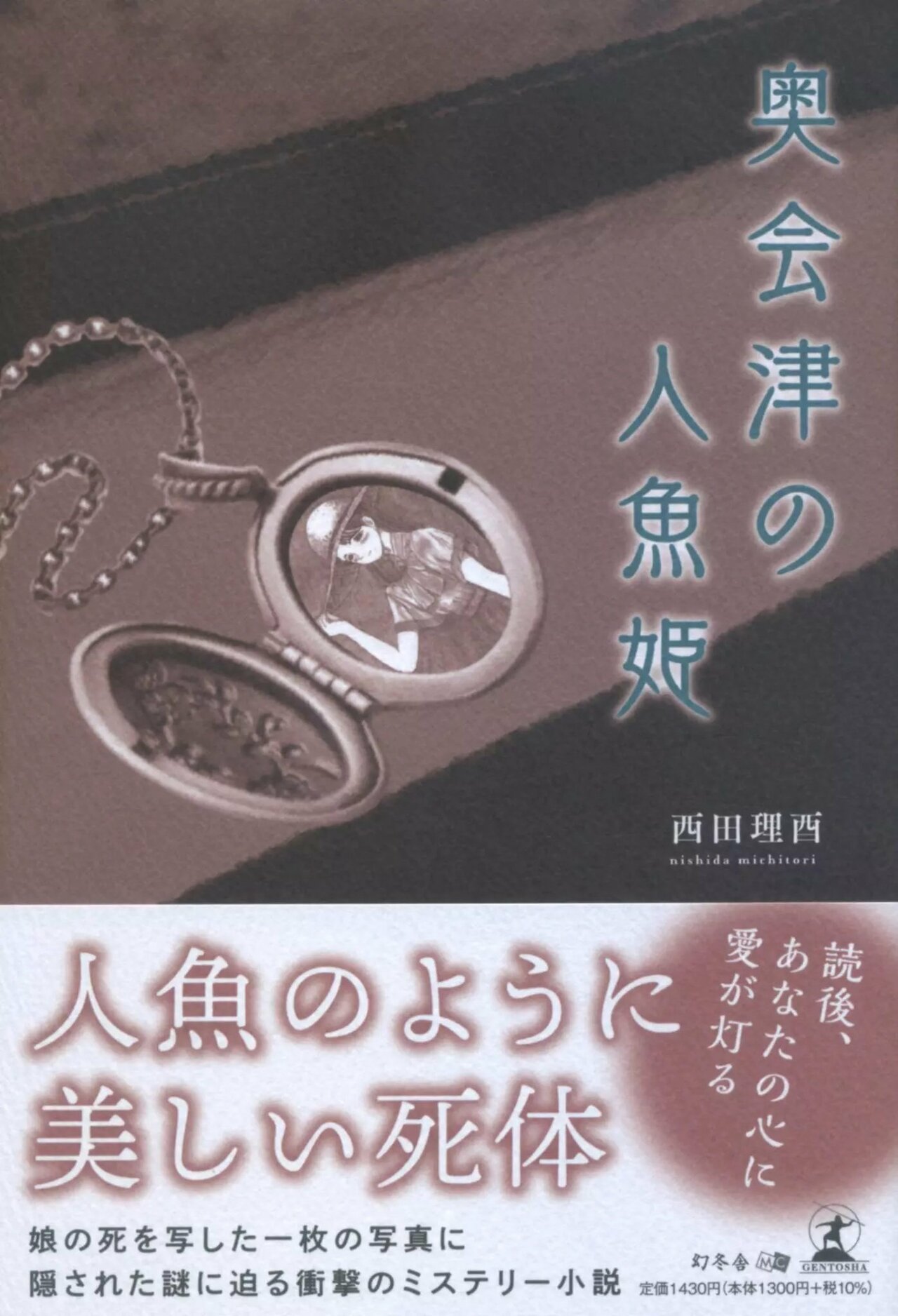「お前が俺と咲也子の結婚式に来てくれた10年前のこと、覚えてるか? 咲也子には双子の連れ子がいて、当時10歳で小学4年生だった乙音と汐里だ。双子座生まれの双子だったせいか、見た目も中身も瓜二つの二人で、乙音と汐里は本当に仲が良かった」
「ああ覚えてるよ。でも10年経って、乙音ちゃんはびっくりするくらい綺麗になったよね。で、今はお前の幼な妻って訳だ。苦労してめぶき屋をやってきて、役得もあったじゃないか」
少し茶化した調子で鍛冶内が言っても、相変わらず千景が表情を緩めることはなかった。
「そんなことじゃないよ。必死で生きてきた俺ら親子にとって、やむを得ざるの選択という側面もある。お前が思うほど甘い世界ではないんだ」
「で、もう一人の汐里ちゃんはどうしてるんだ?」
何気なく聞いた鍛冶内だったが、なぜか千景はその問いには答えず、思い詰めたような顔でテーブルの中央に置かれていた風呂敷包みを解き始めた。そして、さらに淡々と説明を続けた。
「俺はお前も知っている通り、会津に来た10年前まではプロのスタジオカメラマンをやってた。その俺にとって、というか誰にとっても写真というやつは、言うまでもないが基本的に誰かに見られるためのものだ。仮にアルバムに収まり、一時的に陰に隠れてしまう存在だとしても、長い年月暗い中でじっと息を潜めながら、次にアルバムを開いてくれる誰かが来るのを待ってる。まるで鬼から身を隠しているかくれんぼの参加者のように。だから他人に見られない写真など本来何の意味もない。
だが今回俺は生まれて初めて他人に見せるつもりのない写真を撮った。だからこの一枚だけは、今俺のわがままに付き合って遠いところをはるばる来てくれたお前に見せたら、それを最後に俺の棺桶にでも入れてもらうつもりだ。もちろんネガなどは最初から取っていない。だからお前も、この写真のことは誰にも言わないでくれ」
そう言って千景は風呂敷包みを解き終えると、シンプルな黒いフレームに収められた500ピースパズルほどの大きさの写真を露にした。