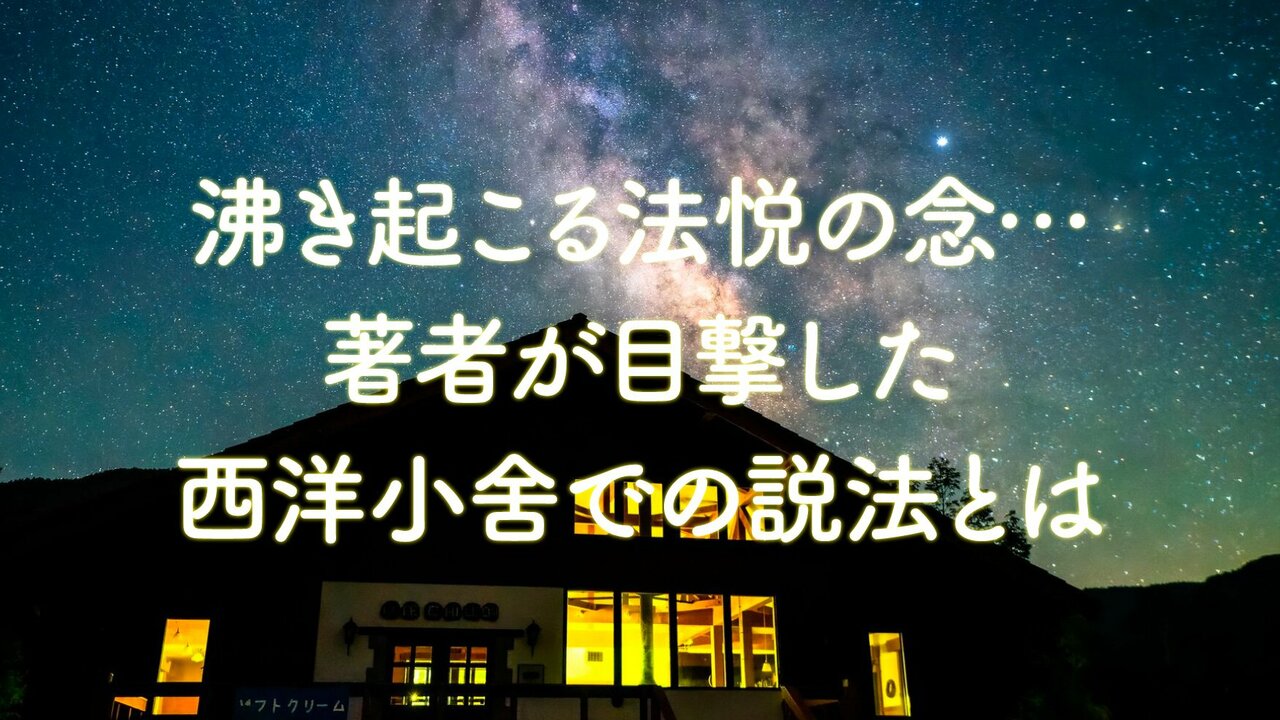この一面、因循な狀況を知つた自分は、今迄現在の宗敎をあまりに輕視してゐた事がなんだか底怖しいように、またこの因循な一面が却つて有難く、何とも云へぬ法悦の念がむらむらと、この貧弱な小さい自分を圍撓した、
そして兎にも角にもこの周圍の無智な人逹が、佛敎を眞に理解したところの信仰であろうとも、盲従の信仰であろうともそんな事はどうでも宜い、兎に角心の底から無意識的にでも要求してゐる彼等の信仰は、彼等の人事に於て一つの强い法悦を感じてゐるに相違なからうと思ふ、寧ろ彼等の無智を無限の幸福と考へられた。
そしてこの小舍に勞働する傭人は、悉くこの老夫婦の眼鏡にかなつた佛敎信者の寄り集りであるとの事である、而も晝の勞働の疲勞を厭はず熱心に、或は敎室に於ける敎師に對して生徒が質問する如く、彼等勞働者も開敎師に向つて種々な事を質問してゐた、其の質問の內には隨分愚鈍なこともあつたようだが、氏は眞面目に一つ一つ極めて通俗的な例を引いて、宜く呑み込むように答へてゐた。
あまり遠衟を歩いた事のない自分は、かなり疲れて、汚れたベッドの中に氏と肩を並べて、窓外の闇夜の金砂子を散らしたようなきらきら光つてゐる星空を眺めながら、氏とよもやまの話をしてゐたが、何つの間にか氏をのこして、瞑夢の世界に運ばれた。
目が醒めて、柳の古木の流れの前で齒を磨いてゐると、遠くの畑の中に昨夜の同胞があちらに一人、こちらに一人悠々と働いてゐる。
學士のスクール・ボーイ
サマリー
与作は米国で大学に所属したわけでもないのに、当時の米国の苦学制度についてよく知っていたことに驚かされる。英語の勉強をかねて大学の図書館に出入りしているうち友達が出来、そこから情報を得たらしい。
また東部に小旅行した時にある駅舎で新聞売りの少年に出会った。その少年は、自力でハイスクールに行き、それから大学を目ざし、将来はこうなりたいと目を輝かす。与作はそんな少年と自分を重ね合わせていたようだ。