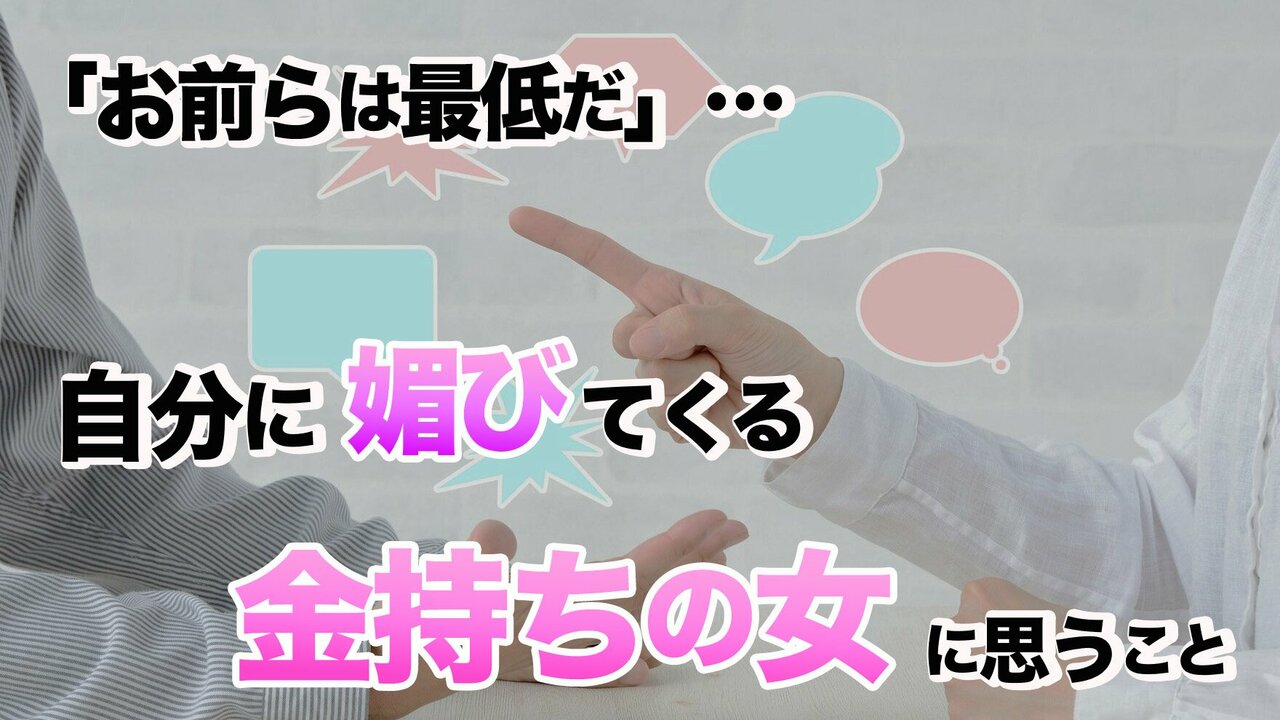ひるあんどん
「勘がいい女房か。それも疲れるなあ」
新村が白いぽっちゃりした手でビールを飲み干した。時々、こんなふうに呼び出されて駅前のひるあんどんという飲み屋で会い、別れる。今日も赤い顔をした飲み助たちがあちこちで気勢を上げている。
「うちのかみさんなんて口を開けば稼げだぜ。これも辛いぞ。女に逃げたくても、監督みたいに脚本家はもてんしなあ」
「そのせいか。監督、この頃やりだしたのは」
「あれは成り行きだ。だが、そういうメリットも確かにあるな。役ちらつかせりゃついて来る女もいる。でも男としては邪道だろ、惚れられてなんぼだ」
新村が赤い顔をしてビールを飲み干した。色白な優男だったが、今は肥って昔の面影はない。相変わらずよく飲むなと言うと、これでも前より量減らしてるんだぞと言いながらまた、ビールを注文した。
「実はこないだ、健康診断で引っかかったんだ。かみさん、この上、病気にでもなったら、私たちをどうしてくれるって、心配するより脅迫よ。それで高い保険にも入った。もしかしたら死んだほうが実入りがいいかもしれんな。酒代も浮くし。時々、女房が殺し屋に見えるよ。その目盗んでたまには羽目外さんとやってらんねえ。
きゅうさんに会うって言うと、何故か納得するんだ、お前なら安心と思うらしい。お前は昔から女受けが良かったからなあ。今もスケジュール通りの生活やってるのか。修行僧じゃあるまいし。生きてて楽しいか。なんでまあ、あんな生活続けるんだ」
「言い訳だ」
「誰に」
「自分が生きてる」
「なんだそりゃ。俺にはただのマゾとしか思えん」
「蝉は殺される時、鳴くのかな」
「蝉?」