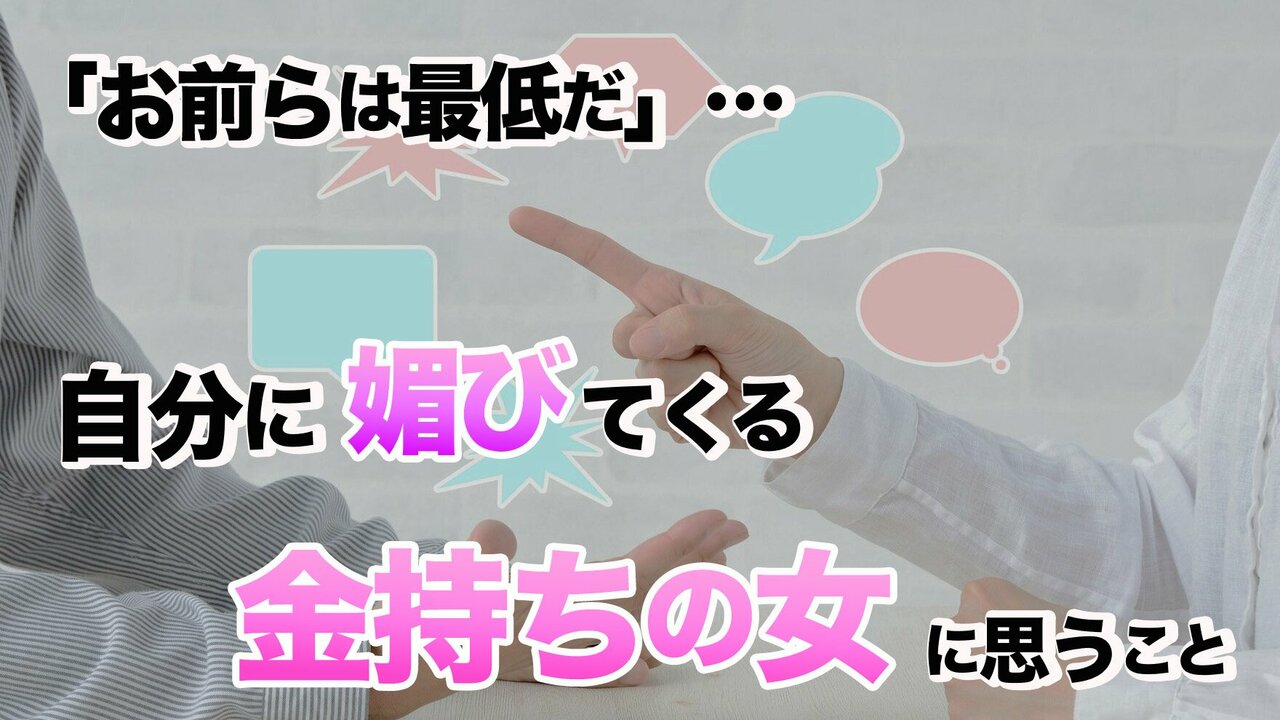「夜中、蝉が鳴いた。喰い殺される時の悲鳴だと、りょうが言うんだ」
「呆れたねえ。そんな話、夫婦でしてんのか。うちなんて、トイレのドア閉めろだの、鼾がうるさいだの、もっと俗っぽい会話しかしねぇぞ。蝉が喰い殺されるより俺が締め殺されそうだよ」
「俺たち夫婦には、子供がいないからだろ」
「子供ねえ。それなんだよ、これが大変なんだよ。娘、音大、行っててな。あれは金かかるんだよ、ワンレッスン三万だぞ、三万。外国人でなんとかいう有名な先生なんだと。わりといい線行ってるらしくて、その先生さまに言われて、留学したいとか言い出してさ、参ったよ」
愚痴っぽく言うが目が柔らかい。
「かみさんなんか張り切っちゃって。あなた、親でしょ。お金なんとかしてくださいと、こうだよ。なんとかならないなんて言おうものなら、結婚に失敗したとくるんだ。かみさん、昔、医者と付き合ってて。何かの間違いで俺が横取りしたから、あの時の選択が間違ってただとさ。これを何百回聞かされたか分かんねえよ。女ってのは、どうしてああ発想が貧弱なのかねえ。
同じ愚痴を初めて話すみたいに言うのには呆れるねえ。それで、仕方ないから、やりたくもない副業やって。添削もやって。俺はお前みたいな高等遊民とは違うからな。金稼げとか俗っぽいこと、りょうさんは言わんだろ。何しろ、野田先生のご息女だからなあ。お前みたいな堅物じゃないと、彼女みたいな才女とは、務まらんよ」
「才女か」
「そりゃ、才女だろ。あんな脚本書いたり絵本描いたりするんだから。少なくとも、うちのみたいに俗っぽくはない。ま、お前も俗っぽくないか。俗っぽい亭主には、俗っぽい女房。割れ鍋に綴じ蓋とはよく言ったもんだ」
りょうの父親は著名な脚本家で、新村や久等、若い者がりょうの家によく集まった。りょうの母親はそういう集まりを嫌うらしく、りょうが酒の肴などを作ったりして時々、顔を出した。きつい目をした固い蕾みたいな娘だった。胸も小さく痩せていた。心臓が弱く、結婚には向いていないと自分から避けている雰囲気があった。
それでも少しずつ話すようになったのは、馬が合ったと言うんだろう。そう言えば、最初から禅問答みたいな会話だった気がする。
「酒じゃなく副菜も食べろって医者に言われてな」
これ、副菜だよなと新村が枝豆をつついた。