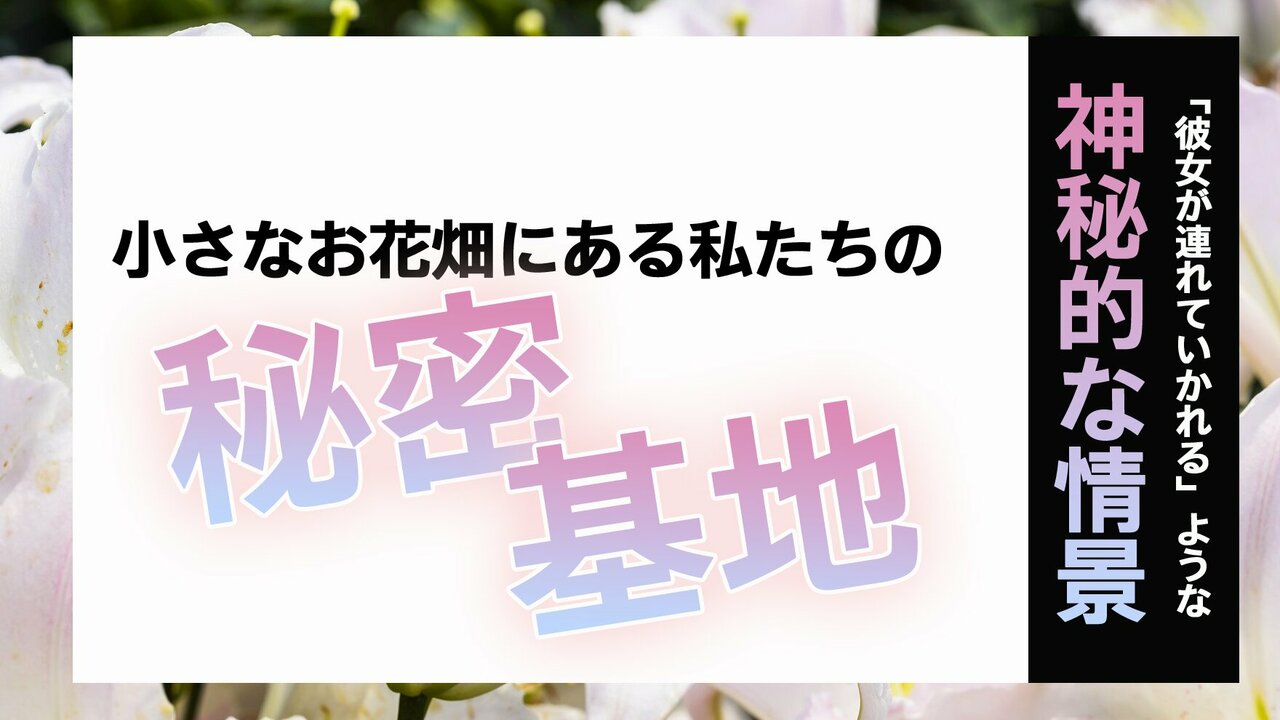3
「今日、お父さんは?」
質問を無視して、自分の聞きたいことだけを訊ねる。
「職場の人とゴルフ。夕飯もいらないって言ってたから、帰りは遅くなるでしょ」
やれやれといったふうに溜息を吐く母だったが、呆れたような口調とは裏腹にその表情は穏やかだ。子は鎹とはよく言うものの、娘が東京に出ていって数年経った今でも、この熟年夫婦の仲は円満のようだった。
携帯をいじるふりをして横目で母の顔を窺う。慣れた道でも運転中は決して視線を外さない母の横顔は、なんとなく小さなしわが目立っているように見えた。昔、まだ中学生だった頃の……こうして同じように助手席に乗っていた時の記憶を呼び起こしてみる。
写真のように鮮明に、とまではいかないけれど、記憶にある母の横顔は現在のそれと比べて絶対的に若々しい。当たり前のことなのにそれがなんだか物凄くショックだった。時の流れの残酷さを目の当たりにした気分だ。
……まあそれも仕方ない。私の中学生時代なんて、数えてだいたい十年前のことだ。十年も経って見た目が変わらない人間なんていないし、変わるほうが普通だ。私だって子供と呼ぶには無理のある容姿に育った。他人を見る目も、子供的だとは言い難い。
十年前の今頃は何をしていただろう──疑問が湧いてくる。十年前というと、私が十四、十五歳ぐらいだろう。
…ああ、そうだ。思い出した。中学三年の夏、ちょうど今頃の時季「来年通う学校が見てみたい」と、当時その高校の一年生だったさよちゃんに案内してもらったっけ。部活や登校日でもないのに制服を着てきたさよちゃんに形容し難い苛立ちを覚えたことも覚えている。
思えばあれは、同じ制服を着ていないことに一年という時間的距離を感じて焦っていたんだなあ、と過去の自分を尻目に冷静かつ客観的な考察をしている自分がいた。もしかしたら、さよちゃんはそのことに気づいていたのかもしれない。だから言い訳までしてミルクティーを奢ってくれたのかも。私をなだめるために。
過去の彼女の内情を知る術はないが、その記憶を思い出すことはできる。当時の彼女は笑っていた。その表情は何年経っても変わらない。この先何十年経っても、変わることはない。