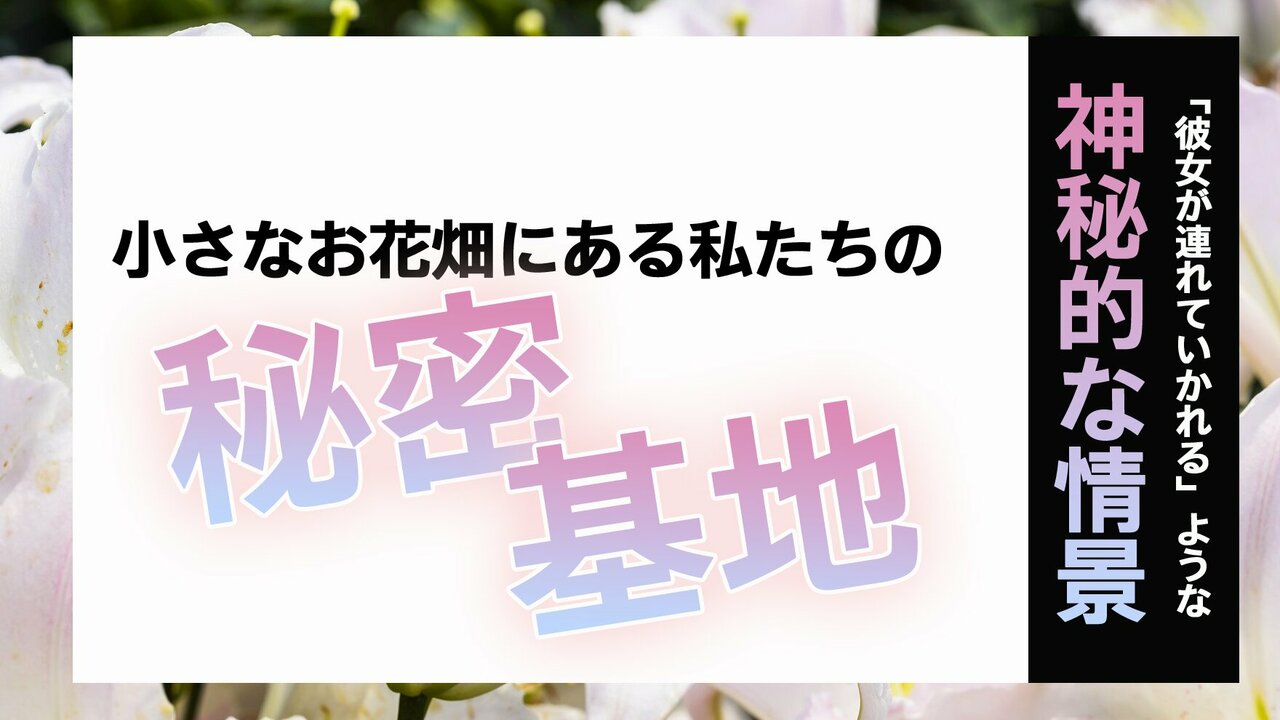4
「私はやっぱり山がいいかな」
高校に上がって初めての夏休み、大勢の生徒が暴力的な日差しに晒されたグラウンドや、蒸し暑い体育館で汗水たらして部活動に打ち込んでいる中、私はクーラーの効いた図書室にいた。大好きな、さよちゃんと一緒に。
この学校では特定の委員会に所属することで部活動が免除される。特にやりたい部活のなかった私は、仲の良いさよちゃんが所属していた図書委員になることを選んだ。……嘘だ。さよちゃんがいる“から”部活ではなく図書委員を選んだ。同じ学校にいるからと言って共有する時間が増えるとは限らない。学年が違えばなおさらで、大半を授業で占められる日中はいいとしても、放課後は部活や委員会などの活動があるから、示し合わせでもしない限り一緒にいることは難しい。
「中学に上がれば小学校みたいにさよちゃんと一緒の時間が増える」、
なんて皮算用をしていた十二歳の私が、いざ中学に上がってみると、休み時間に先輩の教室を訪れるハードルの高さや、部活に奪われる時間の大きさを知り、勝手に騙されたと嘆いたことを覚えている。よく知りもせず誘われるがまま友人と同じ部活(さよちゃんとは違う部活)に入った私が悪いのだが、そういう中学時代の苦い経験があるから、高校に上がったら必ずさよちゃんと同じ所に入ろうと決めていた。
念願叶って、なんて言い方は大袈裟かもしれないが、私は今ここにいる。動機がそんなだから図書委員としての仕事は基本的に退屈だった。本が好きなら違ったかもしれない(いやそれも怪しい)が、残念ながら私は本が好きでも嫌いでもない。受付当番や書架整理など、仕事と言える時間以外は他の委員は皆本を読んでいる中で、課題をしたり隠れて携帯電話をいじったりしていた。
もちろんさよちゃんと当番の日は嬉しかったが、彼女も漏れなく本の虫になっていて話しかけられる雰囲気ではない。そもそも図書室は会話厳禁。受付カウンターという仕切られた空間のすぐ隣にさよちゃんがいるのに、構ってもらえないというのは非常に苦痛だった。
「えー、絶対海だよ」
しかしその日は様子が違った。この学校の図書室は夏休みになると利用できない、ということはなく、夏休み中も開館していて、毎日4、5人は勉強に来る生徒がいるのだけれど、その日は珍しく利用者がいなかった。私たちは受付カウンターを空にして、夏休み中の引継ぎ作業である書架整理を進めることにした。誰に気兼ねすることもなく、お喋りしながら。
「海ぃ?だめだよ海なんて、腐ると体の中からガスが出てきて風船みたいに膨らんじゃうし、皮膚も真っ赤に変色してトマトみたいになるんだから」
「死んだ後の見た目なんてどこでも一緒でしょ?山だってほら、死んだら腐るのは同じなんだし、動物とか虫に食べられちゃうから見た目がグロくなるのは変わらないよ」