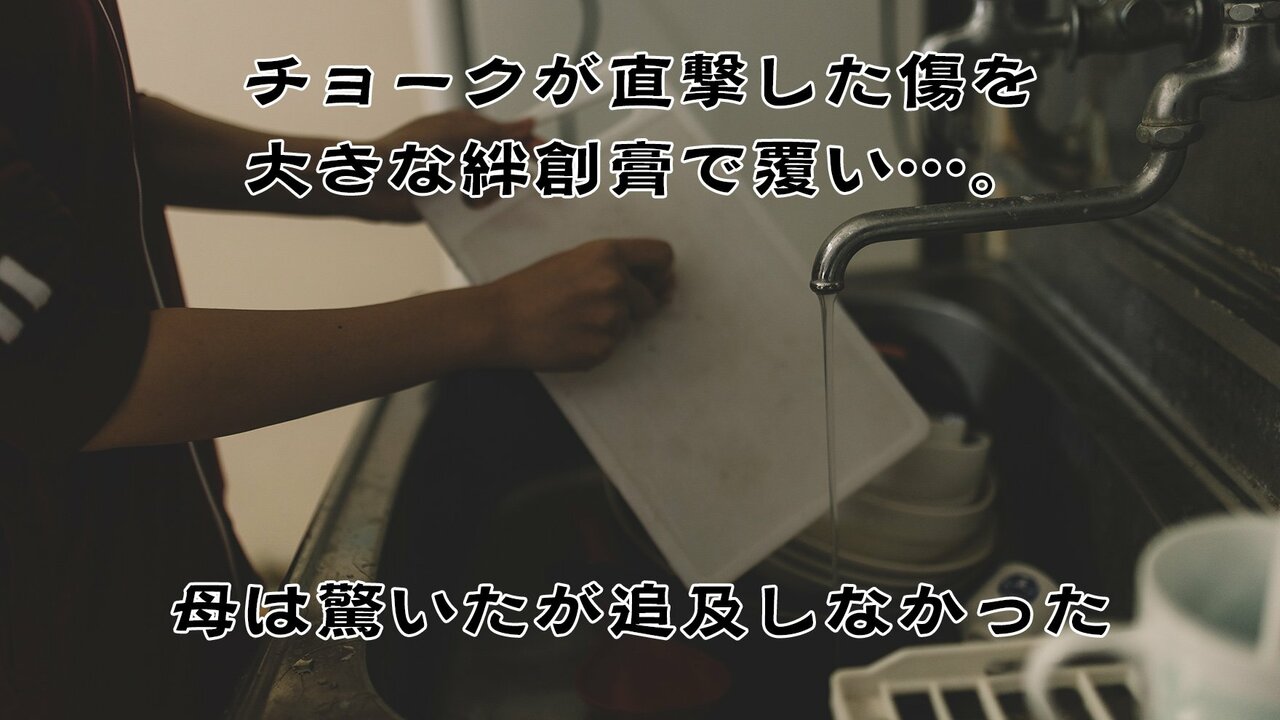【前回の記事を読む】【小説】「お前、女子に人気あるからさ」人気者の同級生にお笑いの練習に誘われ…
そら美が死んだ日
綾乃の家は駅前から少し離れたところで小さな化粧品店を営んでいる。綾乃のお父さんは綾乃が小さい時、交通事故で亡くなった。それから美容部員だった綾乃のお母さんが一人で始めたお店だった。
綾乃の家まで来ると、自転車を店の横の路地に並べて置いた。いつものように店に顔を出し、レジ前にいるおばさんに声をかけた。
「おばさん、綾乃ちゃんいる?」
おばさんは赤い花柄のワンピースの上から半袖の白衣を着ていた。綺麗にお化粧していた顔に汗は出ていない。入り口の自動ドアーが開くとクーラーの冷たい風がスーと純太の体をなでた。
「ごめんね、今、音楽教室。上がって待っていたら、もう帰ると思うよ」と親切に声をかけてくれた。綾乃は六歳の時からフルートを習っていた。
聡と純太は互いに顔を見合わせ、
「じゃあ、良いです」と聡が答えた。
「お前んちに行こう」
聡がサドルに尻を乗せた時に行先が決まった。
純太の家に着いた時、聡は初めにリビングに置いてある猫用の篭の前に座った。
「ねえ、そら美ちゃん、調子悪いんだって?」
と篭の中にいた飼い猫のそら美に声をかけた。
そら美は純太の家の飼い猫だが、野良猫だったから実際の年は分からない。五年前に純太の家に住み着いた時にはすでに年寄りの猫だったかもしれない。灰色の毛で目が青かった。ちょっと洋猫とのミックス的な感じの猫で、どこかの家で飼われていたかもしれないが純太の家からもう逃げ出す事はなかった。
名前は「そら」と付けた。メスだったからいつの間にか「美」が付いてそら美になった。そら子でもそら代でも良かったがなんとなく「そら美」になった。
そら美はいつも篭の中で丸くなって寝ていた。呼んでも知らんふりで、名前が気に入らなかったのかもしれない。
大概は篭からはみ出ていた尻尾も足も今日は全部篭にすっぽり入っていた。
「まだ生きてる?」と聡が言った。
「生きてるよ」
純太は学校から帰ってきた時に篭を覗き込んで息をしているかどうか確認していた。
餌や水はキッチンのところに置いてあったのに一週間前からそら美の篭の傍に移動した。もう、歩くのもやっとだった。
「水とか飲みたいんじゃない?」
と聡に言われて、純太は自分の指先を水入れに入れて、濡れた指をそら美の口に当てた。そら美の鼻先から口のあたりまでカサカサに乾いていた。
「飲まないね。……もう死んでんじゃないの?」不安そうに聡が言った。そして、篭の中のそら美を指で突っついた。
「やめろよ」
純太は飼い主の特権として篭に敷かれていたバスタオルごと、そら美を抱き上げた。そら美は少し目を開けた。そら美と目が合った。
「生きているよ」と純太が言った。