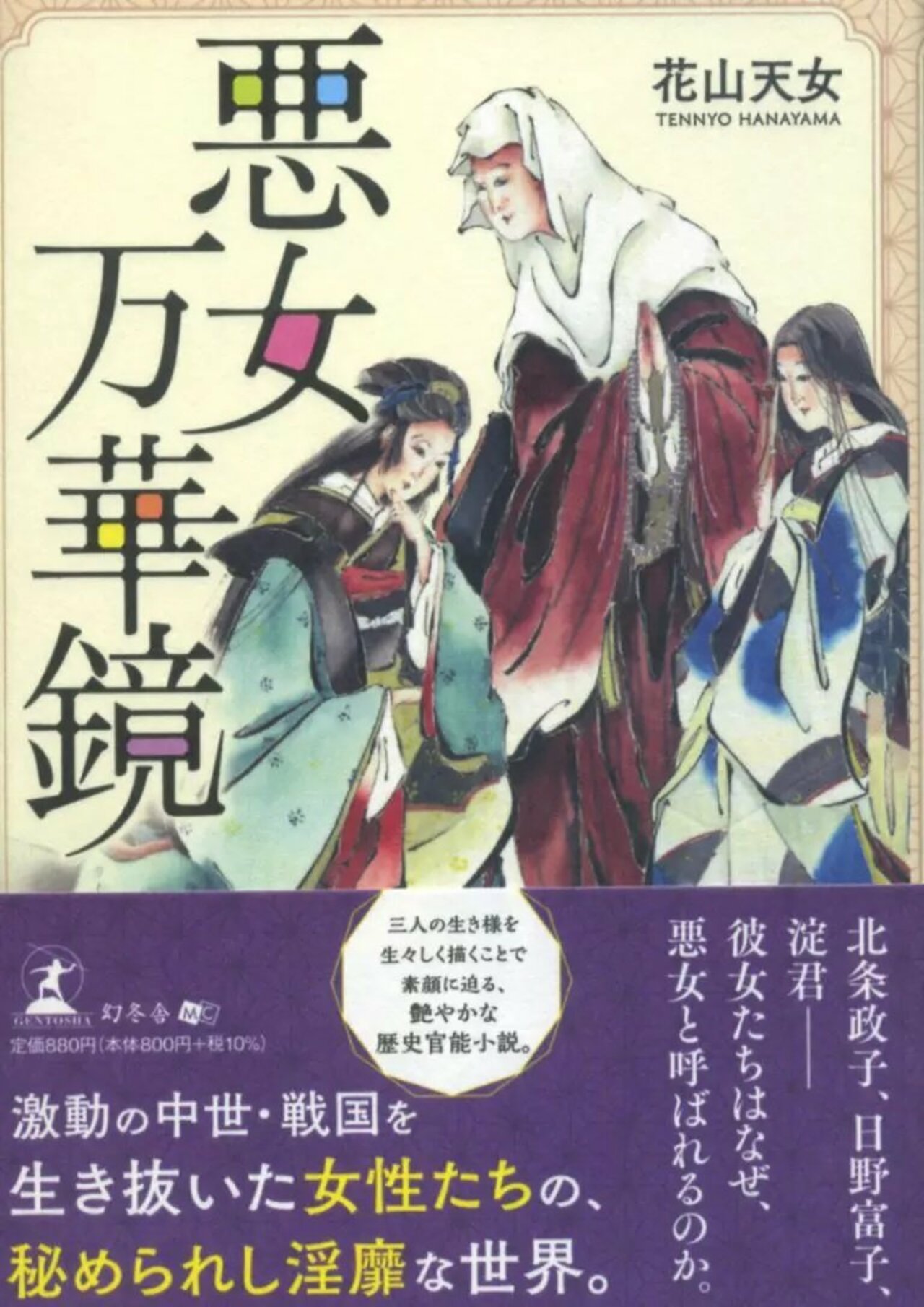「ほう、それは何よりのお申しで、政子どのを儂に寄こすと申されるか」
判官は破顔一笑、二十一歳の売れ残りでも有難く頂戴するとの返事である。判官としては、今でこそ目代として威張ってはいても、内心ではもと罪人という負い目を感じており、そんな矢先に、平家の名門伊豆の豪族の北条が娘をくれようというのだ、加えて娘は美人でおまけにおぼこというではないか。
一方の時政は、娘を無理やり判官に押し付け色よい返事はもらってみたものの、男勝りで負けず嫌い、日頃から親も持て余しているあの政子が、あっさりと恋人を捨てて、素直に判官に嫁ぐであろうか。
血統づきの貴公子然とした頼朝と違って、判官は赤ら顔の大入道で、いつも猪首がめり込んだ肩を怒らせて歩いていて、とても品のよい男とはいえない。
でも親の権利で無理やり押さえつけ嫁づけ、判官殿に夜ごと可愛がってもらえば、政子がいくら気が強いといっても、そこは年ごろの娘、精力絶倫の判官のご指導よろしく、すぐさま新しい夫に馴染んで離れられなくなり、元彼のことなど忘れてしまうに違いない。
「政子、どうか儂の頼みを聞いて判官殿に嫁入りしてはくれまいか、そうでないと、この先北条家の命運もどうなることやも知れぬ。判官殿はあれでなかなかの傑物だと儂は見ているのだが……」
政子は、怖い顔で父親を睨みつけながらもしぶしぶ頷いたが、そんな判官こそいい面の皮であった。