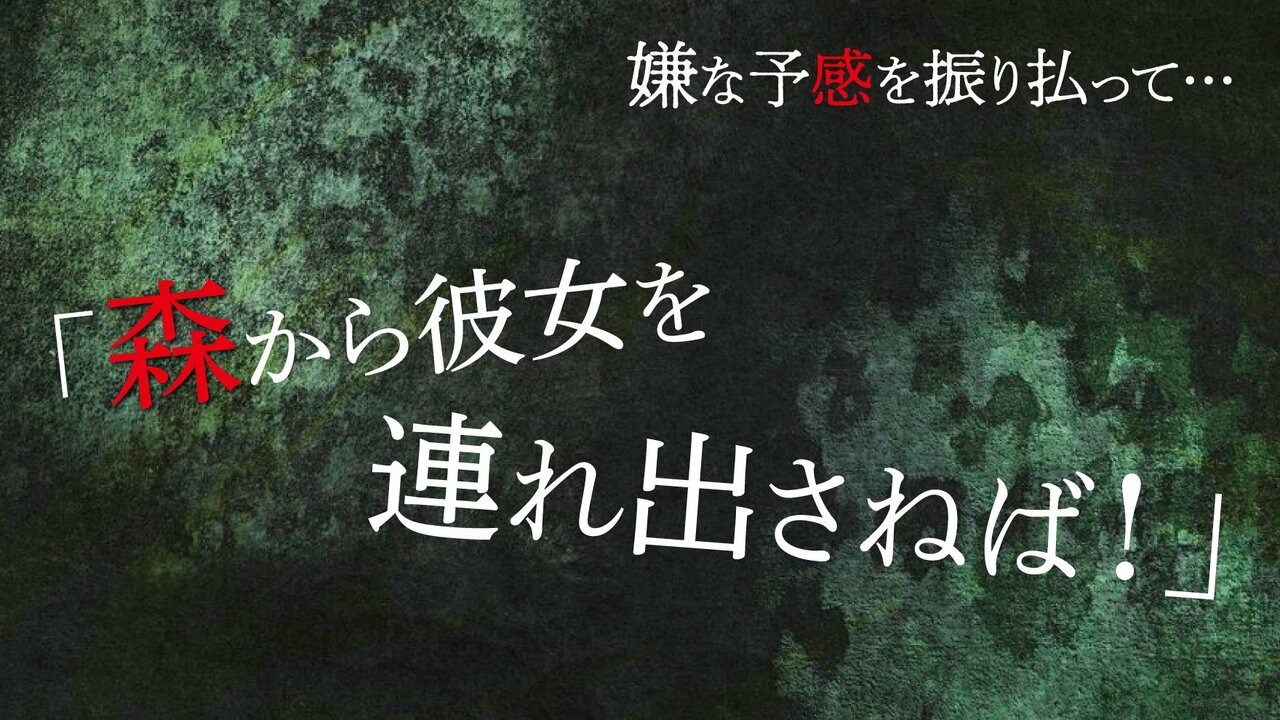お礼を言って、男はスープが入った皿を受け取った。アンは二度もお礼を言われたことにこそばゆさを感じ、すぐに炊事場へと向かった。だが、狭い小屋の中、ベッドの位置から炊事場は丸見えになる。アンは視線を感じ、勝手にプレッシャーを感じてミスをしまくった。
「うまいっ!これはうまい……。こんなうまいものをどうやって……?」
男は、アンがふるまった料理に舌鼓を打った。
「あ、あの、鹿……肉はこの前、張っていた罠に偶然かかっていて……。塩とハーブで漬けました、はい……。ソソ…ソースはベリー類と果実酒を煮詰めて……。よろしかったらおお……、お土産にどどど、どうぞ……」
最後の方は消え入りそうな声で言ったアン。目を合わせることなく、ずっと俯いていた。
「おお!?ありがとう。ウチのカミさんにも食べてもらいたいもんだよ。……それにしても」
と言って、男は辺りを見回した。小屋の中はきれいに掃除されているが、一目見てかなりの年数が経っているとわかる。そして、男にはさっきから疑問に思っている事もあった。
「あの……、お嬢ちゃん!? は、ここに一人で、そのぉ~……、住んでいるのかい?」
この質問に、アンは肩をビクッと震わせた。
「……あの……、その……」
どうしよう……。ジンさんのことは、言えない――と思いアンは目を泳がせ、落ち着きなく答えた。
「は、はいぃ……、一人で、しゅ……住んでます」
「あっ、ああ! そうなんだ……。あ~っと、変に思わないでくれ。その、ちょっと不思議に思っちまって。……うん」
「あっ!でも、時々私の様子を見に来てくれる人はいます」
アンは、男が自分を怪しんでいると思ってそう答えたが、小屋の中は微妙な空気に包まれた。男はそんなアンを見て、それ以上、彼女の素性を尋ねる事はしなかった。
「それにしても。お嬢ちゃんが俺に飲ませてくれた物、アレはなんだい?俺はアレを飲んで、スーッと眠れて、起きたら体調も良くなってたぜぃ?ありゃあいったい……?」
空気を変える意図もあったが、男は自分が再び眠る前に飲んだ、粉状の物の正体をアンに訊いた。