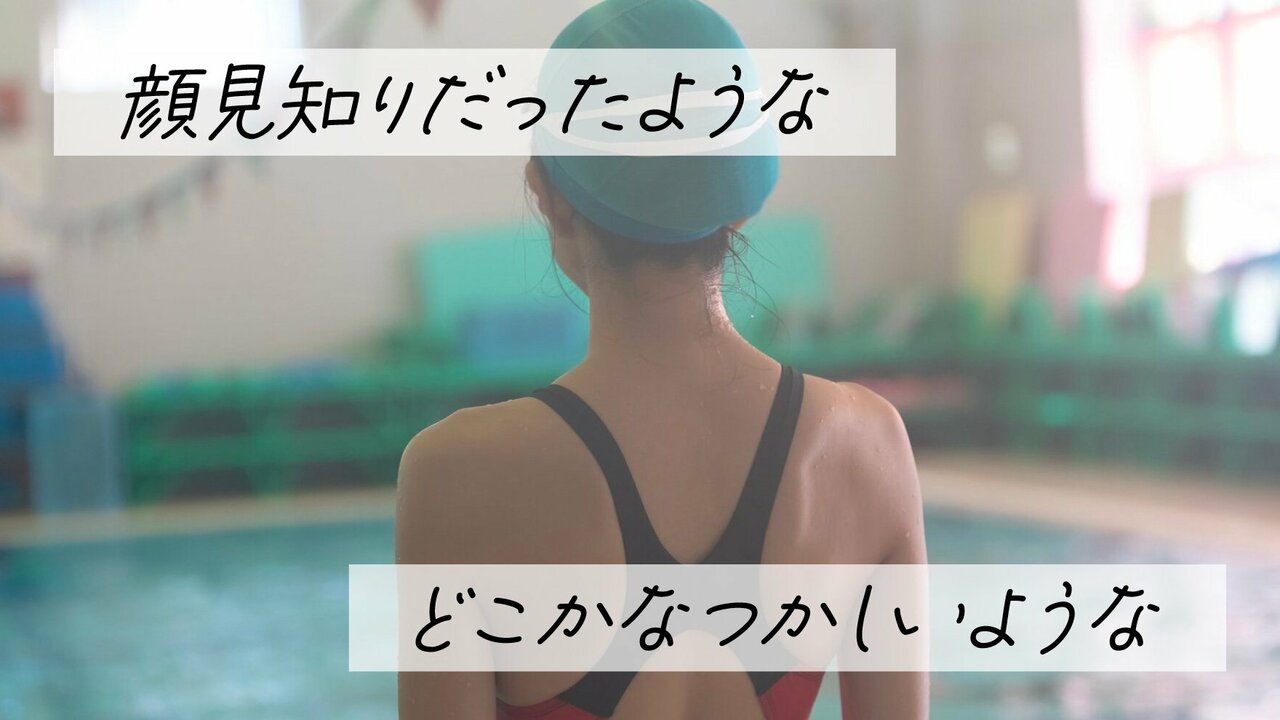「それはそうと、木賊さん、夕飯はちゃんと食べましたか?」
「ええ、多分」
「多分?」
「忘年会に一時間だけ出席したので、お通しと焼き鳥を一本だけ食べて、後はウーロン茶を」
釣木沢の笑う顔を見ながら、
「この人、わたしより若いかもしれない」
と万里絵は思った。
「それでは夕飯とは言えないな。なんか、食べましょうか?」
「でも、今からの時間に食べるのはちょっと」
「確かに、その通りですね。健康上、良くないな」
美容上も良くはない。
「じゃ、送りましょう、お宅はどちらです?」
釣木沢の申し出は職務的で全くさりげなかった。
「いえいえ、大丈夫です。一人で帰れますから」
「とんでもない、これからの時間の若い女性の一人歩きは良くない」
万里絵は笑顔を返した。ここしばらく誰にも見せたことのないような、一気に開いた大輪の花のような笑みが、自然にこぼれた。
「今夜はこのホテルが我が家です。このホテルの三階に部屋を取っていました」
釣木沢が反応した顔を見るためだけにも、部屋を取って良かったと思った。
翌日、朝食を済ませてから室内プールの入口で待ち合わせをした。宿泊者には水着やスイミングキャップ、タオルが無料で貸し出しされる。その都度クリーニングしたものが借りられるし、次の日には別のものを選べるし、買って一枚きりになるよりお得な気がして、指導初日はペールブルーのシンプルなワンピースタイプを選んだ。
九時五分前に釣木沢は現れた。挨拶を交わしたが、なにか思いつめた表情で万里絵をしばらく見つめてから、意を決したように口を開いた。
「木賊さん、ちょっとお尋ねしますが」
言いにくいことを言うのだろう。泳ぎを教える話はなかったことに、そんなことを言い出す気がして、体も心も身構えた。
「わたしがあなたを泳ぎにお誘いしたことで、不愉快になったりする人はおられませんかね?」