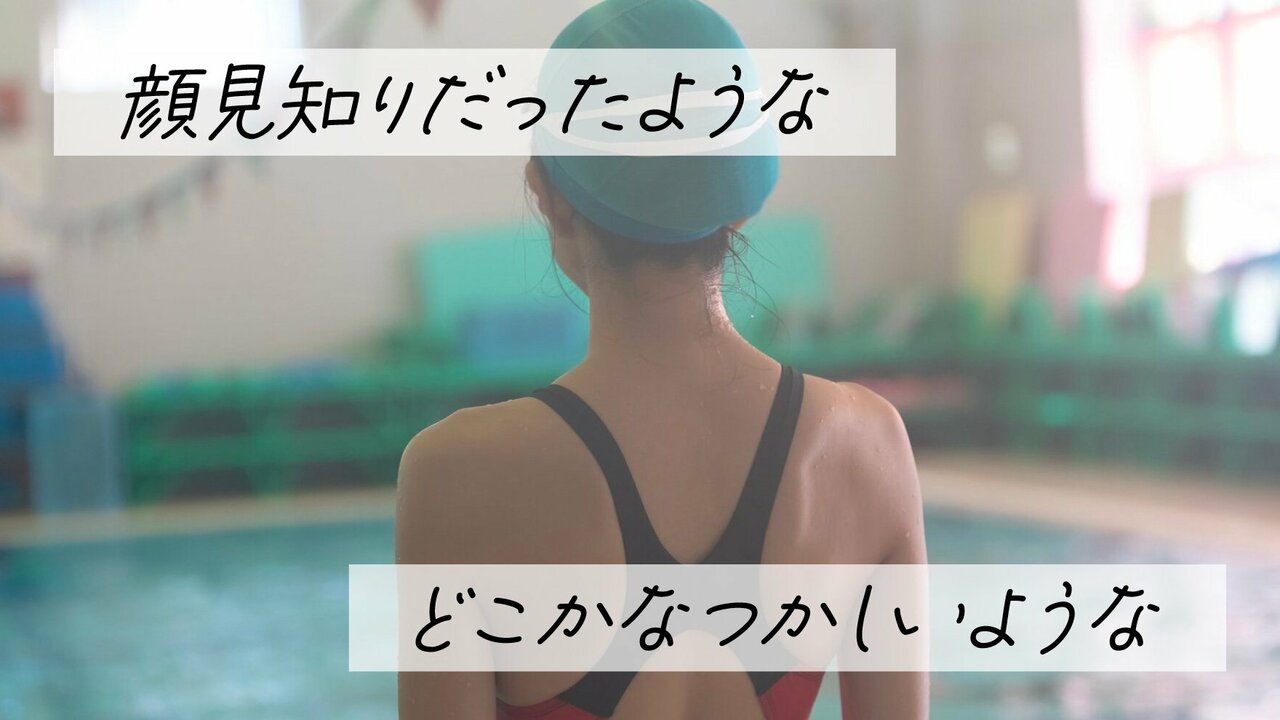自分史の「力強さ」
デスクの上を片付けてから、近くの居酒屋で開かれる出版企画部の忘年会に顔を出した。アルコール類は断って一時間ほどで切り上げると、タクシーでマンションに戻った。部屋に支度してあるスーツケースを手にしてから、待たせていたタクシーで折り返しホテルに向かった。
なんでこんなに急いでいるのだろう。なんでこんなに心が弾むのだろう。万里絵は自分の行動に驚きながらも、タクシーが車寄せに停車すると、鼓動は頂点に達した。ベルボーイに荷物を部屋まで運んでもらってから、室内プールがある地下一階に降りた時には午後九時を十五分ほど過ぎていた。
はめ殺しのサッシ窓の対面に、赤と青のラインが鮮やかに描かれた白いタイルの壁が見えた。釣木沢は十時までは泳いでいると言っていた。プール内に人影はなく、照明も薄暗い。
急激な落胆が万里絵の全身を襲った。
「わたし、馬鹿みたい」
自嘲的につぶやくと、引きつった薄笑いにくちびるが歪んだ。
「わたし、どうかしていた」
泳ぎを教えてあげるよなんて、男の社交辞令を真に受けて、本気になって来てしまうなんて、いい齢をしてどうかしている。本当にあの人がこのホテルに泊っているのかもわからないではないか。
「あーあーあ、やっちゃった」
万里絵は絶望の混じった低い声を、わざとコミカルに発した。現実はドラマのようではないのだ。そんなことわかっていたではないか。しばらく忘れ去られていた躍動感だった。慣れない神経回路を使った妙な疲労感で体がだるくなってきた。とにかく今夜は部屋に戻って休もう、それ以外のことは考えられずにエレベーターに向かった。
「木賊さん」
名前を呼ばれて、振り向いた先には釣木沢の姿があった。ネイビーブルーのチノパンツ、薄いブルーのシャツに紺のカーディガンを羽織っている。乾かしたばかりの髪先が各方向に散らばり、万里絵がいつも画面で見ていた姿とは違って、随分と若々しい。
「探されたんですね。すみません、泳ぐのは九時前までの受付でした。今日は、もう来られないかと思って、着替えてしまったところでした。わたしがラストで一人だけだったものですから、プールも終わりで」
申し訳なさそうにほほ笑んだ。待っていてくれた。あれは約束だったのだ。万里絵が今さっき感じたばかりの落胆を、十五分ほど前の釣木沢も感じてくれていたことになる。
「わたしこそ、すみません。遅くなってしまって」
「いや、とんでもない。出版社にお勤めでしたよね。仕事納めをしてから来られたのでしょ?」
「ええ」
万里絵は首を大きく上下に振った。
「よほど、急いで来られたのでしょう」
「十時に間に合わないかと思ってタクシーを飛ばして来ました」
「明日からはお休みですか?」
万里絵はうなずく。
「ここは朝の六時半から泳げますよ」
「じゃ、明日、出直します」
「何時にしますか?六時半は早過ぎますよね?」
釣木沢の質問に、明朝六時半から泳ぐ自分の姿を想像してみたが、かなり厳しいことに思える。
「九時くらい、では?」
「いいですね。しっかり朝食を取ってから来てください」
「はい」
指導者と生徒のようだが、約束はスムーズに決まっていく。