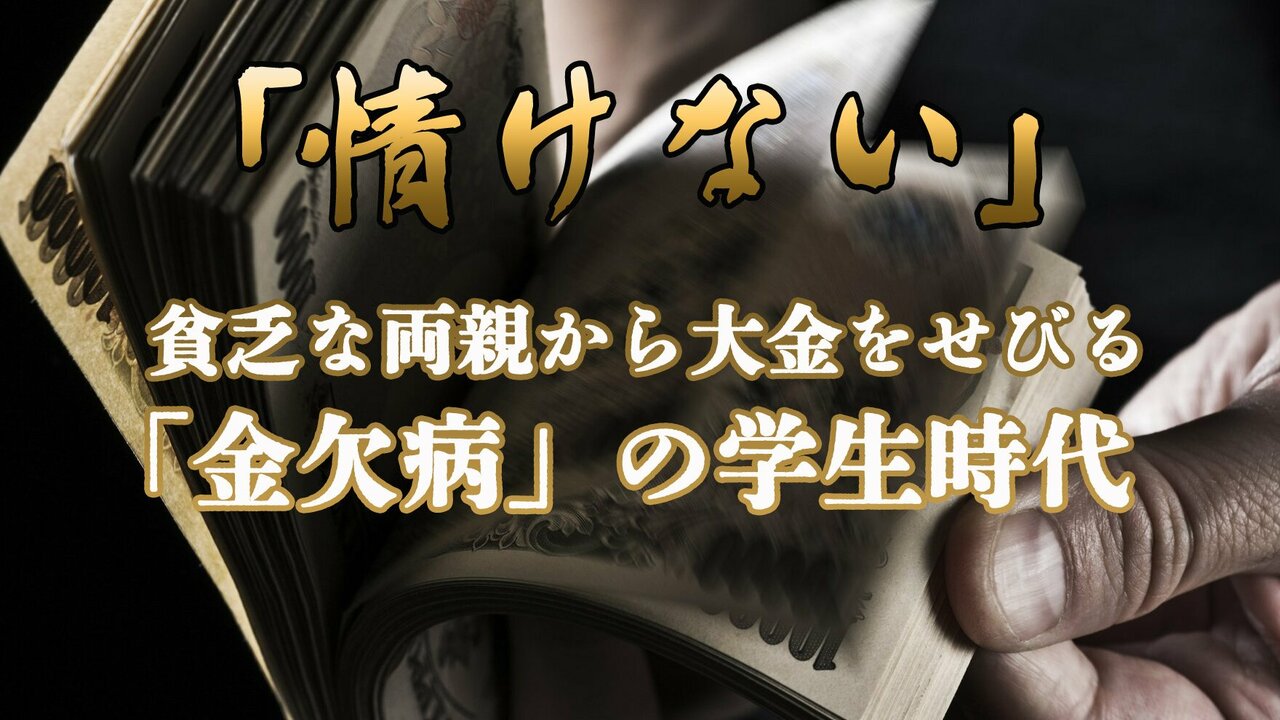第一章 上京
朝の十時頃ともなると予備校に駆け込み、机とセットになった椅子に座る。すると雄太はたちまち眠くてたまらなくなり、つい、うとうとする。
あたかも母や祖母の背で聞いた子守唄が奏でられているようだ。理由ははっきりしている。早朝の四時頃仲間と共に布団からむっくり起き出す。顔を洗った後は、新聞配達の準備をし、準備ができ次第配達に出発する。これが毎日のルーティーンワークだから、いわば寝不足のせいである。
雄太の配達区域は番町を中心とした麹町である。この地域をひた走る。読売新聞市ヶ谷支店所長の成瀬から「今日も元気よく配達頼むで!」と背中をドンと叩かれての励ましの言葉が各自に振りかかる。雄太は「では、行ってきます」と両膝を叩き、空元気で返事をする。
配達仲間の多くは、予備校生や大学生で次々と配達店舖から飛び出して行く。今様のようにオートバイや自転車を利用しての配達ではない。街はまだ夢うつつで、どの家もひっそりと眠っている静けさだ。配達する朝刊は約二百部である。
ベルト帯に包まれた新聞を襷がけする。束となった新聞がぐっと肩に食い込む。速足で家々の郵便受けに投函して行く。出発当初は新聞の重さに悲鳴を上げるが、一部一部配達するうちにその重さも徐々に軽くなってくる。適度の運動からかリズムができて苦痛から解放される。
ときどき番犬に「ウオー! ウオー!」と歯をむき出しにして吠えられるのには閉口する。吠える犬の中にも利口なのがいて、配達当初は雄太を〈不審者〉と見なして気狂いのようにキャンキャン吠えるが、二日、三日も同じ状況が度重なると、犬も〈吠えるのが馬鹿らしい〉と思ってか「ワン!」と一吠え発するも、しっぽを巻きながらその後が続かないで、吠えるのを止めてしまう。
〈ああ! この犬は俺を敵ではなく、味方なのだと理解してくれたんだ。利口な犬だなあ〉と思うようになった。
この街には各国の大使館や政治団体の事務所も軒を連ねている。この中で特に目立つ館は、英国大使館である。楡や杉がうっそうと繁り、つたがからまる塀は、五百メートル四方はあろうか、塀に囲まれた館は外部の侵入者を屏風が立てかけているように拒んでいる。
二月の真冬の朝は底冷えがして、配達する雄太は凍える手に息を吹きかけ悲鳴に近いあえぎ声をあげる。しかし、配達しながら三十分もすると配達部数も徐々に残り少なくなる。新聞と身体とが一体となって、リズム感が出てきて両者が程良くマッチする。