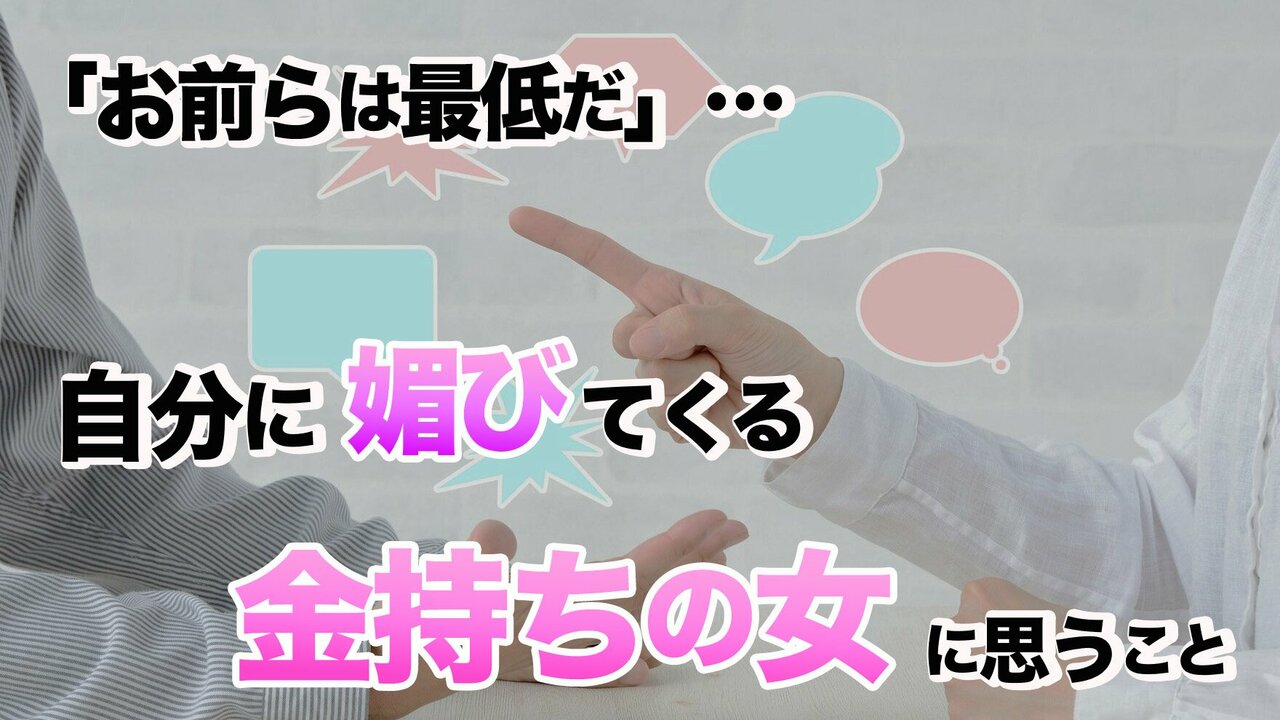1996年 夏の久へ
松林の中に入ると一瞬、目の前が暗くなる。強かった日差しが松に遮られたせいらしい。目も老いたようで、調節機能がこの頃上手くいかない。
蝉の声が松林を震わせ、空気を震わせ、耳の中に潜り込む。毎年夏になるとここは蝉の音で溢れる。蝉は命を音にするような鳴き方をする。蝉を人間の身体ほどにすると、この鳴き声は大阪あたりまで届くとか、何かで読んだ気がする。
日に焼かれた風が吹き抜けた。そろそろ三時を回った頃だろう。時計を見なくても日差しのゆるみ具合で分かる。中途半端な時間が周りにあった。
目の前を腹の皮のたるんだぶちの雌猫が子猫を二匹従えて、横切って行く。子猫はもういっぱしの野良という感じで、母親の後ろでのんびり自分たちの時間を歩いている。ここは海が近いから食料も豊富らしく、野良猫をよく見かける。顔馴染みになったのもいて、見つめると対等だと言うように見つめ返す。
毎日歩くせいか、頭より身体に連れて行かれる気がしながら松林を左に曲がる。家の前の玄関の見慣れた松が見えてきた。少し、門のほうに傾斜しているのは、庭師が手を入れたからだ。門にかかる松は良くないと何かにあったが、門の前に勝手に植えられ、ねじ曲げられ、伸びれば伸びたで門を覆う松は縁起が悪いとか言われる松にしてみれば、いい迷惑だろう。
何も変わらないように見えるが、それでも人間の速度とは違う速さで松も老いているらしい。ゆっくり老いることは幸せか。幸せなど小さい人間が考えることだという感じに、家の前に立った久の上に松がぬっと大きな影を落とした。
その松に覆われた門から入らず横の木戸に回ると、道を掃除している白髪の主婦と目が合った。
「いつも木戸から入られますね。それって、なんかのゲン担ぎとかなんですか」
何十年も道を掃き続けていつの間にか歳とってしまったみたいな顔で、主婦が聞いた。
「いや、そういうのではなく。そうですねえ、身の丈に合ってるからでしょうか」
なるほどねえと言いながら、主婦がまた道を掃き始めた。
確かに何故木戸なんだろうと思いながら、戸を開ける。この木戸は開ける時、軋んで小さな音を出す。その音が日によって微妙に違うのは聞き手の気分もあるし、天候もあるのだろう。それがなんとなく面白いと言えば面白い。が、それが理由で木戸から入る訳でもない。身体が覚えているとしか言いようがない。身体は頭を平気で無視する。