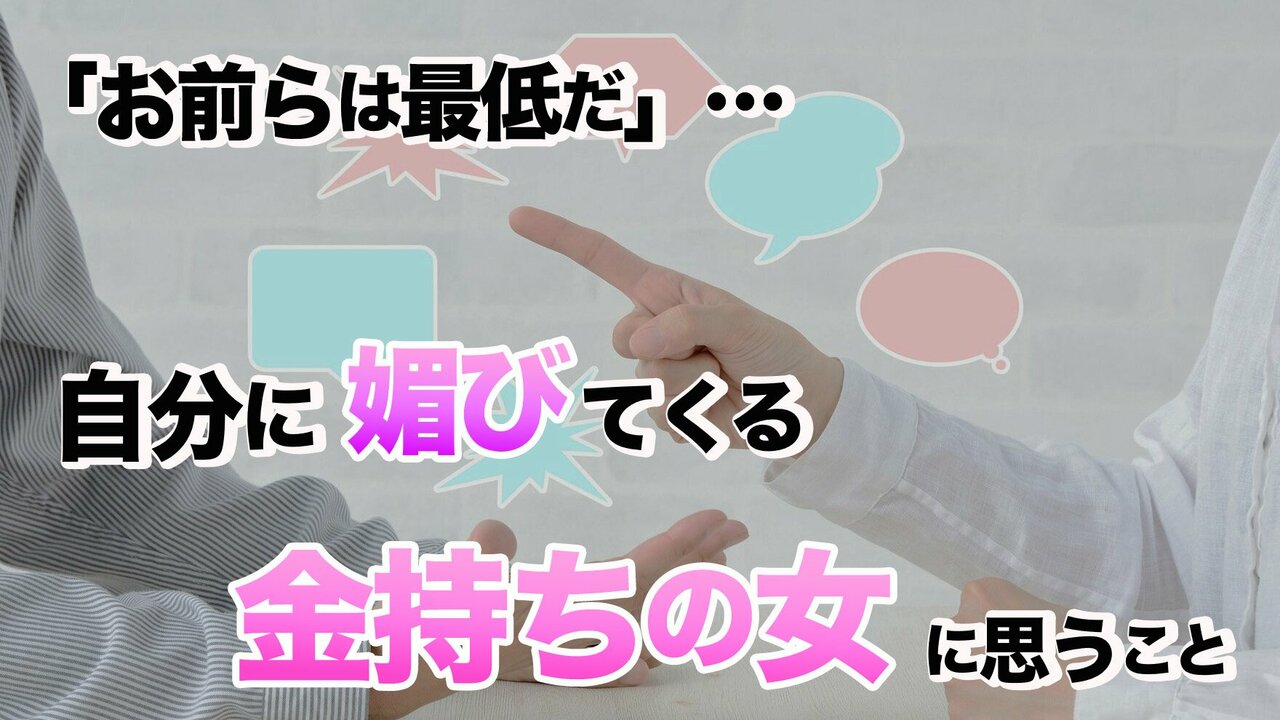台所横にある風呂場に回りシャワーを浴び出て来ると、妻のりょうが白いタオルを持って立っていた。ありがとうと言うと、昔と同じようにはいきませんよと言った。
「何が」
「衰えたとか思ったんでしょ」
「なんでそう思う」
「勘です。お茶、じゃなくて紅茶ね」
「それも勘か」
「そうです、私は勘がいいんです」
「自分が飲みたいだけだろ」
「あなたとは、一心同体ですから」
「いや、それは妄想だ」
「人生自体が妄想です」
禅問答か。廊下を歩いて行くりょうの背中が少し丸い。昔は姿勢が良かった気がするが、それなりに歳を重ねたということだろう。溜め息が出た。何のための溜め息なのか、自分でもよく分からない。溜め息をつくたび、幸福が逃げる? まあ、もともと掴めない幸福なら逃げようもない。
学生時代の友人は年賀状にまだ死ねませんと書いてくる。彼への久の年賀状は、まだ生きています、だ。年に一度の年賀状は二人の溜め息みたいなものかもしれない。
その友人は久と違って、身体の大きいがっちりした男だった。人付き合いもよく、人嫌いの久と何故気が合うのか分からないと周りからよく言われたが、彼はその体格の下に繊細な神経を持っていて、そのちぐはぐさが自分でも疲れると言っていた。今もごく普通の顔をして普通に生きているらしい。
人は生きるためにいろいろな仮面をつける。そしてそのまま歳をとり、いつか仮面をつけていたことも忘れる。それでも年に一度、久への年賀状でその仮面を外し、あいつは小さな溜め息をつくのかもしれない。
風が濡れた髪の毛を揺らして吹き抜けた。それを気持ち良く感じるのは、泳ぎ疲れたせいだろう。全く身体ってのは気持ちの良いものばかり際限なく求め、そして際限なく飽きる身勝手な奴だと思いながら、自分の身体を拭いた。洗い晒しの白いタオルが女の手のように頬に触れ、コウの手を思い出した。
夜、蝉の声がした。りょうが
「食べられたんじゃないですか、断末魔の声」
と言った。断末魔、人は声を出さない。