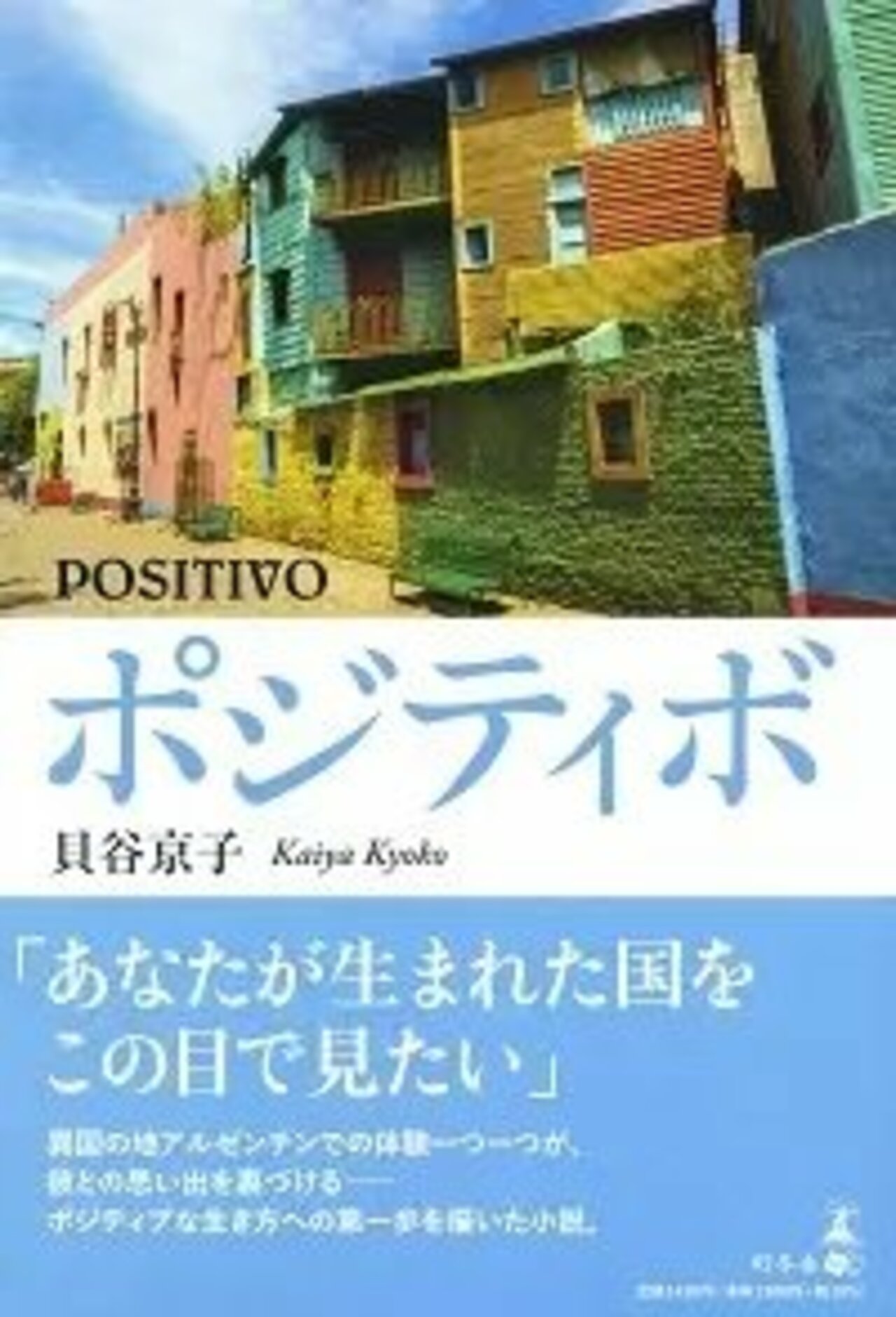ひったくりに遭ったという事実は私の中では思い出でしかなくなって、すっかり記憶の底に沈んでいた。警察に行けば、過去の膨大なデータの中から、私のひったくりの案件は検索されるのだろうか。
新品のショルダーバッグは惜しくはないけどその中には姪っ子たちにやるつもりでおろしておいた新札のお年玉が入っていた。新年を迎えた日に両親の家に家族が集まったとき、お年玉がひったくられたと言ったら、姪っ子らは私を白い目で見た。
思い出しながら、思い出の影が薄くなっていると感じた。その当時ガソリンスタンドだったところが、駐車場になってからもう何年も経っている。
これでもう間違いはないだろうとプリントアウトした文面とモニター画面とを何度もチェックする金髪女性は、入り口から新しく人が入ってきたのに反応して、ごく自然にそちらに目をやると、あからさまに舌打ちをして見せた。
振り向くとそこには私が持っているのと同じガイドブックを手にした男性がうつむき加減で立っていた。タータンチェックの長袖シャツを腕まくりし、色の濃いデニムジーンズに、汚れていない白いスニーカーを履いている。
受付の女性に声をかけられると、英語で話してもいいかと尋ねているようだったが、受付の女性は首を大きく振った。男性は、困ったような顔と同時に、笑うしかないという表情もし、ガイドブックの指ではさまれた場所を開いて、指さした。トモコさんは見て見ぬふりをしている。
「ご愁傷様」と心の中でつぶやく。きっと何かを掏られたに違いないと勝手に決めつける。財布なのかカメラなのか携帯電話なのか。それでも、自分一人でここまで来て、通訳なしで、難局を乗り切ろうとしている彼を立派だと思った。いずれにしろ、彼にはこれから二時間近くの尋問が控えていると、やっぱり勝手に想像する。
彼に向けていた目を戻すと、金髪女性のテカテカに光ったピンクの唇が飛び込んできた。彼女の顔をまともに見られず、トモコさんを見た。私はトモコさんに頼っている。
同じことを何度も聞かれたから、同じことを何度も繰り返して言った。ひょっとしたら細部で少しずつ違うことを言ってしまったかもしれない。
そうした些細なことがきっちりメモされていて、印刷されないパソコンの内部にはしっかり記録されていて、あとになってすべてが「嘘」ということになってしまうのではないか。このパソコンは九十年代半ばのころの図体をしていながら、実は最先端の機能をあの重々しいブラウン管の中におさめているのではないだろうか。