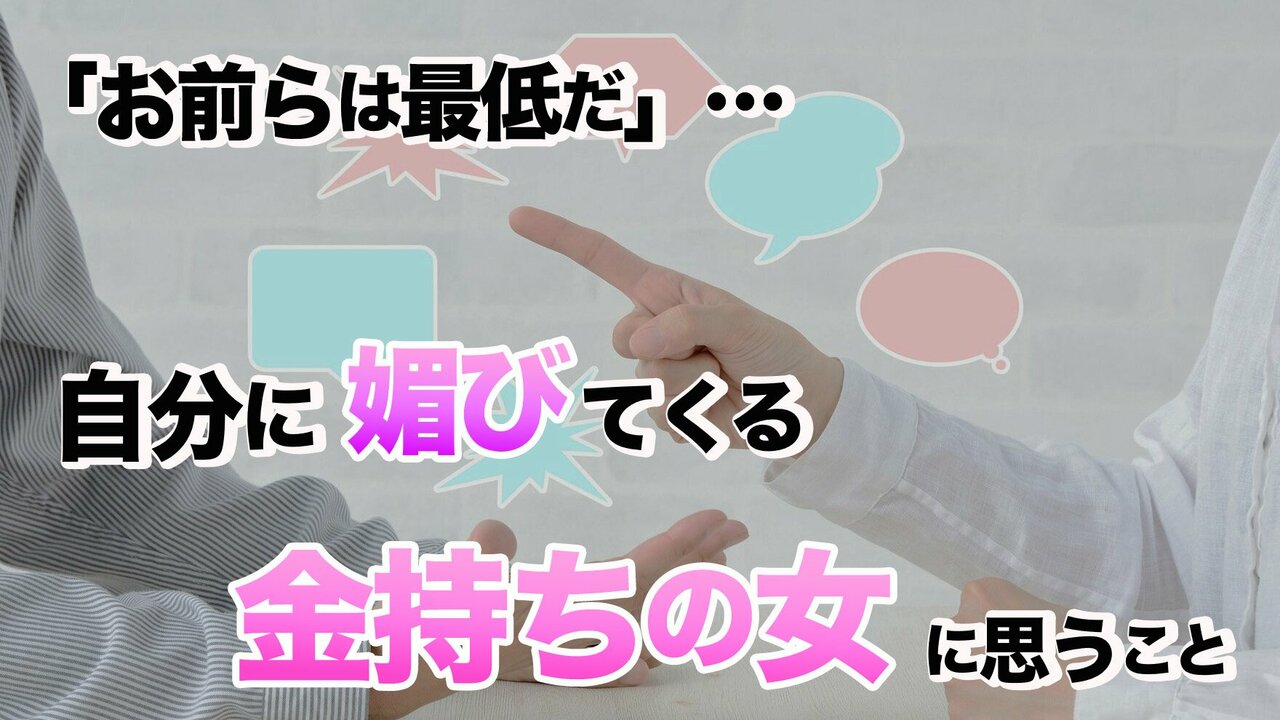その先の水平線が細かく揺れて見えるのは波が荒れているせいだろう。その波が久の足下に打ち寄せようとして打ち損なって、舌打ちみたいな小さな音を立てて引き戻されていった。沖で若者がおぼつかない腰つきで波乗りをしているのを目の端で見ながら、水道の水で身体をぬぐい、Tシャツを着、剥き出しの萎びた足でゆっくり歩いた。砂が足の下で崩れ、踏みしめた先から小さな生き物みたいに逃げていく。
隅に黒い大きなゴミ。と思ったら、人間だった。着古して色の抜けた上っ張りを頭から被った老婆が、松林を背にして座っている。黒い角張った顔の中に細い目と頑固そうな口元が見える。横を通り過ぎる時、声がした。
「あまだった」
と、言ったようだ。そう言われればかなりの歳らしいが、出ている足はがっちりしているし、顔の皺の入り具合も深くて、長年日に晒された感じがなくもない。
「海女さんだったんですか」
「毎日毎日もぐってなあ。でも、もう泳げねえ。ここまで歩くのが精一杯だあ」
「いずれ、こちらも歩くだけで精一杯になります」
「なんちゃあない」
老婆が呟いた。そう、なんちゃあない。人生なんて、過ぎてしまえばなんてこともない。老いるとみんな哲学者だ。
「今日は水平線が揺れて見えますね。波がかなり荒いようだ」
老婆はもう久に話しかけたことも忘れたように、海に目をやっている。老婆が見つめているのは楽しかった時間の先の死。と思うのは、うがち過ぎか。