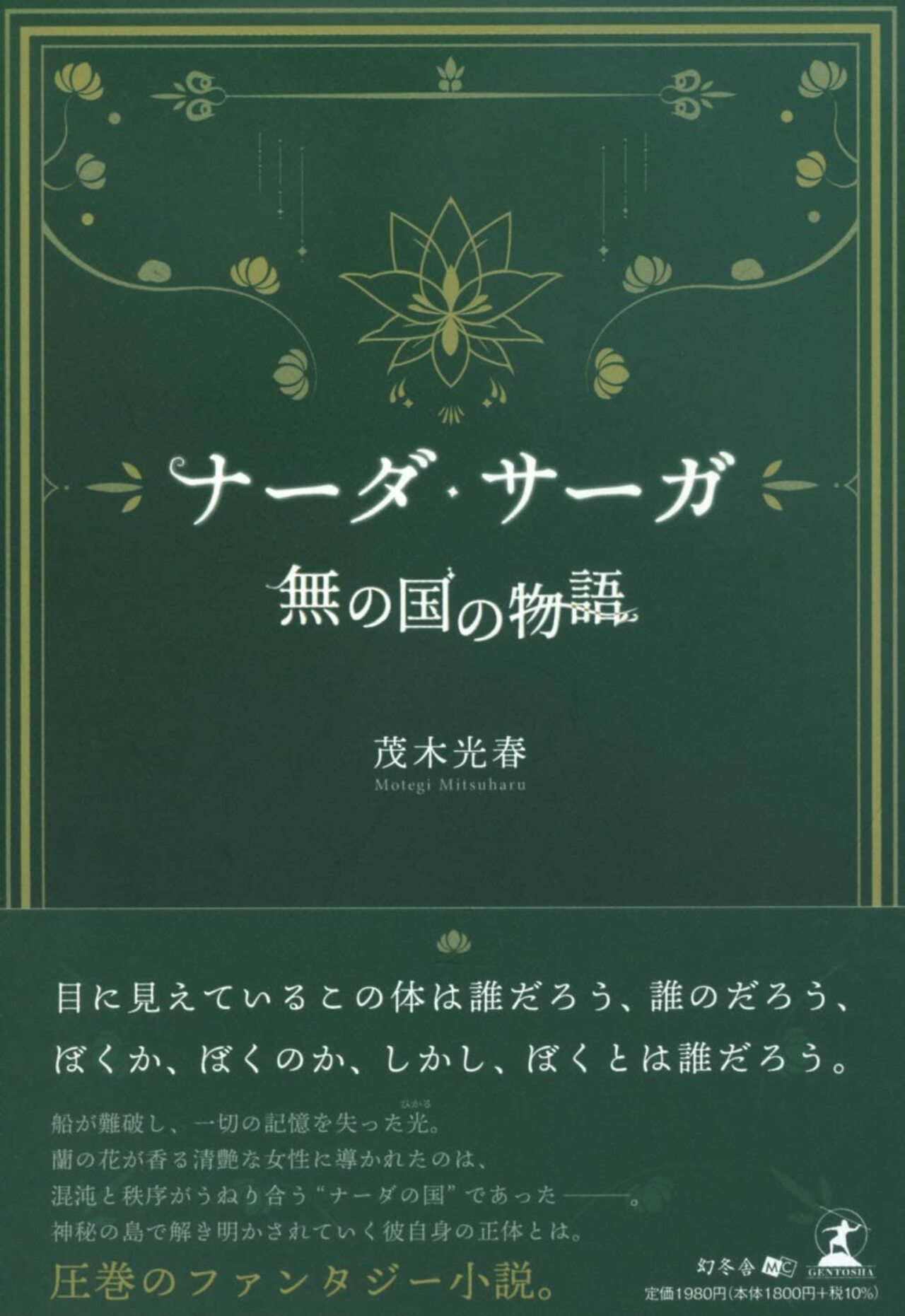「あのう……」
女性は濡れた薄桃色の唇をかすかに開いて、そう言った。そしてぼくをまじまじと見つめた。深い恐れを知らぬ純なる瞳、純粋な眼差し、香しい、花の芯を秘めた、妖しいまでの美に満ちた瞳をもって、ぼくを見つめたのである。
「あなたはどなたさまですか」
真っすぐに、その声は花の香りのごとく、ぼくの顔に向かって漂い来たった。
ぼくの方こそ、最初にその質問を放つべきであった。そのことがまず悔やまれた。そして、直後、自分が質問に対してどのような答えをも見出せないことに気が付いた。
「ぼくは、ぼくは……」それ以上に言葉が出て来なかった。
「何も思い出すことができません。ぼくが誰であるかさえ分かりません」
そこまでは言うことはできた。
「もしかしたらあなたはこの浜辺に漂着した方ではありませんか。この島、この国へは、今までにいろんな人々が漂着し、流れ着き、打ち上げられ、たどり着いて参りました。ですから、もしかしたらあなたは船が難破して、かろうじてこの島に流れ着いた方ではありませんか。そんな記憶はございませんか」
「いいえ、分かりません。まったく記憶がないんです」
「そうですか。ここは嵐の通り道ですから難破船も多く、それに海のただ中でいろんな敵対する国の間にある島なので、難民も多く、亡命者も多いのです。お洋服が破れてお体も傷だらけ。ああ、頭のところ、毛髪が血で濡れています。やはり難破に遭った方に違いありません」
女性は、女性と言っても十八か十九の若い女性。だから少女と言ってもいいのかもしれない。その少女が、奇妙な断固とした口調でそう宣言した。
「いずれきっと思い出す時が来るでしょう。急ぐことはありません」