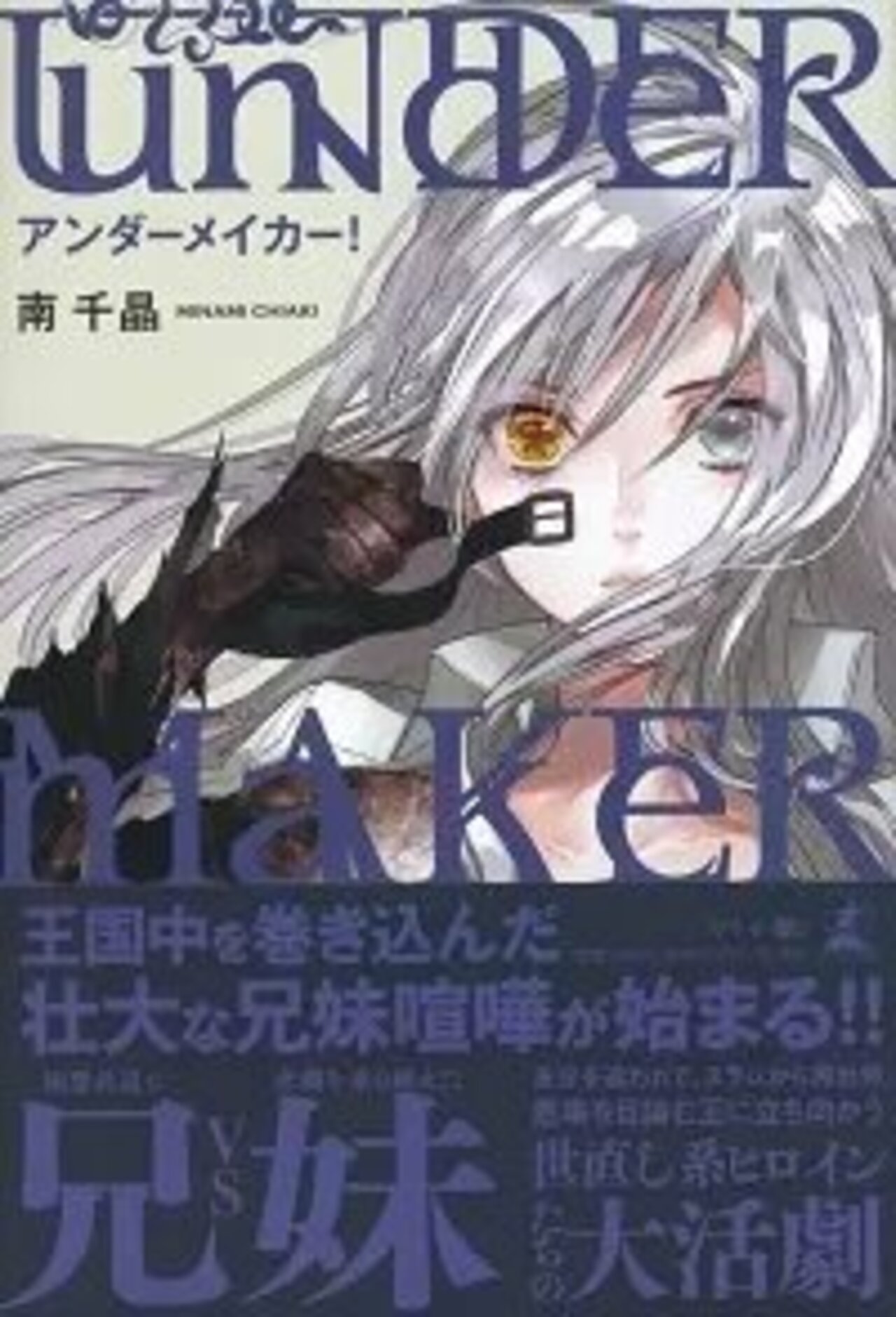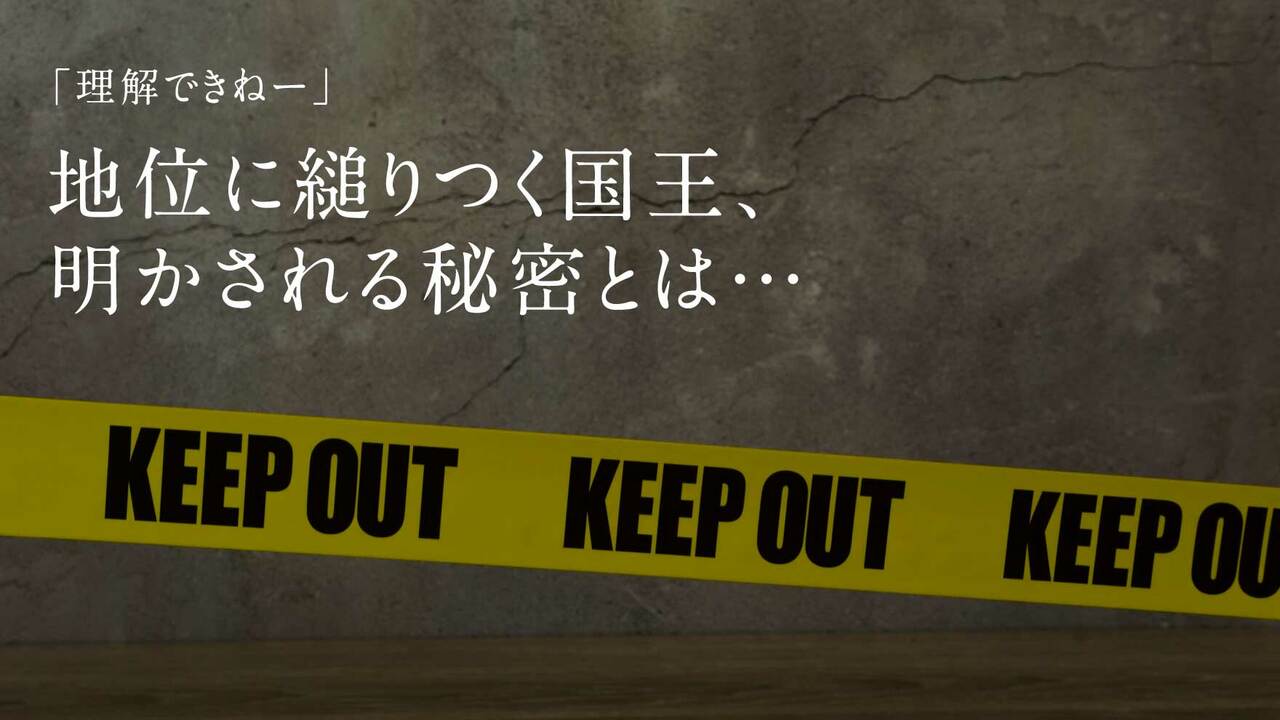「で? 今は傍にいなくていいのかよ?」
「奴は今頃、女と戯れているさ」
「男って、なんですぐそっちにいくんだか。理解不能だ」
「これは心外だな。俺は、まだ一度たりとも君に手を出してはいないぞ」
「未成年になんつー事を言うんだ、てめぇはっ」
「俺と君は婚約者であろう」
「親が勝手に決めた約束だろ。落ちぶれた俺にその資格はねぇよ」
「とりあえず」
送り状を手に、桐弥の視線が落ちる。
「さすがの君でも王族世界までは忍べまい。どうするつもりだね?」
彼女は、右目を隠した眼帯に手を触れている。どこを見るでもなく、虚ろな視線。桐弥の声は果たして聞こえたのだろうか。
「葬儀人?」
「あ、わ、悪い。これからの事だよな。とりあえず、次はIDカード探すんだろ? 浩輔! おい、浩輔!」
寝室に向かって歩き出す彼女の背中を、桐弥はただ見つめる。
「辛かろうが、これが君のやるべき事だ。逃げるな、立ち向かって―最後は俺に微笑んでくれ」
IDカードはすぐに見つかった。これも人間の心理なのだろうか、身近に置いておく事で安心して見つかるまいとしたのだろう。そう、同じ部屋の文机の中にまとめられていた。
「死んだ人間は、IDカードにその旨を上書きして失効させなければならん」
そう言ってIDカードの束は桐弥の手に渡り―思った通り、浩輔の母親のものはそこにはなかった。浩輔は落胆するようにその場に崩れ落ちたが、
「っ、ちくしょうっ! こいつらへの報復は俺がしようと思ってたんだ! 俺を捨てたこいつらに、俺が復讐してやろうと思ってたんだ!」
と、目的がなくなってしまった事を悔やんでいる。
「浩輔」
「……は、かっこ悪ぃよな、こんなの……あんなに一族の連中を見返してやるって叫んだのに、それを見てくれる血縁者はもういねぇんだ」
「海川家の当主はお前だろ。母親が放棄した今、お前がこの家の主だ」
「貴族世界に留まる事を国は許してくれねぇってのにか? はっ、慰めかよ。くだらねー」
「くだらないと思うならそれでいいさ。俺達はてめーの母親を追うし、お前は好きにすればいい。元より、事件現場がここじゃなければ連れてくるつもりはなかったんだからな」
「……行くのか、国王の住む世界に」
「行くさ。ま、準備が整うまで、まずはこの手紙の復元が先だけどよ」
散らばった紙切れを残す事なく栗栖に渡す。
「それより、先に聞いておきたい事がある」
「なんだよ?」
「この海川家で一番の家宝はなんだ?」
浩輔は分からない顔をしていた。だが彼女は、辛うじて読む事のできた“海川の” “渡せば”、この二つの単語が気になっていたのだ。推測するならば、“海川の家宝を渡せば悪いようにはしない“という言葉も簡単に作れる。それ故、浩輔に聞いたのだが―まだ当主としての責務を教え込まれていない彼に心当たりはなかったようだ。