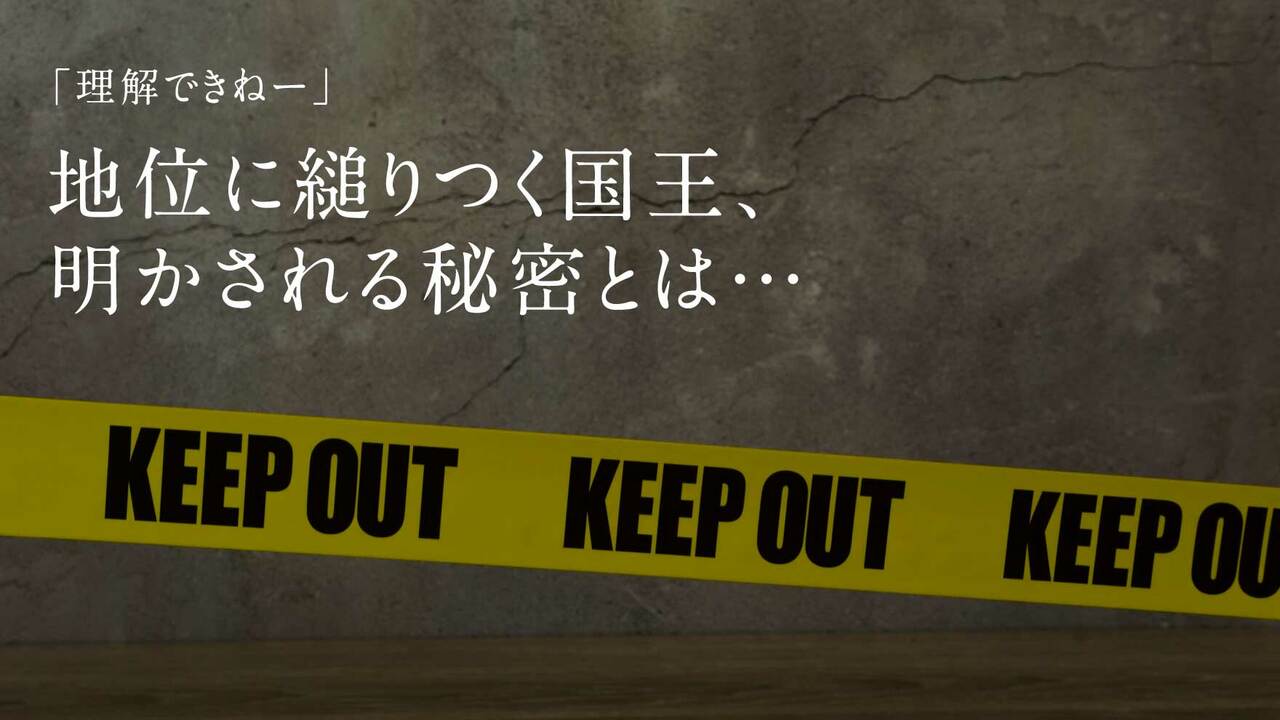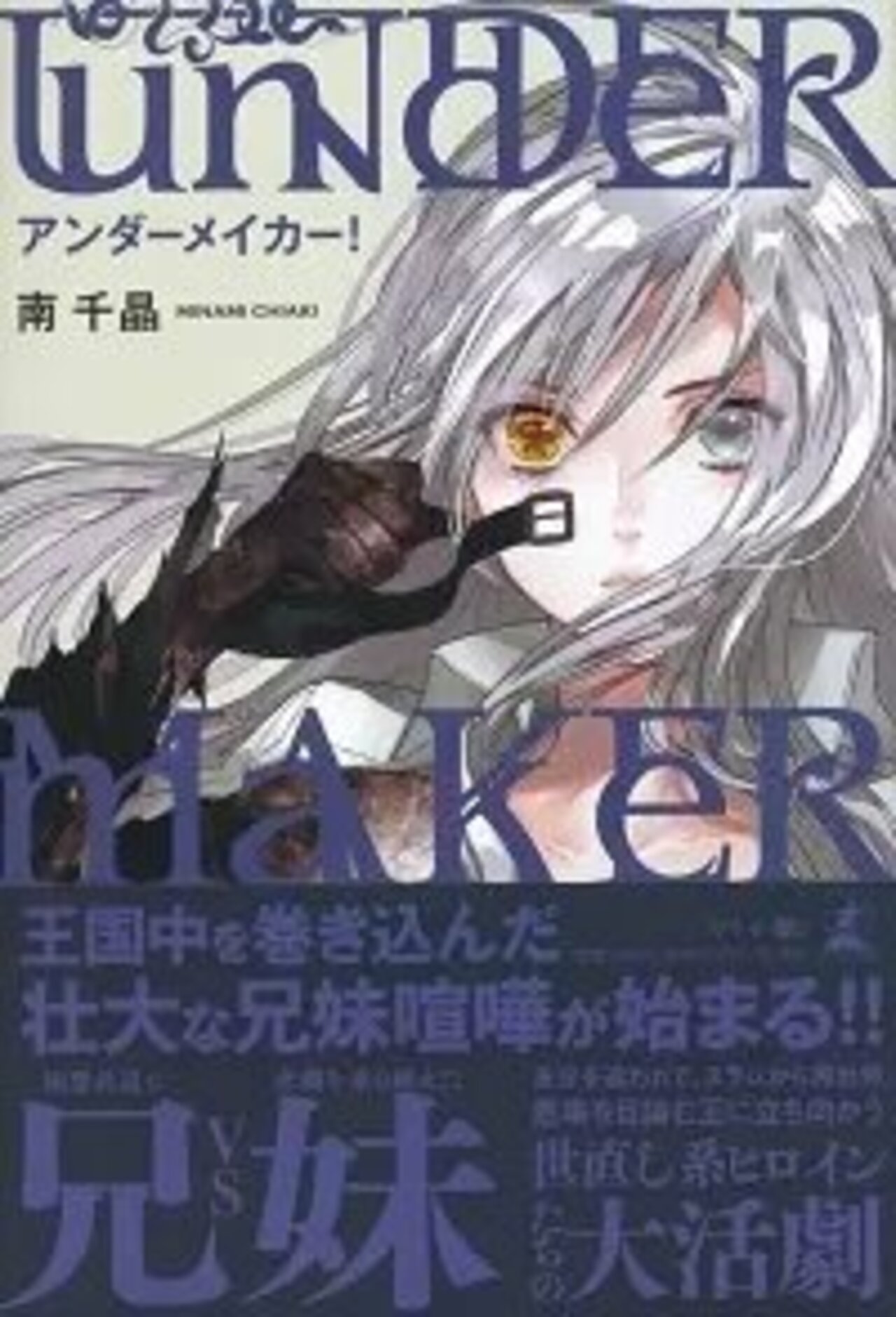海川家
「手紙―と言っていいのかは分からんが、この筆跡、君なら分かるのでは?」
「七年も経ちゃ筆跡も変わるだろ」
「荷物の搬送先は国王のいる王族世界なのだぞ? それに関連していると考えるのが妥当なのではないのかね?」
「そのへんは、国王側近のてめーのお仕事だろ。俺にゃ関係ねー話だ」
「この一件は、君に要請した仕事の筈だがね?」
「なら今回の依頼達成の報酬はなんだよ?」
「そうだな、ここまで来てもらって土地の権利書というのも味がない。ふむ、……国王の情報、でどうだね?」
「興味ねーな」
「人工的に右目を造っているとしても、かね?」
彼女の顔色が変わった。
「造ってる、だと?」
桐弥の胸倉を掴み、引き寄せる。
「この眼はそう簡単に造れるものじゃねぇ!!」
「そう、ただの見せかけだ。だが、彼は自前の右目を犠牲にしてまでも国王の座に就いているのだよ。貪欲というか我が強いというか」
国王として天が定めた掟。それは特殊な右目を持って産まれる事だった。
「止めなかったのか。諌めなかったのか、側近だろ!」
「彼は俺に命令した。王族であり一国の国王の継承者の証である右目を造れとな。だが、何度も失敗しては彼は喚き叫んだ」
健康な右目を抉って人工的な目を何度も入れて。失敗の度に痛みに耐えられず叫んで。
「……そうまでして国王の座が欲しいのかよ……理解できねー」
「俺も国王軍総帥という立場にはあるが、技術局長を務めているのは君も知っていよう」
「まさか、お前―」
桐弥は悪戯な笑みを浮かべた。
「粗悪品ばかりを提出している。なにせ、特殊な目の造り方などはどの文献にも載っていない事だからな、責められる要因はあるまい」
「いつか気づかれるぞ」
「その時はその時さ。口先だけは達者なのでね」
「自分で言う事かよ」
「これでも、あの男の信頼は俺が一番よく得ている。でなければ、こんな計画も国王直属の側近軍属に任せるワケがなかろう」
まぁ、それは尤もな意見だ。筋が通っている。信用できる人間にしか自分の正体を知らせようとはしないのは勿論の事、そんな事は話さないし持ちかけようともしないだろう。彼女が知ってる現国王は、誰一人として信用せず、自分だけしか信じていなかった男だ。だがそれを、この桐弥が成し遂げた。信頼に値すると、決意させたのだ。