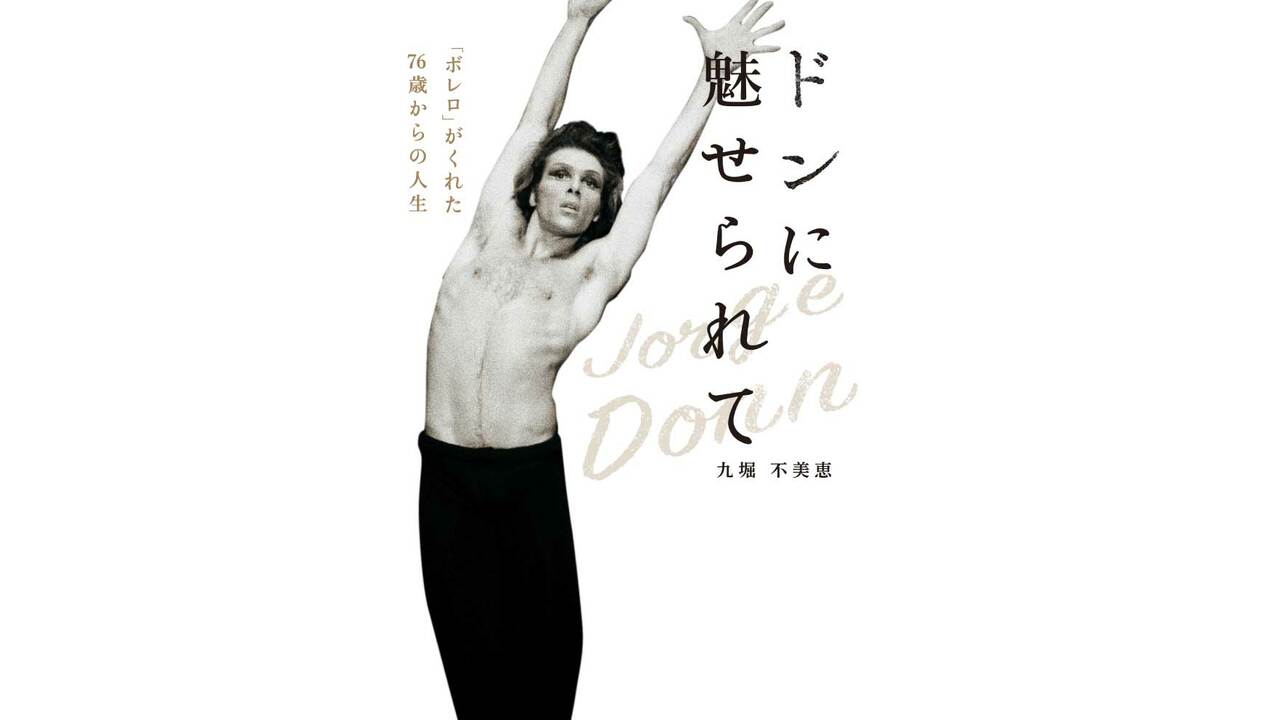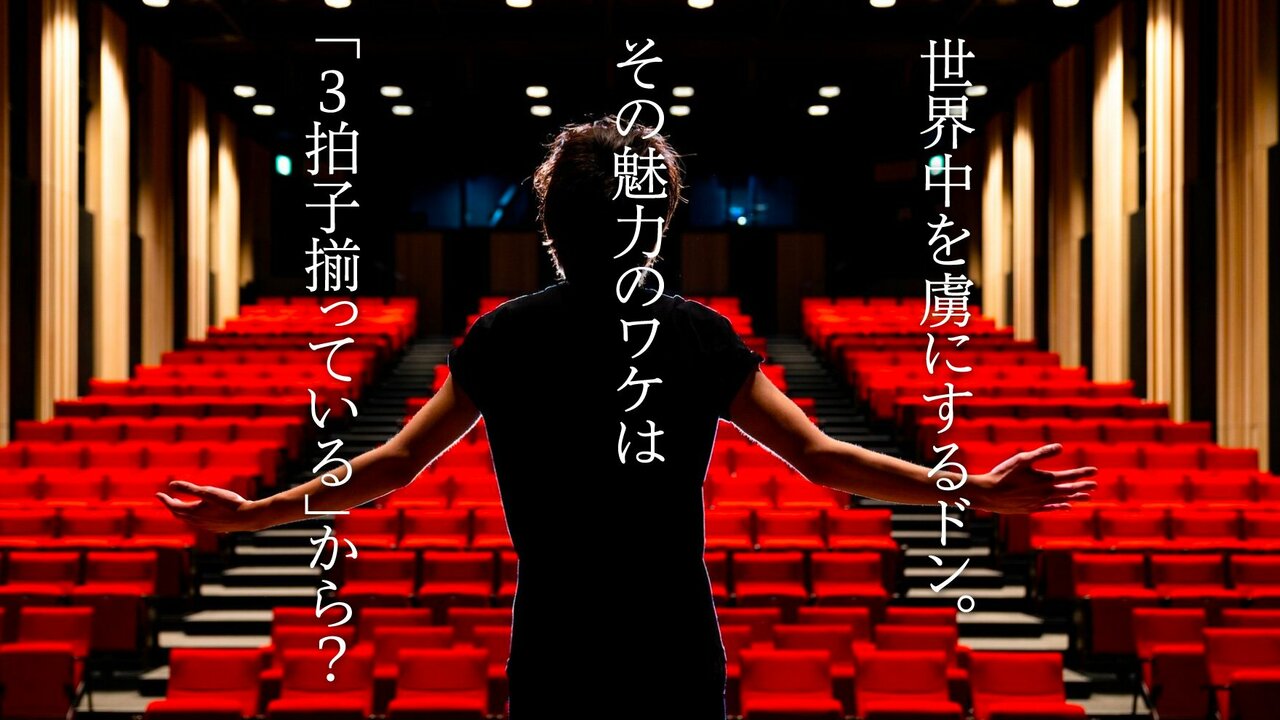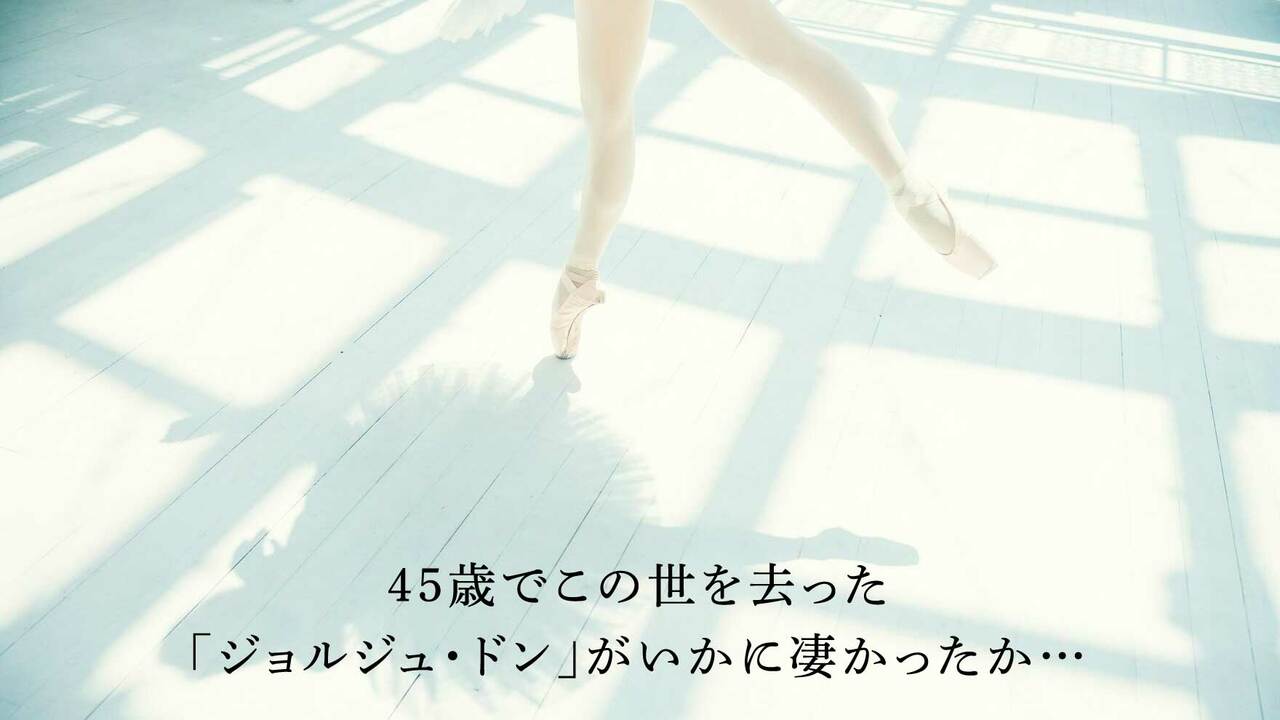第一章 ジョルジュ・ドンと出会う前の日々
金原ひとみ著『パリの砂漠、東京の蜃気楼』が教えてくれたこと
2020年夏から冬へ。
図書館に予約を入れておいた『パリの砂漠、東京の蜃気楼』(ホーム社、2020年)が届いた。暇を見て最初の数ページを読み始めて、その文体の香り高さに静かな感動を覚えた。
金原ひとみさんは37歳、2児の母親で、フランスに暮らして6年。何ともすごい作品だ。感性が激しすぎるため落ち着いて生活ができず、向こう岸まで細い綱1本で、曲芸師のように渡らなければならないような、危なっかしい心の状態で暮らしている。毎日毎日、酒を浴びるように飲む。そんな状態でも2女を育てた。夫がかなり助けてくれているようだ。
この本を数日、ほとんど何もせず読みふけった。当分彼女の作品さえ読んでいればいい、というほど、この本の世界は豊かだ。思考する力がすごい。一つの事柄に対し独白が続く。とても30代とは思えないほどだ。文章力も半端でない。
店も少しずつ客が戻ってきた。売上げを増やすというより、経費を削減して存続させる方法で何とかやっていけそうだ。本音をいえば、まるで孫の世話をさせられているように手間のかかる外国人従業員の世話からいい加減に足を洗いたいので、できるだけ早く店を売却したいが、そのことにも戦略が必要だ。
朝、目が覚めると不安がどこかにある。それはコロナ禍の店のことだ。私が大変なら世界中の人々はもっと大変だよ、私のどこが心配なんだと自分に言いきかせる。
ヨガに出向いた。生徒は3人。先週サボったせいか途中で突然動作を忘れた。そうか、これからこういうことがしばしば起こるんだと気付いた。ちょっと深刻な気分。何とかできていたブリッジができない。以前は毎日、店に行って椅子に座ると、両腕を高く上げて後ろに反らせ、ガラス戸に両手の手の平をしっかり付けて、50数えることを1日に5、6回続けていた。
先々週はそれが功を奏して、今までで一番いいブリッジができていた。それで安心したせいか、多忙のせいか、そのトレーニングをしないでいたら、たちまち腕が上がらなくなった。筋肉ができていないためだろうか。それでも帰路は、しみじみと充足感に満たされ、爽やかな幸せを感じていた。今回は口内炎も悪化しなかったし、疲労も残っていない。気分は上々だ。