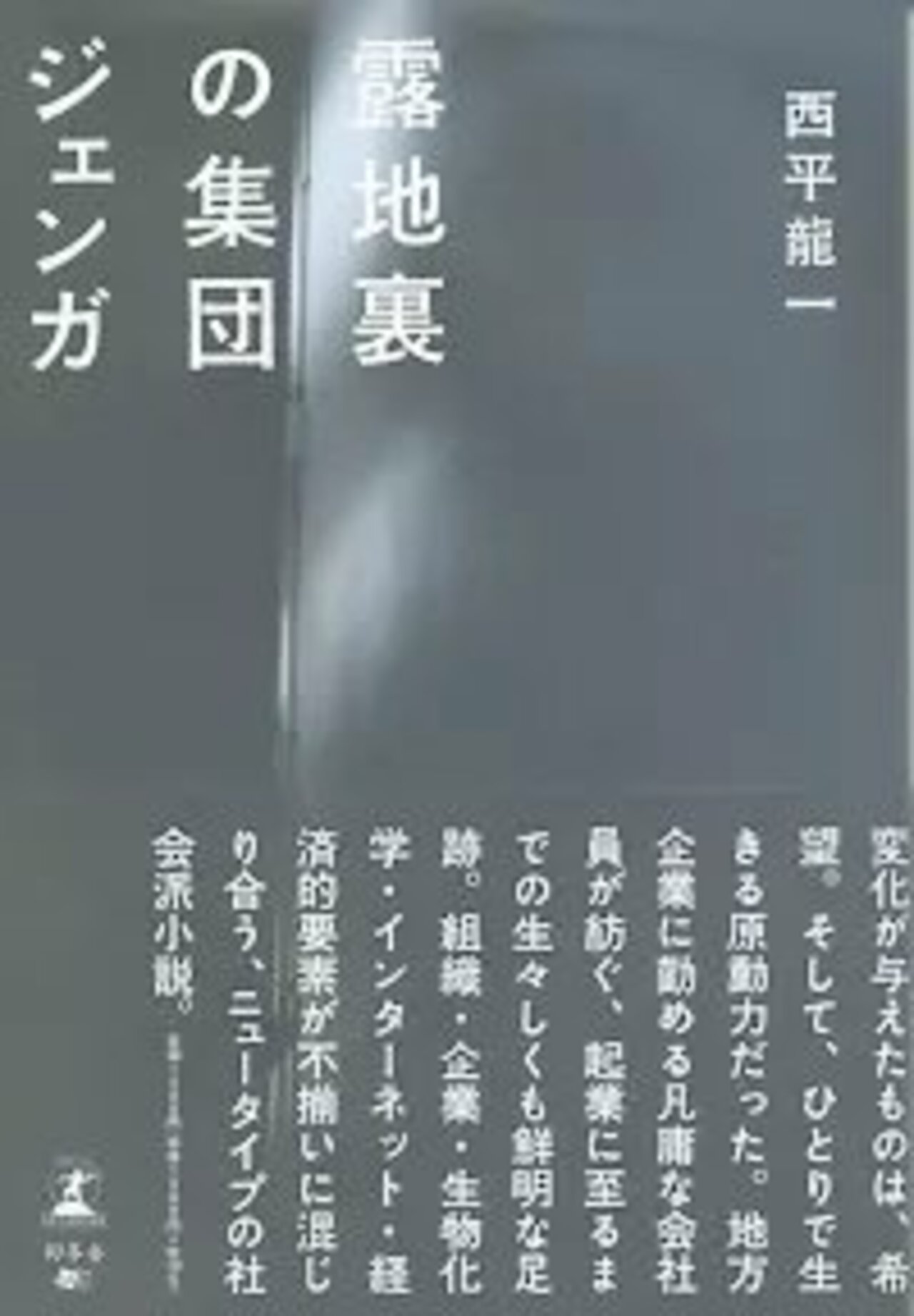【前回の記事を読む】17歳の少年に殴られ続ける…「34歳男性」の痛々しすぎる姿
第一章 洞穴の燈火
新設されたオフィスの大きな硝子戸からは、冷たい風と春の陽射しが溢れている。
朝の九時に迫るころには、開放的に感じた空間も、徐々に息苦しく変化する。無機質な家具と機器。そして人によって被覆されたように感じてしまう。壁にあちこちかかる額縁のほとんどに、美辞麗句な標語が筆書きされていて、「せーの」と号令が響くと、五十を超える声が奇妙に重なる。奇妙なのは、口先だけでシンクロしているからだ。
僕は率先的に声を張り上げながら、周囲の一挙手一投足に目を配る。それは、役員である川島。営業部長の上松。そしてその補佐である森と同じ様子になるのは毎朝のことだった。思考は真空状態のようでいて、口や体は空虚にただ条件反射している。
僕は我社に在籍して、十二年目になる会社員である。世界的な金融危機で、多くの企業がもっとも雇用を縮小したその年に、健康美容事業を営む会社が落魄寸前だった僕を救った。その企業は東海地方の都市にある。顧客は、同じ類の施術や販売業を専門とする実店舗の経営者たちで、それは創業当時から特に変わりがないようだった。
我社は僕が入社した十二年前から、毎年業績も堅調に伸ばしており、年間の売上は当時の約四倍にまで成長していて、いつの間にか零細企業だとはいわれなくなった。決算報告は一般社員にまで、毎年丁寧に公開される場が設けられていた。
そのため事業に無頓着な僕でも、あらゆる環境への変化に目が回ったし、たまには高慢な態度になることもあった。そこそこである個人営業成績と、在籍年数の繰り上がりに合わせて、少しずつだが職位も変わった。職位が変わると仕事が変わった。つまり月間取引件数の上昇トレンドや、一顧客あたりの高い粗利益をマークする要求だけではなくなった。
そして僕に変化を求めたのは、唯一人。役員である川島だけだった。川島は僕に口酸っぱく毎日のように繰り返した。それは例えば、
「健康美容産業の国内経済規模は、疑うことなく伸びていますよ。それは高齢化だから当然ですよね。しかし異様だとは思いませんか。私たちのお客様。つまりね、実店舗はここ十年、上方も下方もしてないのはニシさんも含めて周知の事実でしょう。実店舗の数は伸びている。何を申し上げたいかというとね。総じて取引先は、年々苦しくなっているということなのですよ」
今年四十二歳の川島は、日頃慇懃丁重に僕に接した。どう思われますか? と、尋ねられることも少なくはなく、そういうときは決まって答申していた。
「当社の業績は上がっていますよね。そんなに悲観する必要はないと思うのですが」
営業部長の上松や、補佐である森の意見は、このように楽観的だった。僕は彼らの会議で発する思想や予測を、模擬的に、呪文のように呟くだけだった。川島は取締役なので、営業部門の管掌は、上松らに任せるしかなかった。僕はそれに都合をつけて汎用しているだけだった。