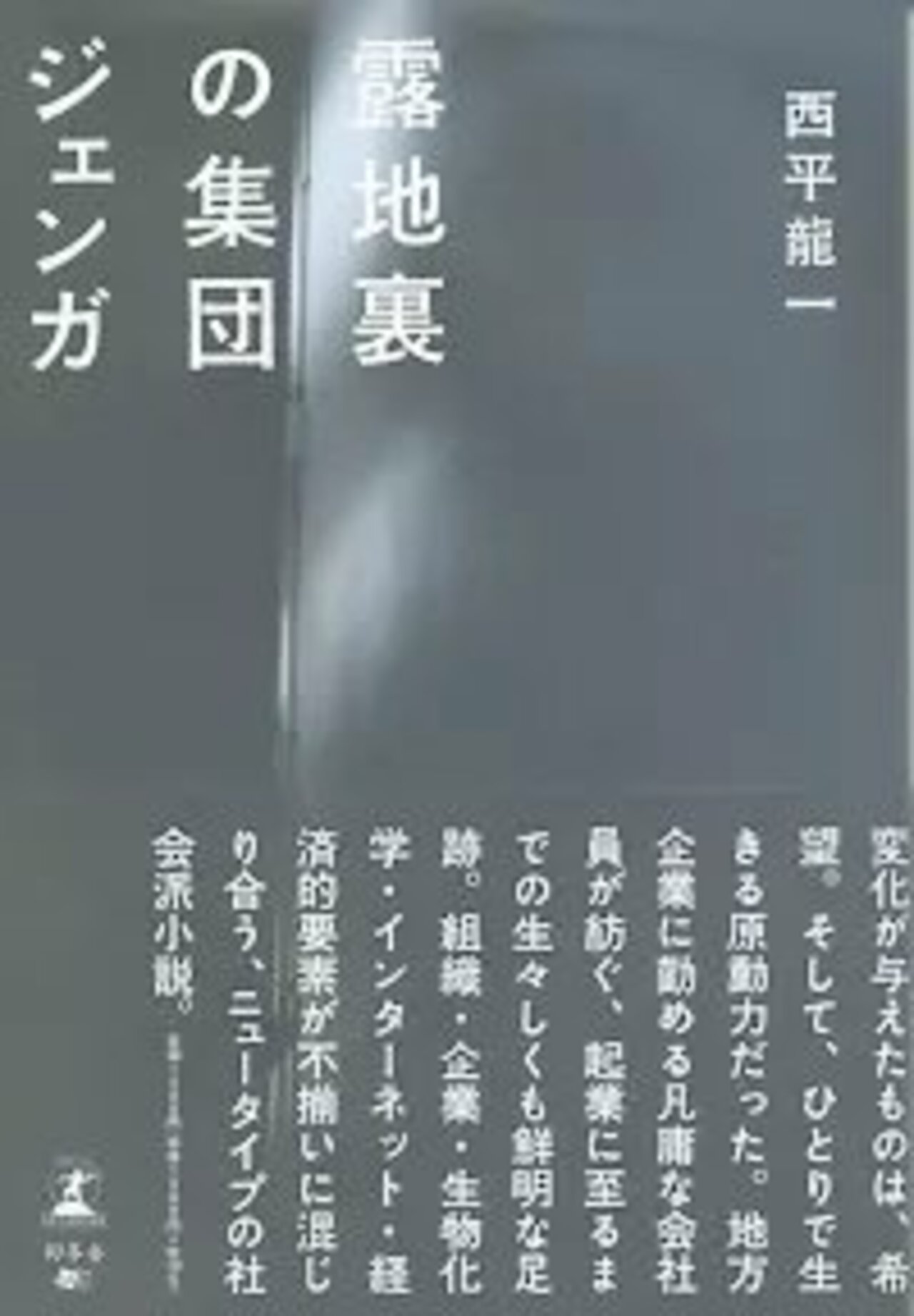川島は挫けなかった。
「それではね。視点を変えてみてはどうでしょう。経済には範囲があります。私たちはね。たまたまその範囲の占有率が上がっているだけなのですよ。そしてそれは努力がなくてもね、上がりやすい環境でもあるのです。それは嘗てこの領域に不在だったリーダーを。その役割を担ったことにあります。それには我々も誇りを持ってもいいでしょう。しかしね、次なる役割はその範囲を拡大することだと。私はそう思うのですよ」
川島は帰路や食事の際に、僕にだけそう伝えた。僕はそれを警戒していた。なぜなら僕が仕事や組織に抱えていたのは、鮮やかな青写真なんかではなく、抽象的な射幸心だったからだ。心境に変化が芽生えたのは、川島が就任して一年が過ぎたころからだった。そしてそれをきっかけに、僕は営業部門の一角から、突然左遷されることになる。
僕が組織で交流をもっていたのは、総務部の冬木だけだった。冬木は数少ない我社の創業人材であって、入社間もないふらふらした時期の、精神的な支柱だった。
冬木は僕に、就任を翌日に控えた川島の存在を教えた。企業が黎明の時代、冬木は休日も関係なく、夜を通して尽くしてきた。だから上位に就任する予定である、外様の川島を快く思うはずがないと踏んでいた。
しかしそれは違っていた。冬木は口をすぼめながら次々熱燗を飲んでいる。頬の紅潮以上に、幾分機嫌がよさそうだった。
「これから会社は伸びるはずだよ。川島さんが指揮を執るんだからね」
「そんなに一人の力で変わるものですかね」
僕は普段嗜むことのないウイスキーを、水で割らずに口をつけた。安っぽいロックグラスからは、不似合いな沈香が放たれている。
「馬鹿、ニシ。おまえはセールスマンだろ。ちゃんと調べていないのか?」
頬が少し淡い色に戻った。井戸端会議みたいに、小さく手を振っている。僕は口を噤んで首を傾けた。冬木は、川島と以前から交流があるようだった。川島は、創業期の我社がコンサルティング業務を発注した、とある企業の当の担当者だったらしい。