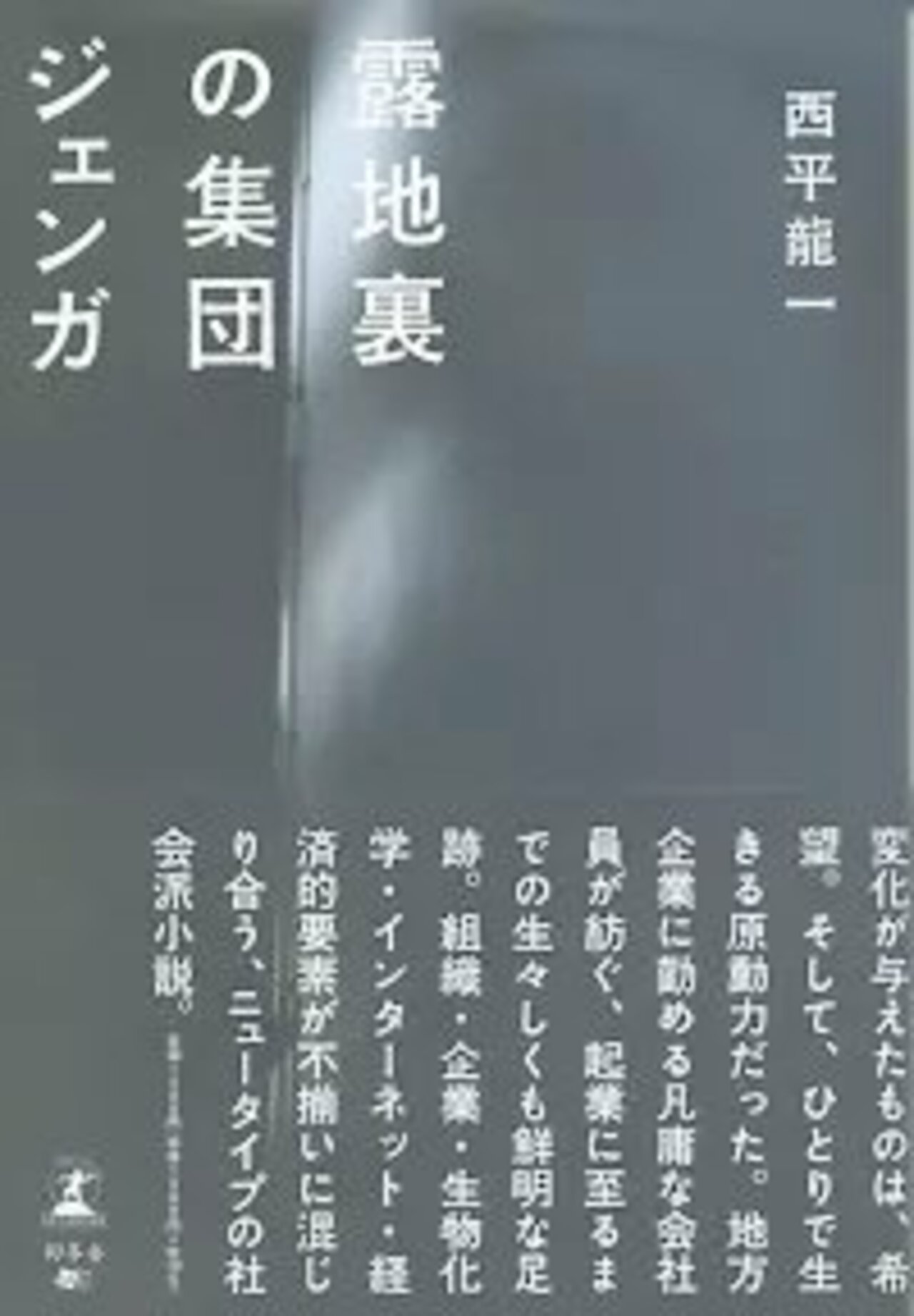第一章 洞穴の燈火
川島は、東証一部上場のコンサルティング企業の出身で、その名は経済ニュースをまったく集めない僕なんかでも知っていた。
どうやらその企業が得意としていたのは、新しい業態そのものを、0から創造することにあった。
創造した業態は、フランチャイズの形式で拡大した。ビジネスモデルの核となるのは顧客の業績向上で、対価としては加盟金。そして著作権と特許権の使用料だった。
外部の企業や社内の競争に、川島は尽く勝利した。そして獲得した地位に執着はしなかった。数少ない仲間とともに、とある企業の事業部門を買収した。
川島は二十代最後の年齢で、経営者へと転身した。創業当時は赤字が続くので、しばらく辛酸を嘗めることもあったが、末に組織は拡大した。
つまり川島は、所謂エリートであると。そう世間では分類される人材だった。
そういうことを、冬木は滔々と僕に伝えた。
「しかしね。敏腕な人っていうんやったら、そら例えば上松部長とかで十分でしょう」
ロックグラスの中を覗くと、茶色く濁った液体が小さく揺れている。
冬木は急に咳き込んで、丸くなった目を上げた。
「上松さん? 本当おまえはいつまで経っても節穴だな」
あっ。と言って口を掌で押さえた。なかったことに。と、冬木が言って、知ってますよ、そら見てたらわかりますからね。と、僕はほくそ笑んだ。
上松は、十把一絡げに管理したがる人間の典型だった。だから従うだけの簡単な扱いでそれでよかった。
問題なのは、まだ見ぬ川島という人間だ。僕は一般社員の枠を出て、ようやく課長の職位を手に入れた。それはほんの僅かだが、権限の拡大と所得の増加を意味していた。
川島のような人間は、大義のためなら初期化することを厭わないのだろうと。そういう畏怖を感じさせた。
ただ僕は、同時に疑い深かった。それは冬木がずっと微笑みながら、川島を語ったことだった。
川島は就任してからずっと、僕に大局的な話をした。
帰路と通う食堂が同じなのは多分都合がよかった。川島はよくいえば繊細で、悪くいえば神経質だった。
上松配下の営業部門と、コミュニケーションによる不都合を予測していたのだろう。禅問答のような会話は、最初は酷く、僕を憂鬱にさせることが多かった。
なぜなら僕は、目上の者には鸚鵡のように受けた言葉を繰り返し、何かの意見には肯定的に答えることを慣習にしていたからだった。
僕の警戒心が解けたのは、川島がねちっこくて執念深いからではなかった。女にフラれたときには、下手な歌を惜しげもなく熱唱して笑わせられたし、気を失いかける程の高熱になったときには、炊事の世話までみてくれた。
そして何も僕に求めはしなかった。
次第に僕は、眼を見て話すようになった。川島は相変わらず大局を語り続けた。しかし僕は、憂鬱にはならなかった。眼には小さな燈火が浮かぶように映っていて、微温的な僕の心には、弾いた弦の顫動が駆け巡っているようだった。
「ニシさん。ここだけの話ですよ。コミュニケーションには段階がありますからね。いいですか。このままだとね、我社の利益は半分。従業員も半分になるでしょう」
ある日の帰路で、川島は僕にそう言った。
とても眼が澄んでいたので、単なる危機感を触発するものでなく真意なのだと感じた。
それはいつの話ですか? そう尋ねると、三年後にはそうなるかと。と、川島は答えた。
「どうすればいいのでしょうか?」
自転車を公園に停めた。緑々しい街路樹の枝の根本には、猫が背中を丸めて怯えている。梢も猫も、小刻みに震えている。
「戦略はもちろんありますよ。役員である私の。それは大切な仕事なのですから」
川島は微笑みながらそう言った。
そして小さなナイロン袋から、そっと缶ビールを差し出した。掌には、生温いアルミニウムの感触がしている。
「私は。私はどうすればいいのですか?」
頬が少し強ばって、川島は鋭くなった眼でこちらを見た。