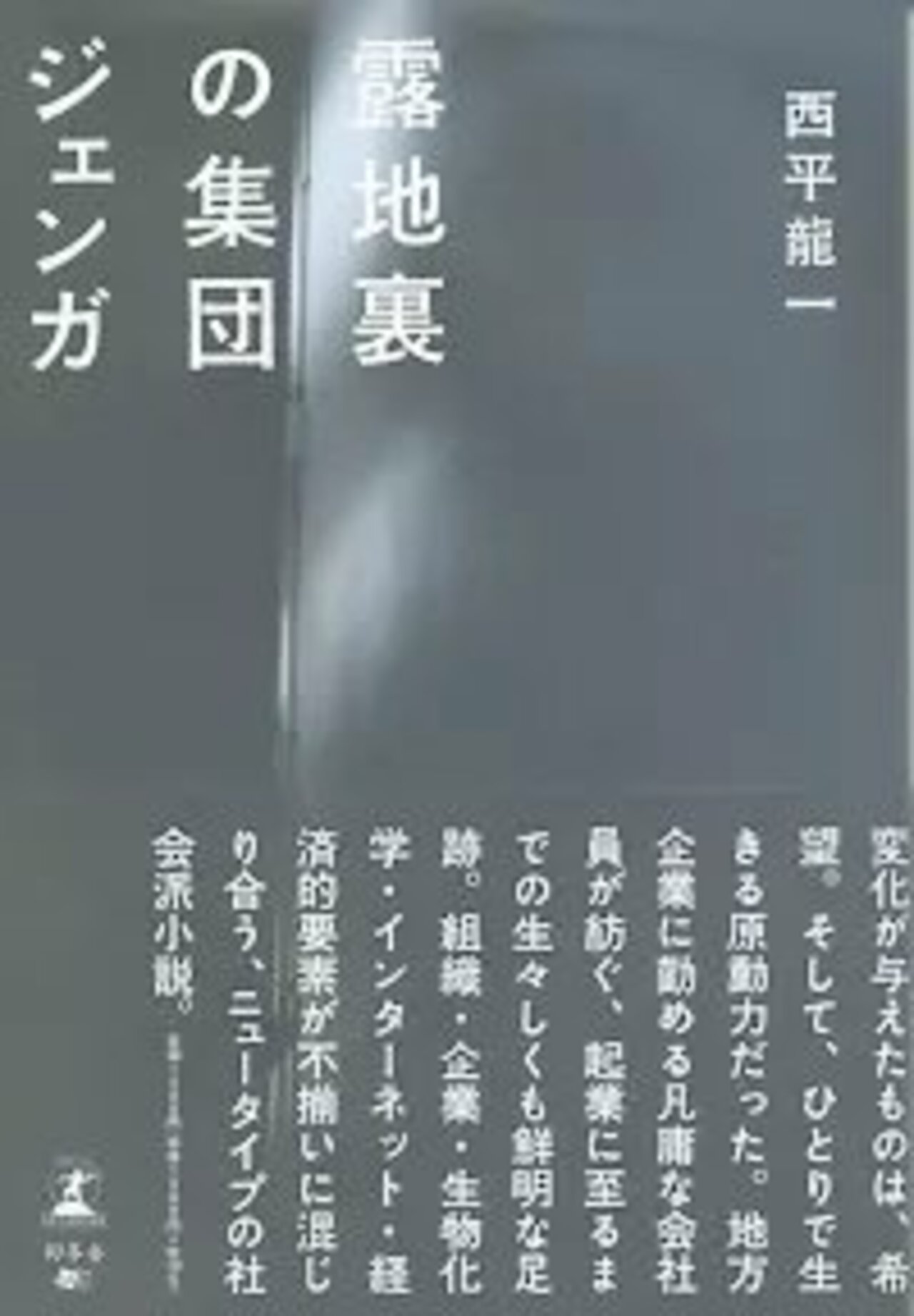以前のように、僕はそれを外すことはしなかった。
川島は又、微笑んだ。
「レベルアップしかないでしょう。逃げないことを約束するなら、遠慮なく鍛えますよ」
僕は勢いよく頷いた。
プルタブを引くと、泡がシューッとあふれ出して、慌てて蛸のように口をつけた。川島は両手を叩いて哄笑している。
街路樹を見上げると、いつの間にか猫は消えている。前照灯は、いつもよりはゆっくりと、帰路につくまで僕の影を静かに運んだ。
僕は欠陥のある建造物のようで、それは地盤が脆弱だったからだ。川島から課された鍛錬は、妥協がまったく存在しなかった。
「ただのセールスマンですね」
これが川島の僕に対する口癖だった。
川島は、営業部門の僕に対して話術や心理学の発達を求めなかった。求めた技術は、例えば調査だったりした。調査は網羅するだけではなく、速度や精度のレベルアップを求めた。
そして前提となる課題や仮説の設定にまで、口酸っぱく指導した。根拠になるデータの、信頼性まで確認した。又、日頃使い慣れた表計算ソフトの操作方法にもうるさかった。
「ニシさんの作成する資料はね。人間の認知システムに従ってないのです」
つまりね。とてもわかりにくいのですよ。と、これも口癖だった。それは例えば時間は左から右に流れることだとか、例えば論理は上から下に流れることだとか、細かな修正をパッと見ては頻繁に命じた。
フォントや配色など、これも又、間違いを見逃さずに、都度修正を命じた。
僕は大した業務の量にもかかわらず、大変な時間を使うことも多かった。方々からは馬鹿馬鹿しいといわれたし、同情されるような振る舞いをうけることも多かった。しかし川島は、これを辞めることはなかったし、程度を僕に相談することも一切なかった。
唯一つ、僕よりあとに帰ることだけは、必ず怠ることをしなかった。