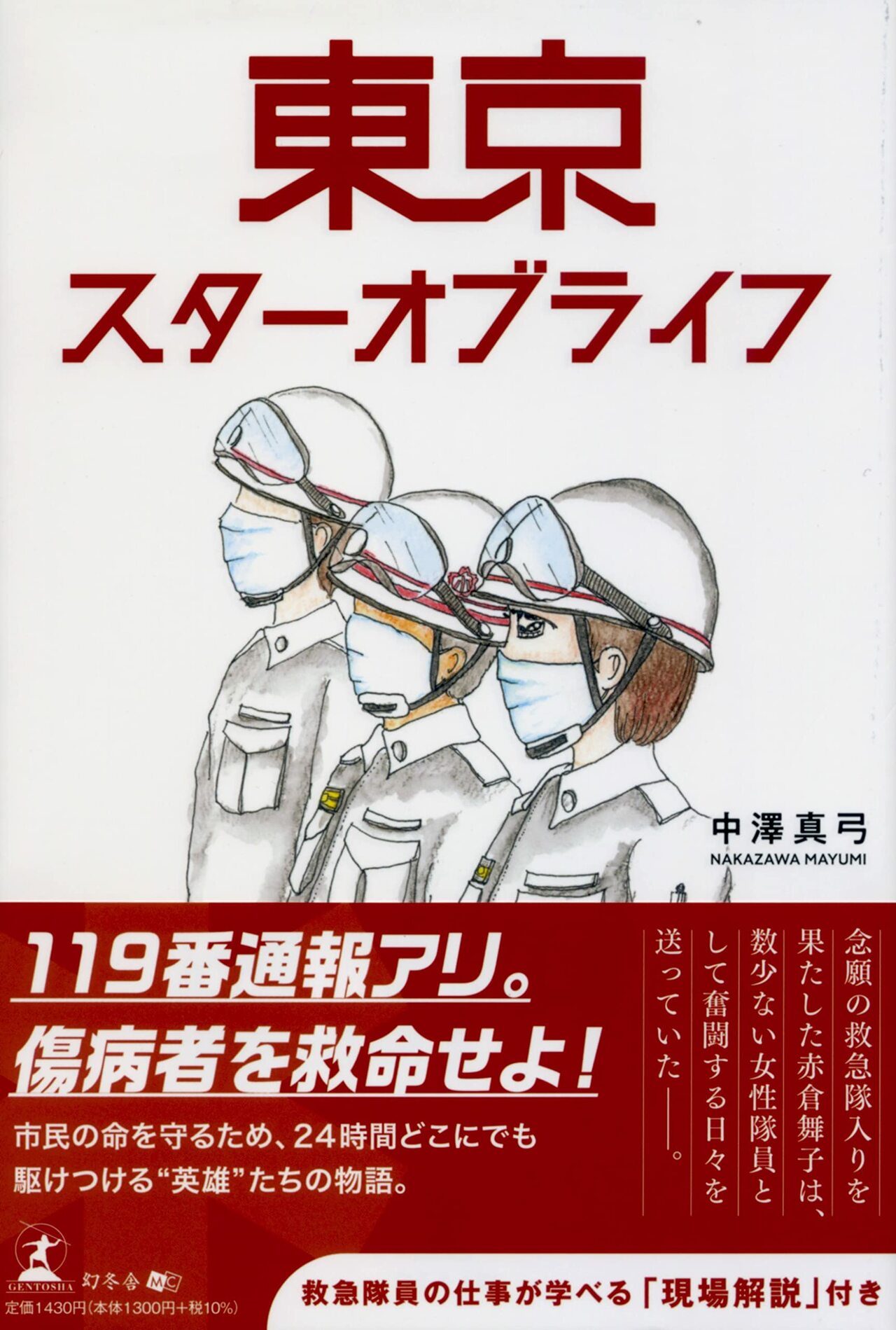「終わりましたね」
「お疲れさまでした」
「ご苦労さま」
審査を受け終わった後、菅平、舞子、水上の三人は汗だくになり、消防署の裏庭で缶ジュースを飲みながら休憩を取っていた。
「しかし、水上さんって女性にだけでなく、子供からもモテるんですね」
汗を拭きつつ炭酸飲料を飲みながら、舞子は水上に話題を振った。
三人が飲んでいる缶ジュースは、伊吹からの差し入れだった。
「カッコいい救急隊のお兄さんに渡してください」と、受付に届けられていたものだった。もちろん買ったのは母親の雫であろう。
「あの親子、けっこう頻繁に消防署に来ているみたいですね。もしかして、お母さんの方も、子供を使って水上さんに近づこうとしていたりして」
「……今度、ウチの署の救命講習会に参加するって言ってた」
「やっぱり! 結構、本気かもしれないですね」
「さて、そろそろ事務室に戻るか。審査会が終わっても、今日は当番勤務だから、これから仕事がいっぱいあるかと思うと気が抜けないけどね」
誰より厳しい訓練をしてきた菅平が言ったとたんに、『ピー、ピー、ピー』と指令が流れてきた。
『六十五歳男性、胸痛のもよう』