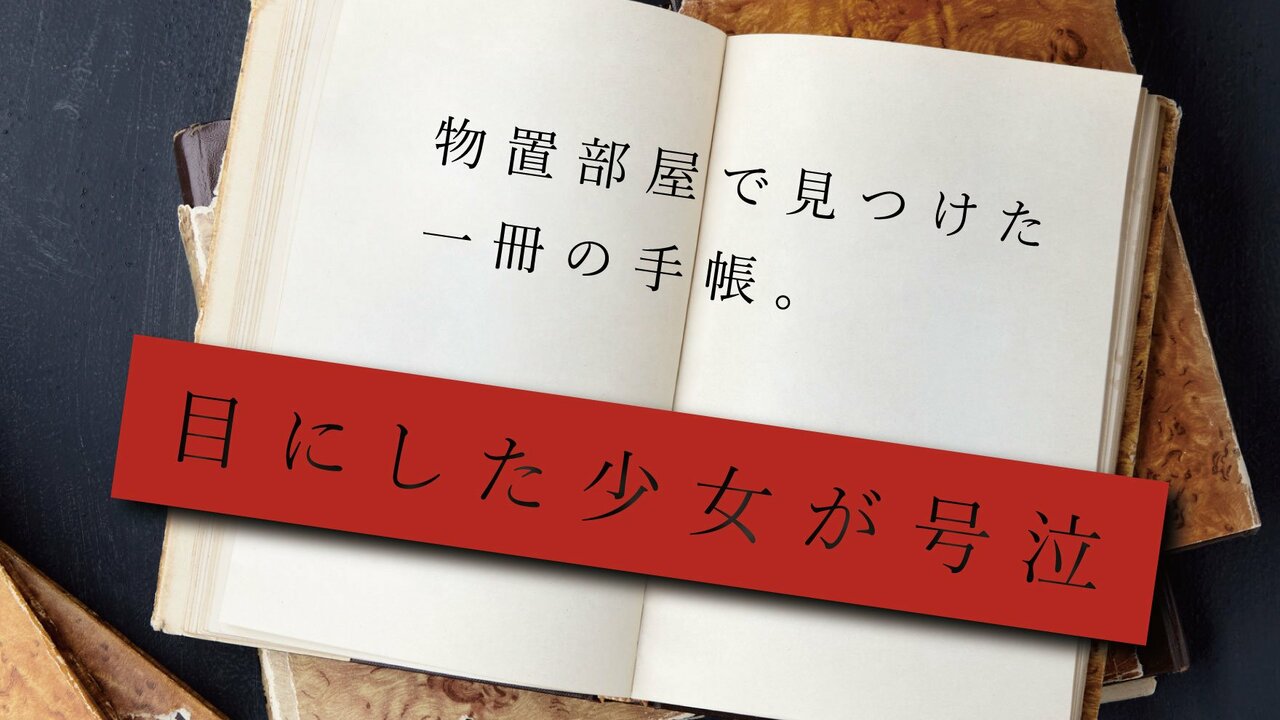「ある夜、街灯も月明かりもない真っ暗な山道を、一台のタクシーが走っとったそうな。急に、運転手さんが車のスピードを緩めよった。前方の暗闇に、人影のような物が見えたけんらしい。まさか人なわけない思うて目を凝らすと、黒髪を結った小さな女の子が、手を挙げてこちらを見つめとった」
「キャ~~!」
「ワァ~~!」
クライマックスに辿り着く前から、二人で金切り声を上げて、ブランケットの中でジタバタしたものだ。
おばあちゃんはその反応を見て、してやったりという顔をしながらケラケラと笑っていた。 更に、幼少期から青年期までを戦争と共に過ごしたおばあちゃんは、よく戦時中の話もしてくれた。
「あの時分は、食べるものがのうてねぇ。うちは農業しよったけん、なんとか芋を食べて食を繋ぎよったんよ。そやけど、海端の人らはねぇ、そりゃあ可哀想やったんよ。食べるもんを分けて欲しい言うて、遥々この山の奥までやって来たんやけど、こっちも精一杯やったけん、なんにもあげることができなんでねぇ」
「こっちのほうにまで、B-29がやってくる言うけんねぇ、一軒ずつ防空壕を掘ったんよ。灯がついとったら爆弾を落とされるけん、灯を消して真っ暗にして夜を過ごしよってなぁ。ほんで、一たび、サイレンが鳴ったら、大急ぎでその穴に逃げ込みよったんよ。それはそれは、恐ろしかったことよ……」
「この家はなぁ、終戦の翌年に、うちの人らぁが、大工を何人か雇うて建てたんやけど、あの時分にゃあ、兵隊さんにとられて硝子が手に入らんかったけん、障子硝子や窓硝子は長いこと、はめれんづくやったんよ」
そして何より、おばあちゃんは孫のことをいつも応援してくれていた。陸上や水泳などの大会がある度に、おばあちゃんは五段の重箱いっぱいに、めのりやおいなりさんなどのお祝い御膳を作って、応援に駆けつけてくれた。
昼休みに、その重箱を家族皆で囲んで食べるのが楽しみだった。私は走ることや泳ぐことが得意で、よく賞状や盾を持ち帰った。
小さな町の小さな大会の小さな盾だったのだが、おばあちゃんは、つぶらな瞳をしばしばさせて「がんばったねぇ」と褒めてくれた。
私はニッコリ笑って、「おばあちゃんの応援のおかげ」と伝えた。おばあちゃんは、これらの盾を大事に玄関の下駄箱の上に並べてくれた。
「この頃が一番楽しかったわなぁ」とおばあちゃんから聞いたのは、この二十年後のことだ。