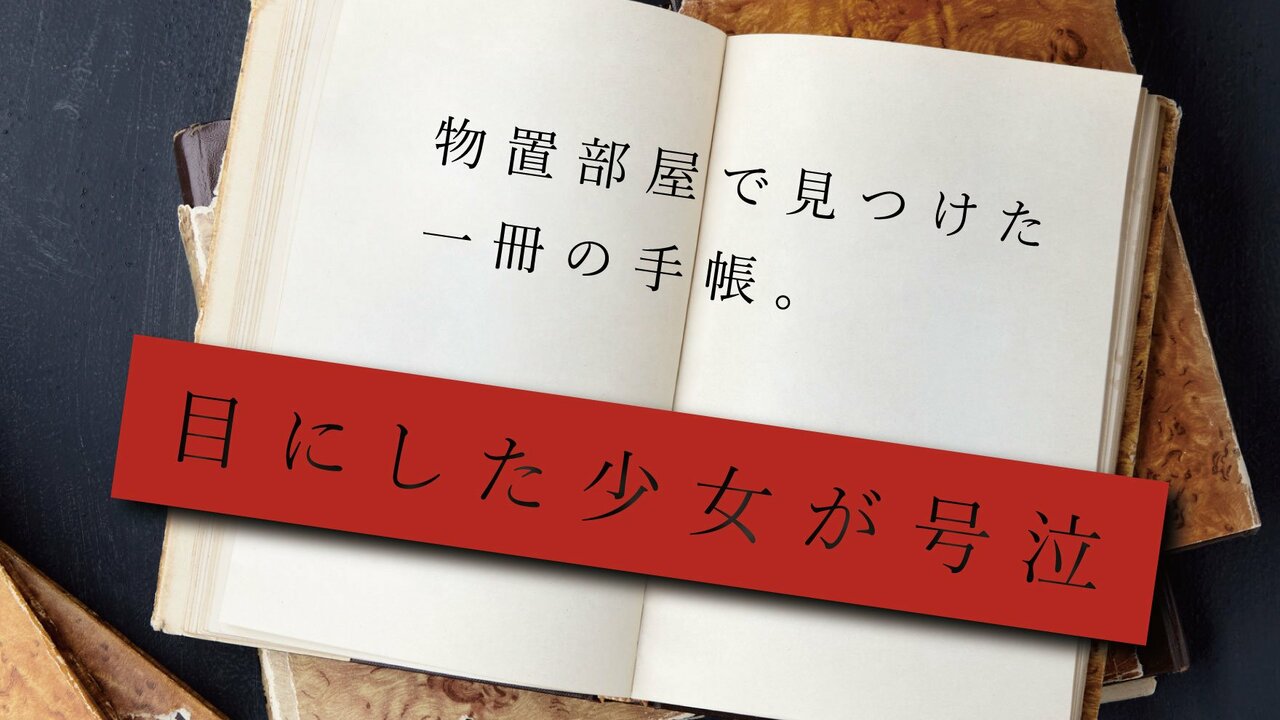第一章 大自然の中で
一
私が生まれ育ったのは、四国の西南端の人口一万人の小さな町だった。
ショッピングセンターもファミレスもボウリング場もカラオケ店もない、高速道路も通っていなければ、電車も走っていない、好奇心の塊の幼少期を過ごすには、全くもって誘惑から無縁の町だった。その代わり、常に私を取り囲んでいたもの――それは、一語で言い表すと、「大自然」だった。
国土の大部分を占める山地には、緑豊かな森林と特産品のみかん畑が広がり、その西方には水産資源豊富な海が輝いていた。私の家は、この町の最高峰、通称やまびこ山を南側から仰ぎ見る、東西を山に囲まれた谷間に位置した。想像に難くないのだが、そこは町の中心地からほど遠い、深い深い山の奥だった。
ここで、私のうちは、みかん農家をしていた。
家の裏山には、文旦の段々畑が空に登る階段のように切り開かれ、家の正面の小坂を下ったところには、ジューシーフルーツの段々畑が谷間を下る清流へと続いていた。みかんはいつも私のすぐ側にあり、生活に溶け込んでいた。家の周りでも、小学校に続く山道でも、みかん畑が見渡せて、果樹から落ちた実がそこら中に散在していた。
ここを舞台に、地球が太陽の周りを回るにつれて、刻々と装いを変える四季折々の大自然が展開された。春、山の百木に芽吹いた新緑が、何層もの若緑の輝きで、天に初々しく挨拶をする。畑の畦道では、筍たちが背比べをし、万花の中を蝶や天道虫たちが南風と追いかけっこをする。
夏、薫風に揺られる深緑の青葉が、堂々と天に向かって胸を張る。昼間には蝉たちの耳をつんざく鳴き声が、谷川のせせらぎを掻き消し、夜にはその川の辺りの暗闇を蛍たちが朧げに照らす。秋、山々の広葉樹林が個性豊かな色彩で人々の目を釘付けにする。路端の落ち葉や団栗、木の枝が、靴の下でシャカシャカと愉快な音をたて、山吹色の稲穂が涼風に吹かれて収穫の時を待つ。
冬、霜が大地を濡らし、やまびこ山から吹き下ろす北風が防風林を四方八方に激しく揺さぶる。果樹が千枝に所狭しと実をならし、それらの実が黄色、橙色、黄金色、それぞれの色で輝きを放つ。
私はこの大自然のど真ん中で、妹と弟と共に成長していった。高価なおもちゃを買ってもらったり、遠くのどこか楽しいところに旅行に行ったりした記憶はなく、みかん山や畑や倉庫が何よりの遊び場だった。しかし、幼き私は、この環境が素晴らしいとか、恵まれていると、認識することはなかった。
私が幼少期に、「雄大」や「手つかず」といった表現を知っていたならば、当たり前で何も特別に感じなかったこの大自然を、もっと慈しむことができたのかもしれない。
私はこの場所で、活発、且つ、少し困るくらいのお調子者に育った。例えば、小学校の国語の授業で、物語を読解している先生が、
「なんでA子はこの街に来たのでしょうか?」
という質問を投げかけると、手も挙げずに、
「バス!」と発言するような子だった。