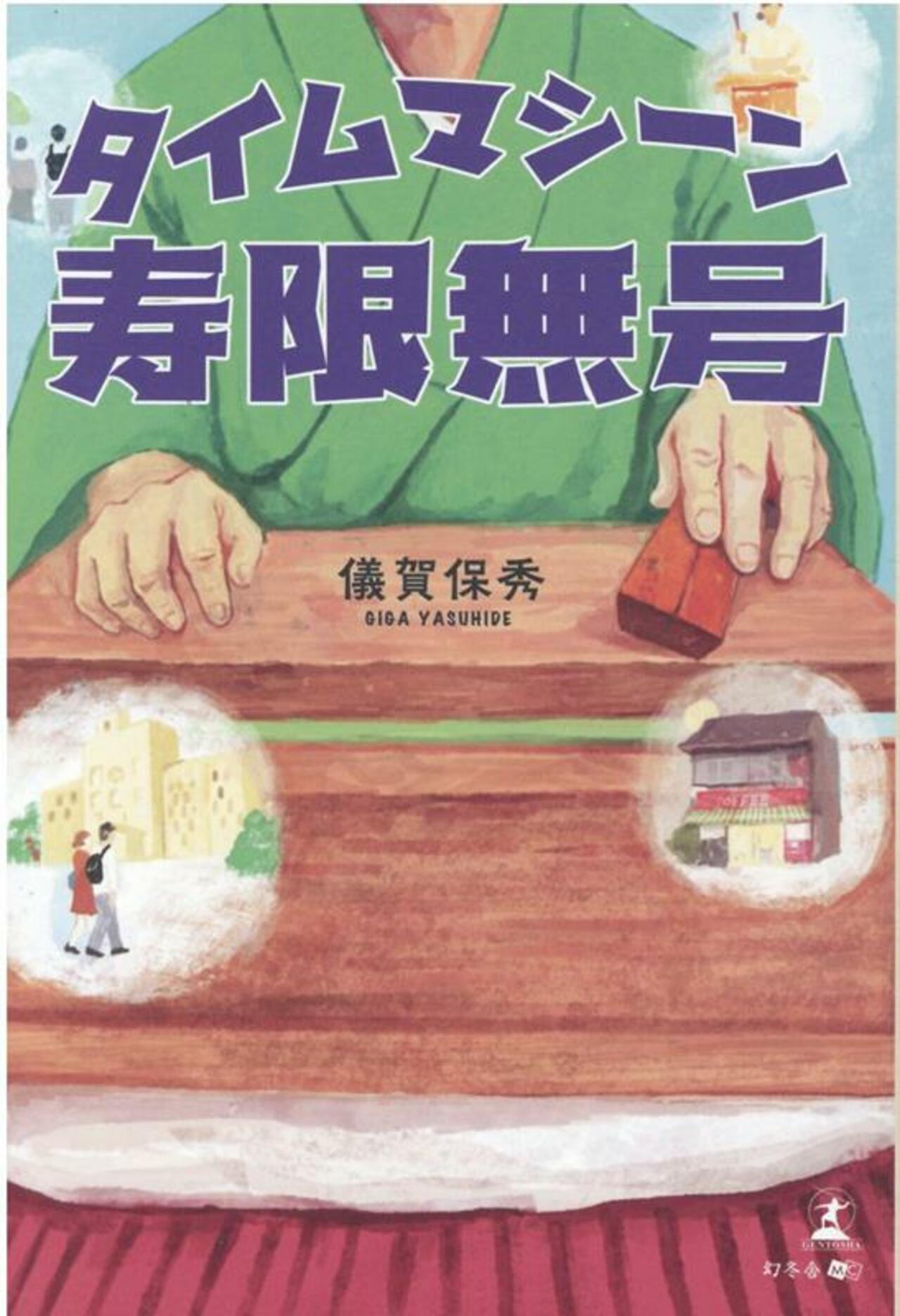「あ、先生!」
「じいちゃんや!」
「ご無沙汰してます!」
参加者から驚きの声が上がる。じいちゃん先生は言葉を発せず、久し振りに再会した教え子たちを見回して満足そうな笑顔を振りまく。
「先生、今はどうされてるんですか?」
一人の男性が質問した。
「どうしてるって、今は一九八九年やねんから、先生をしてはるんや。ややこしいことを聞いたらアカンやないの」
女性の参加者が注意する。
「そうやったな。すまんすまん」
素直に謝る。じいちゃん先生は二十一世紀に突入した後、しばらくして七十五歳で亡くなった。
「いやあ、こうして先生の姿を見てるだけで、何か嬉しい」
「俺、ちょっと泣けてきた」
「鬼の目にも涙か」
「ほっとけ」
生徒だった参加者とじいちゃん先生は直接会話することなく終わる。
「じゃあ、皆、元気でな」
じいちゃん先生は、その言葉だけを発して去っていった。その後も先生の思い出話は尽きない。卒業三十年記念の同窓会は大いに盛り上がった。予定の時間が来たところで理之介が参加者に声をかける。
「皆さん、では、そろそろお時間でございます!」
「もう終わり?」
「早かったなあ」
「もっといたかったのに」
参加者の間には、ここにずっと滞在していたいという思いが充満していた。
「まあ、名残惜しいでしょうが、一九八九年を後にして、二〇一九年、令和の時代に戻りたいと思います。ご準備ください」
理之介が会の終了を告げる。参加者たちは後ろ髪を引かれながらも帰る準備をはじめる。