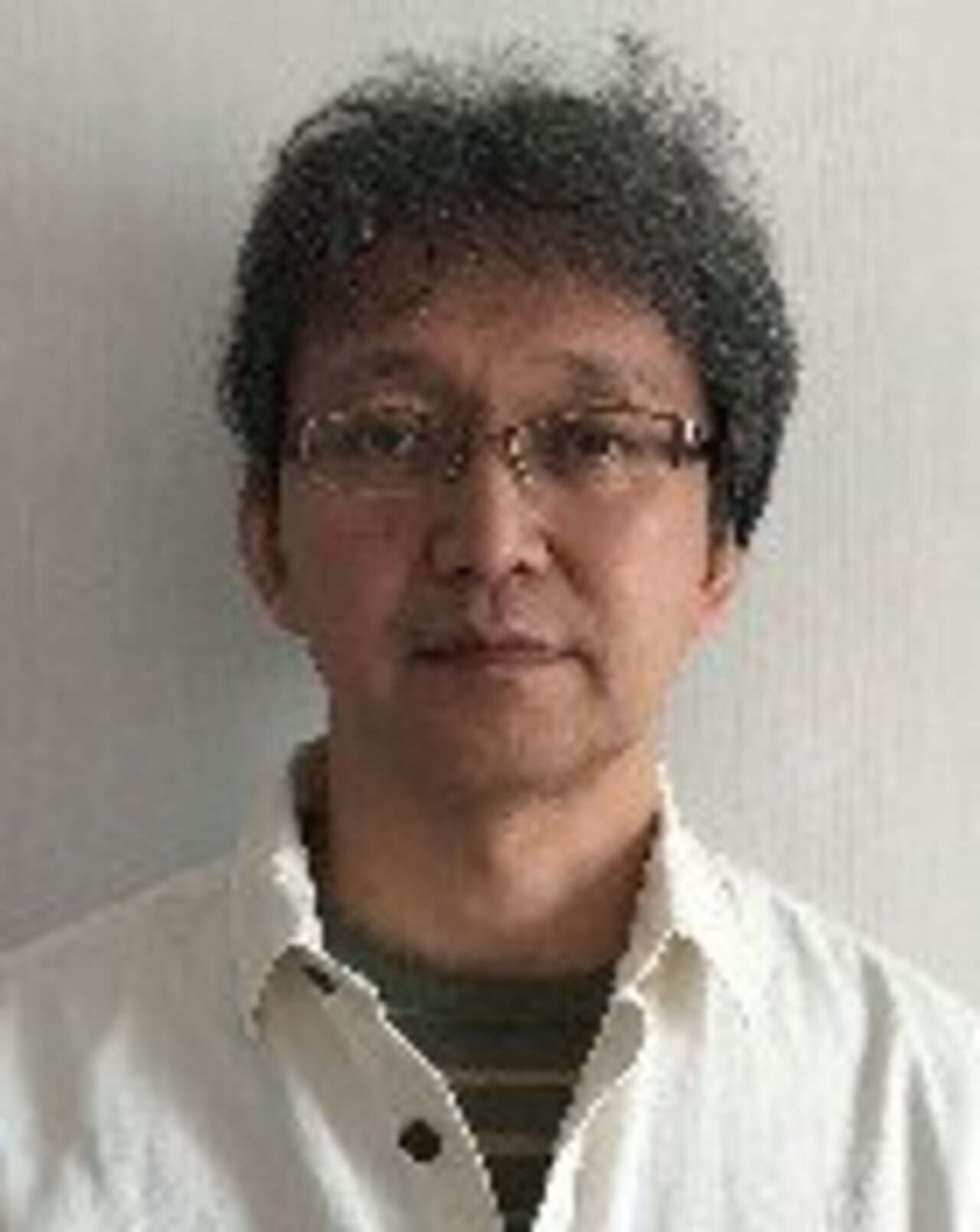【前回の記事を読む】【小説】治療に苦しみ、絶望を味わおうとも「妻は未来を見据えていた」…
ヤマハのキーボード
ハプニングはその朝に起きた。遥が、家の階段で足を踏み外したのだ。
同級生で親友の静那ちゃんから「北海道のおばあちゃんが送ってくれたトウモロコシを、今から届けるよ」とメールが届き、舞い上がって二階から跳んで下りて来るところだった。
何とか体勢を立て直し転倒はしなかったが、右足の先を強打した。腫れが酷いように見える。廉は取り急ぎ、子ども同士が仲が良く、ご近所付き合いが長い中本幸代さんに電話をした。
こういったケースに的確にアドバイスをくれる頼れるお母さんだった。
日曜日だったので、中本さんはすぐに休日当番医を調べ、自分の車で湘南台の整形外科医院まで遥を連れて行ってくれた。右足親指の付け根の骨にV字形のひびが入っていた。全治三週間とのことで、ギプスが装着された。
消毒や添え木の固定し直しなどで何度か通院することになりそうだったところを、中本さんが機転を利かせて自宅に近い整形外科への紹介状を書いてもらうよう段取りしてくれた。そして廉が預けた治療代の不足分を立て替えてくれたうえに、遥と昼食まで共にしてくれた。
廉が出社したあと、今度は姉の真咲が靴の量販店に遥を連れて行き、怪我をしていても履けるサンダルに似た外履きを買ってくれ、遥の従姉の綾も合流して夕食をご馳走になった。お向かいの林さんもこの騒ぎを聞きつけて、遥の足の怪我が治るまで、夕方の「そら」の散歩を買って出てくれた。
温かい救いの手が次から次へとわが家に差し伸べられている。その計り知れないパワーを、会社にいながらも廉は感じていた。そしてこれら朝からの一連の出来事は、真咲から和枝の耳にもちゃんと伝わっていた。