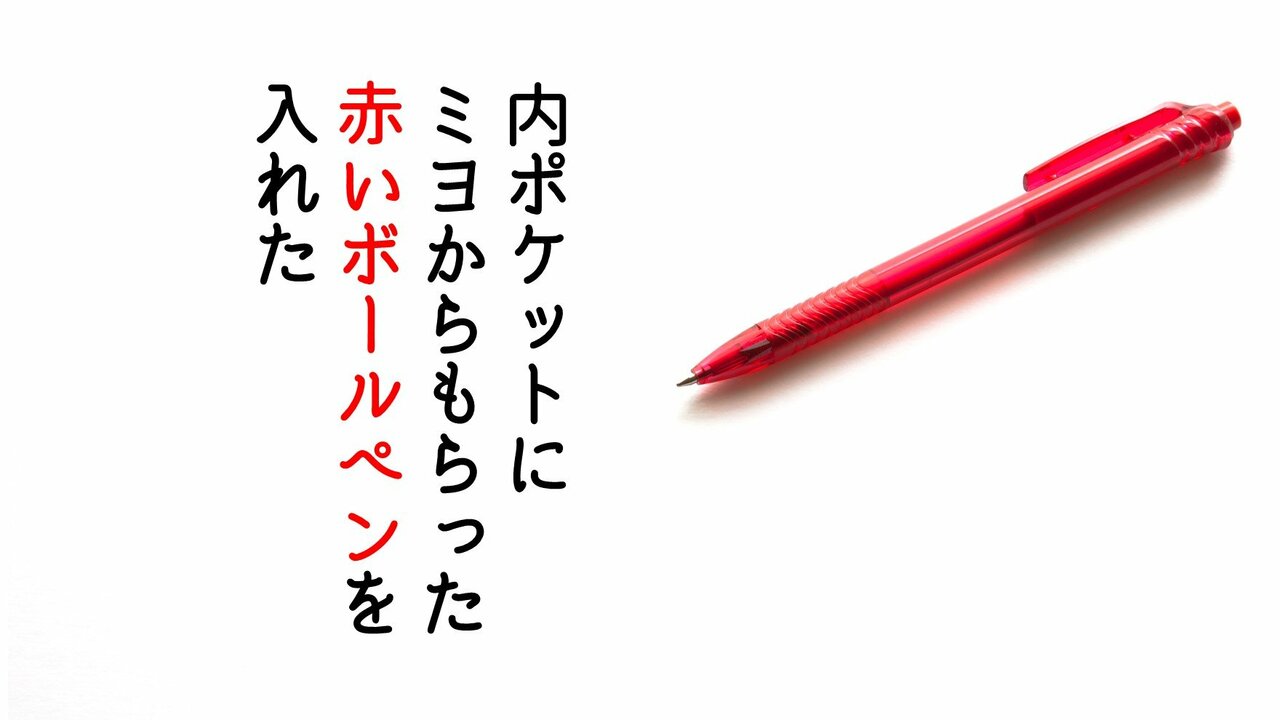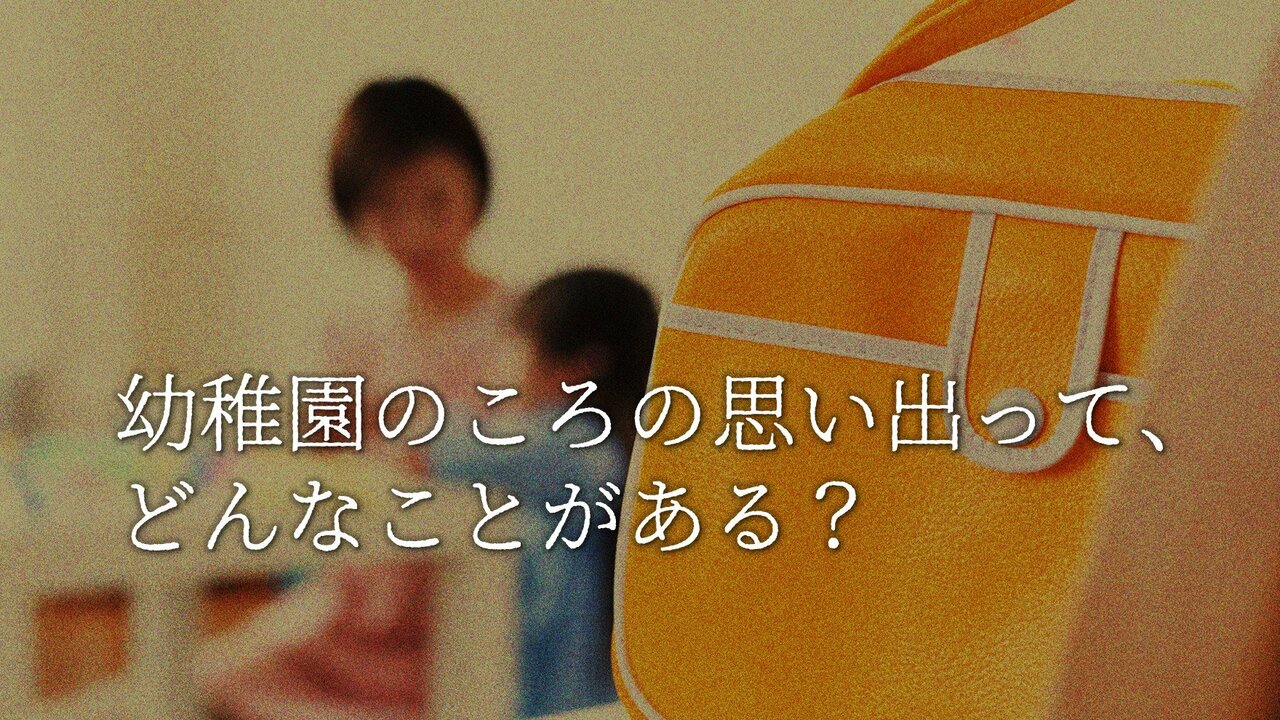第二章 希望
みそぎ学園高校の説明会から二日が経った。塾の帰り道、達也は「またね」というミヨの言葉を何度も繰り返していた。思わず歩む足を止めた。
すぐにわかった。瞳を閉じてはいるが、顔を上げ、胸に両手をあてたミヨが、駅へと向かう夜道で一人佇んでいる。細く白い首筋が月明かりに照らされ、どこか神聖な空間を作っている。「神崎先輩」達也が駆け寄ると、ミヨは目蓋(まぶた)を開いた。
「また……会えたね」
「はい、説明会の日からずっと会いたいと思ってました」
無表情だったミヨの頬が、ほんのり赤くなる。
「勉強の調子はどう?」
「はい、それが、先輩からもらった赤いボールペンを使いはじめてから不思議と正答率が上がってきているんです。もっと勉強して絶対にみそぎ学園に合格します! 入学したら毎日、先輩に会えますから」
「よかった……。そうだ、来月文化祭があるのよ。一般公開する日もあるんだけど」
ミヨの頬は白く戻り、にこりともしない。
「必ず行きます」
「楽しみね。それじゃあ、そろそろ帰りましょう」
改札へ向かう途中、達也は思い切ってミヨを呼び止めた。
「あ、あの、神崎先輩! あの、もしよかったら、その……携帯のアドレスを交換してくれませんか? あ、いや、そのご迷惑なら仕方ないっていうか……その」
「ええ、いいわよ」
達也が乗車してすぐにメールが届いた。ミヨからだ。わくわくしながら開いたメールにはこう記されていた。
『またね』
携帯の向こうの温もりを握りしめ、達也もまた緊張する手で初めてミヨに返信するのだった。
十一月。そろそろ受験校を確定する時期だ。ミヨとは、あれから定期的に連絡をとるようになり、ミヨと会える日の塾帰りが達也の楽しみになっていた。勉強も順調に進み、塾での成績は信じられないほど急上昇している。
志望校について塾と相談すると、次回の外部模試の結果を見て総合的に判断するとのことだった。当初、無謀と思われたみそぎ学園高校合格も、今では夢ではなくなってきている。
明日は、ミヨと約束した、みそぎ学園高校の文化祭だ。どうしても寝つけなくて、達也はベッドを離れた。今晩に限って全く眠気が襲ってこない。むしろ、ますます目が冴えていくようだ。
達也は、ミヨからもらった赤いボールペンを手に机に向かった。あれほど嫌いだった勉強なのに、答え合わせをするたびにやる気がみなぎってくる。今まで、こんなにも時間を忘れ勉強に没頭したことがあっただろうか。
「よし。数学はかなり点が取れるようになってきたぞ」
何度目かの答え合わせを済ませ、一息つく。ミヨと会えることを思うと、自然とにやけてしまう。達也はその後も問題をいくつか解くため、赤いボールペンを手に取るのだった。