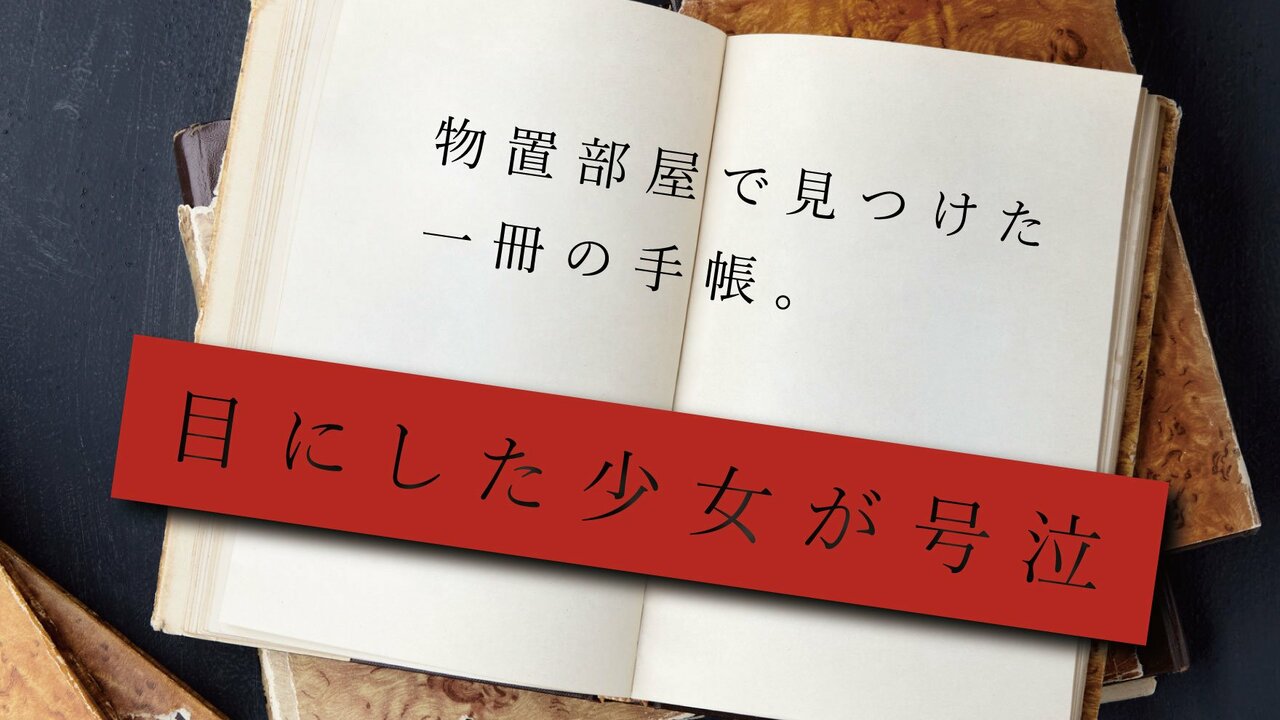「実里や、お父さんが買うてきてくれた大瓶を持ってきてくれんやろか? 入口の押入れの上の段の一番右側に入れとるけん。重いけん気をつけて」
「うん、分かった」
私は入口に置いてあるおばあちゃんの按摩器に登って、押し入れに手を伸ばした。ちょうど私の指が入るくらいの隙間が開いていたので、そこに指を掛けて扉をガタガタ言わせて引き開けた。その途端、暗闇からピョーンと小さくてヌルッとしたものが飛び出してきた。
「うわぁ!」
私は驚いて、按摩器からよろけて尻餅をついた。何処からか迷い込んだ、黒光りしている雨蛙だった。
「なんだ、蛙かぁ」
私はその蛙を捕まえて廊下に放ると、気を取り直して再び按摩器に登った。暗がりの中を覗くと、何処かの大都市のシンボルの塔のような大瓶が立っていた。
――重そう。持てるやろか? 私は両手でその瓶を抱えて、せーのっと全身の力を込めて持ち上げた。その途端、私の体はグラっと揺れて、再び按摩器から転げ落ちそうになった。なんと、その瓶は軽かったのだ。中身が忽然と姿を消していた。お父さんが、一日で飲み干していたのだ。
私はそんなお父さんの姿を見て、よくこの状態で畑のみかんが育つなぁ、と真剣に不思議に思っていた。私はそのことを、顔面を活火山のように赤らめて、愉快そうに飲んでいるお父さんに尋ねたことがある。すると、お父さんは口に運ぼうとしたビールの缶をそっと机に置き、妙に真面目な表情で答えた。
「おれは、実里ねえやんらがまだ寝よる朝早くから、山に行って仕事をしよるんやけん」
もし、このことを世紀の大発見と捉えていたならば、ここでお父さんに対する感謝を述べることができただろうが、私は耳にしたことと実感が伴わない時に発せられる「ふうん」という生返事しかできなかった。やっぱり私にとって、お父さんは「朝から晩まで酒を飲む人」のままだった。