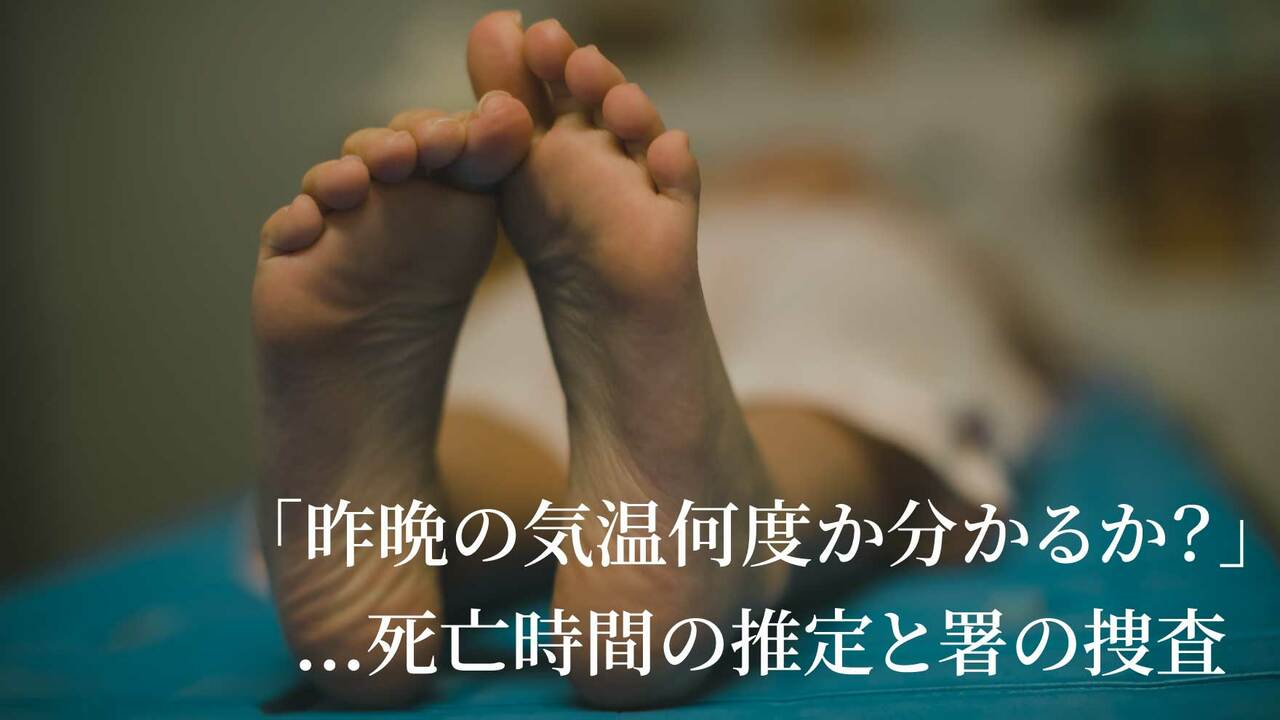第一章 屈折した凶行
「カウント3!……」
コルチを通して耳介に響く指令に、武田は我に返った。コルチとは耳栓タイプの無線受信機である。武田の目の前のドアマンが玄関ドアを開けた瞬間、無意識に身体が突入モードに変わる。事前の指示通り、武田の身体が勝手に動き出す。そして、閃光弾が炸裂し部屋中に高音響が鳴り響く中、玄関を入ってすぐ左側の和室にいる被害者へ突進し身柄を確保した。3メートル程離れたところで呆然と立ち尽くす犯人は、武田の後続隊員が取り押さえていた。
「想定終了……」
全隊員への無線が入り、立てこもりの訓練は終了した。5月に入ったばかりとはいえ、昼前の気温はゆうに20度を超え、刃物用の対刃防護衣を着た隊員は全身汗まみれであった。場所は、福岡県の西部地区の糸島半島、山の形が似ているところから糸島富士といわれている可也山の麓である。廃屋となっている旧志摩町の町営住宅で、捜査一課特殊犯係(SIT)の訓練が行われていた。
昨夜遅くまで降り続いていた雨で、あたりはむっとするような湿気に包まれており、山からの吹きおろしの微風くらいでは隊員たちの汗を止めることはできなかった。防護衣は銃器対応の場合は重いだけで、それは訓練で慣れるものだ。しかし、対刃防護衣は、全身を通気性に著しく欠ける耐刃繊維で包み込んでいることから、熱の発散がほとんどなく尋常ではない暑さとなる。真夏なら、頑強な隊員さえ1時間も着ていたら脱水症状になるくらいだ。
特殊犯班長の武田学は44歳、まだまだ若手との訓練で引けを取ることはない、と思っている。身長は170センチ程で一見細身だが、いわゆる細マッチョである。その武田が、布製の目出し帽であるバラクラヴァを剥ぎ取り、コルチを外して汗を拭いていた。コルチは大豆ぐらいの大きさで、訓練中に落下する心配はない。
「班長、また何か違うこと考えてたでしょう?」
武田の後続隊員であった巡査部長の木村が耳元でささやいた。さすがにSAT出身の木村の眼は誤魔化せなかった。
「すまん、0.5秒くらいか?」
「いや、今日は0.3くらい」
「すまん、ちょっと考えごとを……」
木村は、突入の際の武田の反応の遅れを指摘しているのだ。しかし、決して責めてはおらず、心配そうな眼を向けていた。
「いいんです、誰にも言いません、ってか誰も気づいてないんで。ただ、またいつものことなら、そろそろ腹決めてください、みんな真剣なんだから」
「いやぁ、そうだな、分かってるよ、申し訳ない」