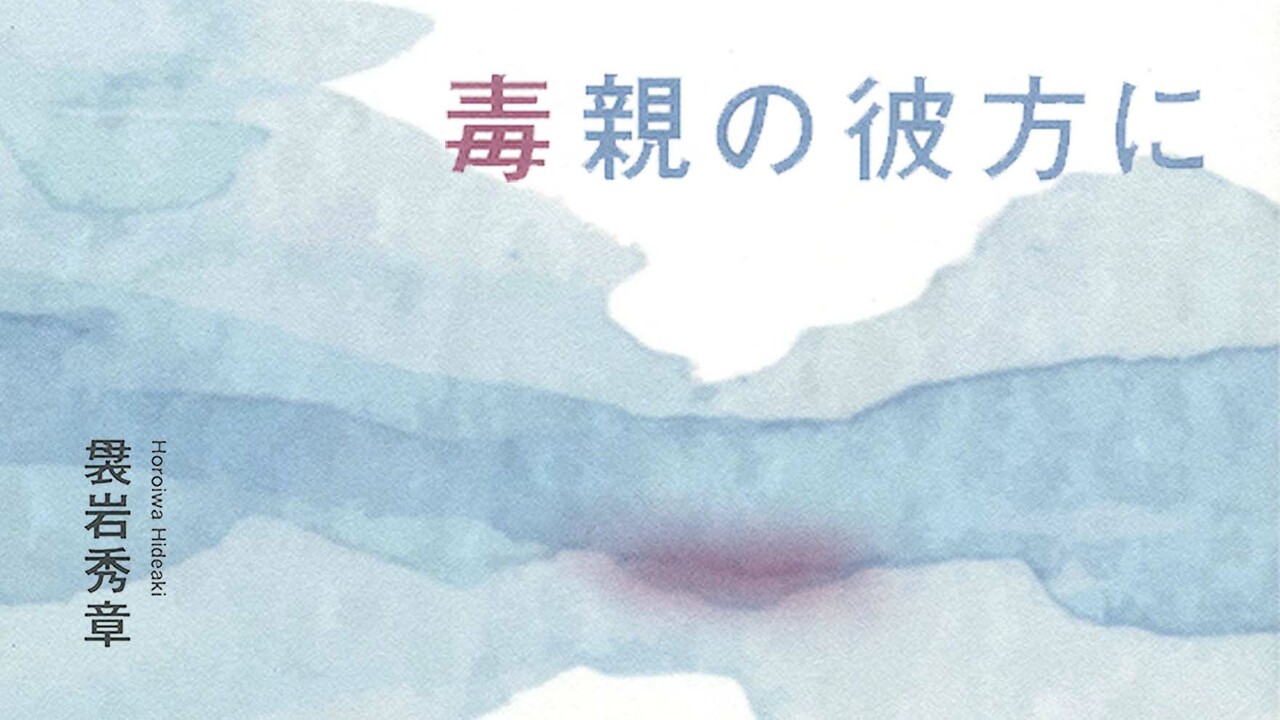【前回の記事を読む】「妹は卑怯だとさえ思った」母親からの壮絶な暴力に耐え続けた少女の歪な認知
カウンセリングに至るまでの道のり
この女性の気持ちの中核は、いまだにはっきりとしない。この女性は私をじっと見ながら、自分のことをおかしいんだと表情も変えずに言う。つらい気持ちや怒り、切なさが胸をかすめるが、それを口にしてよいものか戸惑う。まるで論文コンクールのように朗々と、我慢するのがわたし、怖くて竦むのがわたし、どこかおかしいのがわたし、と主張する。
この人の気持ちは、奈辺にあるのだろうか。朗々と報告するかのような語り口の裏側には、怒りや怖さが、火花のように激しく散っているのではないだろうか。合いの手を入れることも質問することもせず、私はうなずきながら聞いていた。
「そういうことが当たり前の生活の中では、学校に行くことが楽しみでした。でも友だちと放課後に遊ぶとか、一緒に塾に行くということができなかったので、自然とひとりでいることが多く、本を読んだり勉強して、先生にほめられるのが何より嬉しい日々でした」
「日々耐えてやり過ごすことが精いっぱいで、自分の生活や母の態度に疑問を持つ余裕などまったくなかったのですが、中学くらいから母の態度について考えるようになりました。母からの身体的暴力が減っていったことも、考え事をする余裕につながったと思います。体が大きくなって母より背が高くなったので、母も手を出しにくくなったのではないでしょうか。ただ、お小遣いをくれない、夕食抜きにされる、ずっと正座させられるといったことは続きました」
「身体的暴力もなくなったわけではなく、小突いたり頬を張るということはありましたが、母が動くだけでとっさに頭をかばうとか、恐怖で体が動かなくなるといったことは減っていきました。それでもあからさまに逆らうことはせず、ただやり過ごすことを愚鈍に繰り返していました。暴力への恐れというものは消えません。今でもずっとあります。また母の様子を窺うということもやめられません。そうすることは、もうわたしの一部だという気がします」
「どうも母自身、虐待を受けていた気がします。そんなようなことを口にしていました。わたしを同じ目に遭わせたくない、ととれるようなことまで言っていたと思います」
「その中でただひたすら本を読み、自分がいけないからこんな仕打ちに遭うのではない、と少しは思えるようになったのですが、かといってどうしていいかはわからない毎日でした。母がわたしの成績を気にして、成績がいいと機嫌がいいということがだんだんわかり、家内安全のためだと思い、一層勉強して偏差値の高い高校に進学しました」