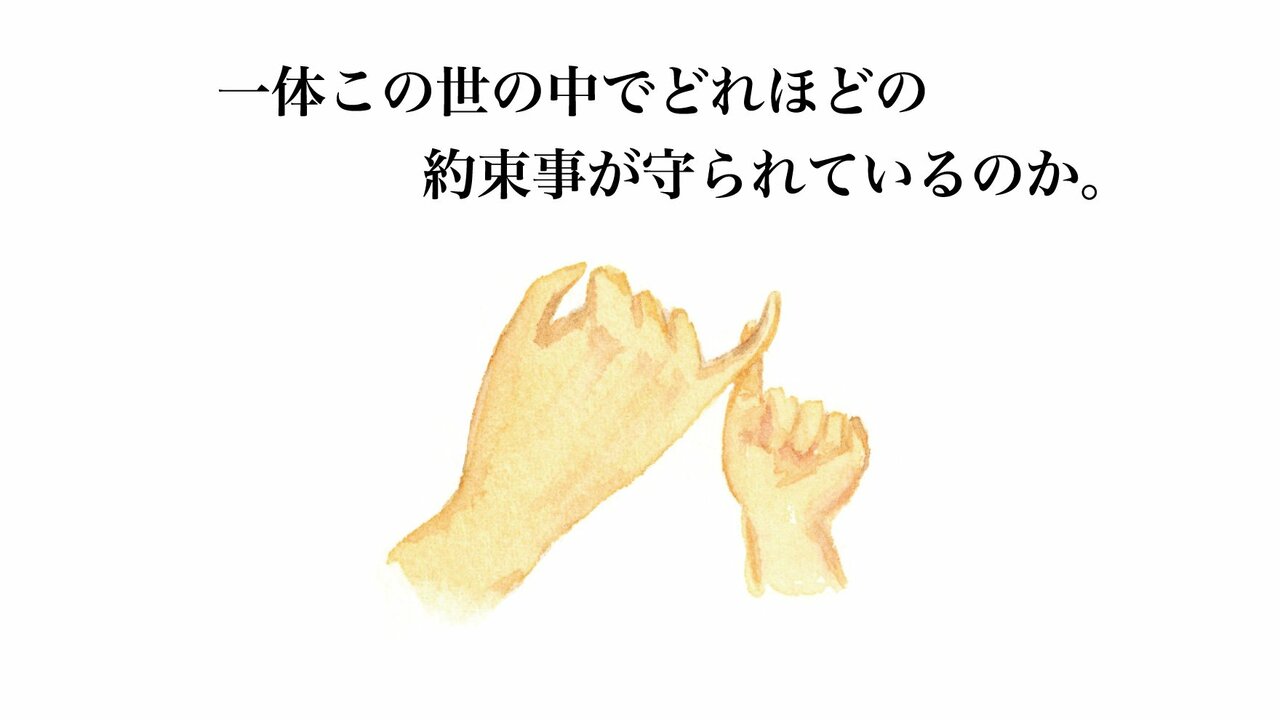真夏の落果新宿駅西口のMY生命ビルの前で高速バスを降りると、布由子は下ろしたての踵の高いスニーカーで舗道を歩き、色とりどりの日日草のような夏服の群れに混じって横断歩道を渡り、青いサンシェードのある百貨店の入り口に飛び込んだ。ちょうど昼時だったので八階のレストラン街のカフェで軽食を取ってから、エスカレーターで階下に降りた。
入院している弟の諭への見舞いの品を選ぶにあたり、生花や果物などは病室に持ち込めないとメールで知らされていたので、三階で国内ブランドのパジャマを買うことにした。それから思いついて、闘病の退屈しのぎに何か本を贈ろうと考え、店内の案内板を見てまた七階に昇った。想像したより小さな書籍売場で、布由子は三十分ほど迷っていた。
五歳年下で四十八歳になる弟の読書の傾向は把握していないが、大人向けかつ軽い文体の小説かエッセイが望ましい。店頭に平積みされた売れ筋の単行本にはミステリーが多く、自分用であれば楽しめるのだが、殺人事件が絡むような物語を病人に読ませたくない。時代小説なら彼は好きかもしれないが、布由子自身があまり読まないので良し悪しがわからない。
ぐるっと売場を見渡すと、ロングセラーになっているエッセイ『大人の流儀』シリーズが目に止まった。三作目のタイトルは『別れる力』、四作目は『許す力』か……タイトルで選ぶなら[許す]ほうがいいかもしれない。パラパラと斜め読みしているうちに布由子は重大な事実を思い出した。
著者は広告業界や芸能界にも由縁のある作家で、元妻のNMさんは端整な女優だったが、もうかなり前、三十年ほど前かと思うが白血病で亡くなったはずだ。そのエピソードに触れていなければいいのだが、と案じながらページを捲っていくと、やはりその一節にぶつかった。たとえそこに触れていない他の作品があったとしても、弟がその有名な事実を思い出したら良くない。布由子は結局本を選ぶことができず、「病院の売店で週刊誌でも買おうか」と考え直して、都営大江戸線の新宿西口駅に向かった。
二〇一五年の六月初め、諭は仕事中に体調の異変を感じて会社近くのクリニックを受診し、紹介された国立病院で[急性骨髄性白血病]と診断され入院した。本人から兄の哲生と布由子宛にその旨のメールが届いたのが数日前のことだ。国際的に有名な俳優や親しい知人の例からしても、現在の医療なら白血病は治癒できると思われたが、一方では死に至る可能性がある病とも認識していたので、病室にいながら死をイメージさせるような本を持ち込みたくなかった。
諭は新宿区内のとある企業の代表取締役社長を務めていた。大学卒業後に某ソフトウェア開発会社に就職し、その後引き抜かれる形で現在所属する会社の親会社に転職した。業務内容を聞いても布由子にはよくわからなかったが、医療機器や医薬品の開発、治験のデータ分析などに関わる企業らしかった。そこで諭はおそらく仕事に邁進した結果認められて、IT部門子会社の平取締役を経て数年前に社長になった。布由子は「諭が社長? 子会社って社員十数人くらいかも」と高を括っていたが、最近その会社のホームページを見て百人以上の社員がいると知って感心した。
一方プライベートでは諭が転職した頃から家庭不和が始まり、その果てに離婚し、彼は今も大学生と高校生になる子ども二人の養育費その他を払い続けている。日頃から「調子はどう?」と聞くとたいてい「まあ、順調だよ」と答える弟は、自ら葛藤や苦労を多く語ることはなかったが、幾つもの無理を重ねてきたことは想像できる。