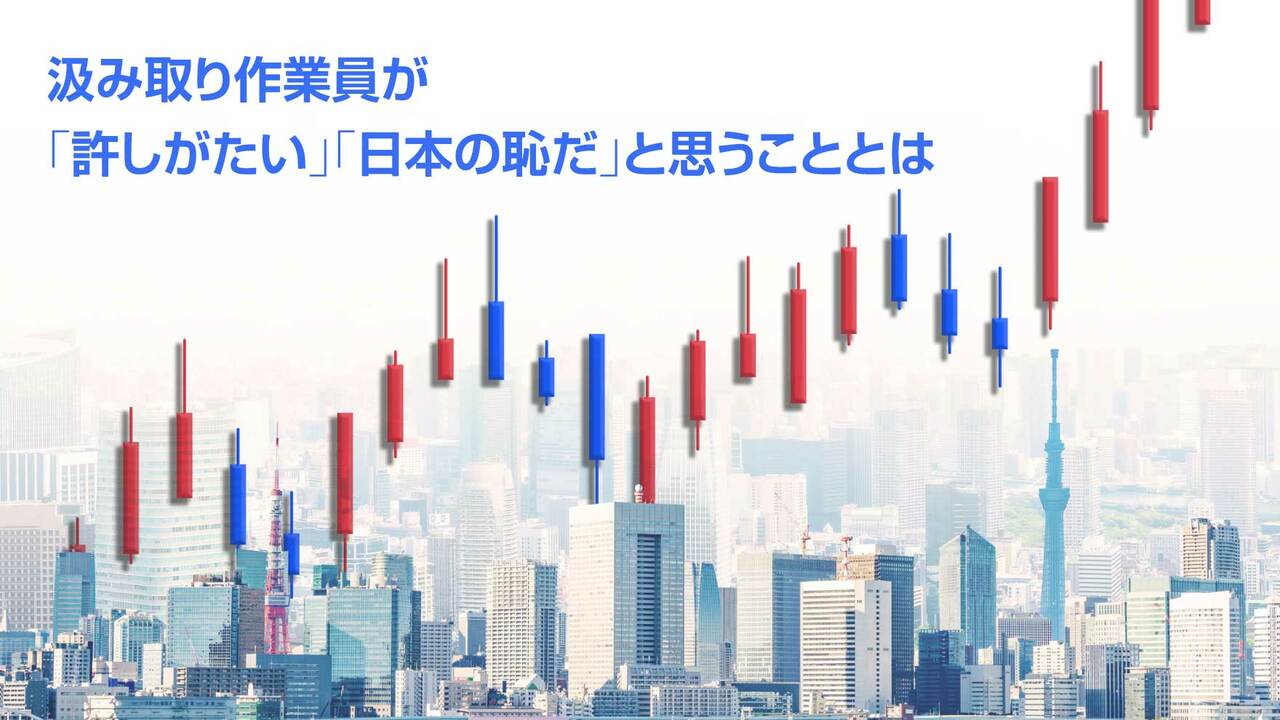会津にいた頃は、学校の帰りにほとんど誰もいない田んぼや畑のあぜ道をフラフラ、トボトボ歩いていると、はるか遠くで草取りをしている隣の村のおばさんが、
「ケンボウ、今帰りが? 気いつけで帰れよ」
と、声をかけてくれたり、
「これ、かじりながら帰れ」
と言って畑のキュウリをもいでくれたり、スイカを鎌で割ってくれたりした。健一は、手も不自由だが、顔の筋肉も麻痺し硬直していて食物を上手にきれいに食べることができない。いつも食事のときには食べ物を口の周りにくっつけたり、胸元にこぼして洋服をベタベタにした。そして、健一の周りは、食べこぼしでひどく汚れた。それは犬や猫が、当たりかまわず餌を食べ散らかすのに似ていた。そのうえ、健一は食べるのも遅いので学校の給食のときなどには、同級生たちからいつもからかわれた。
そんな健一にとって、田んぼや畑でもらうオヤツは、顔じゅうを汚しても、周りにいくらこぼし散らかしても、そして時間がいくらかかっても、誰にも文句を言われることもなく、何も気にする必要がないので、そのときだけは本当に食べ物の味を思う存分味わうことができた。
そして、それは解放と自由というごちそうを味わえる、至福のときでもあった。健一はまだ表面にトゲトゲのあるもぎたてのキュウリを歪んだ口で思い切り「カリカリ、ポリポリ」とかじったり、鎌の跡のある、大きく割られたスイカに顔面全体を突っ込むようにして「ペチョペチョ、ブチャブチャ」両手も顔面も「ベッタベタ、ベッチャベチャ」にしながら食べた。
そして、冷たく透き通った湧き水の流れる用水路で手と顔を洗って、祖父が毎日持たせてくれる水玉模様の手ぬぐいで、顔を拭いて何もなかったかのように、まっ青の空のもと家に帰っていった。また、体力がない健一が、疲れてしまって道端にしゃがみ込んでいると、
「ほら、ケンボウ、乗ってけ」
と言って、近所のおじさんが当時「テーラー」と呼ばれていた、小型の耕運機にリヤカーと座席の付いた乗り物に乗せて、家まで送ってくれた。
会津の田舎とは違って都心の町では、人が洪水のように流れている。フラフラと奇妙でアンバランスな格好で歩く健一は、その激流の中を人にぶつからないように、気を使って緊張して歩く。しかし周りの人たちは、そこに健一の存在がまったくないかのように、「スルリ、スルリ」と、通りすぎていく。
「人の心の密接さと人口密度は、関係がないどころか、反比例してしまうのかも」
健一はそう考えたりした。