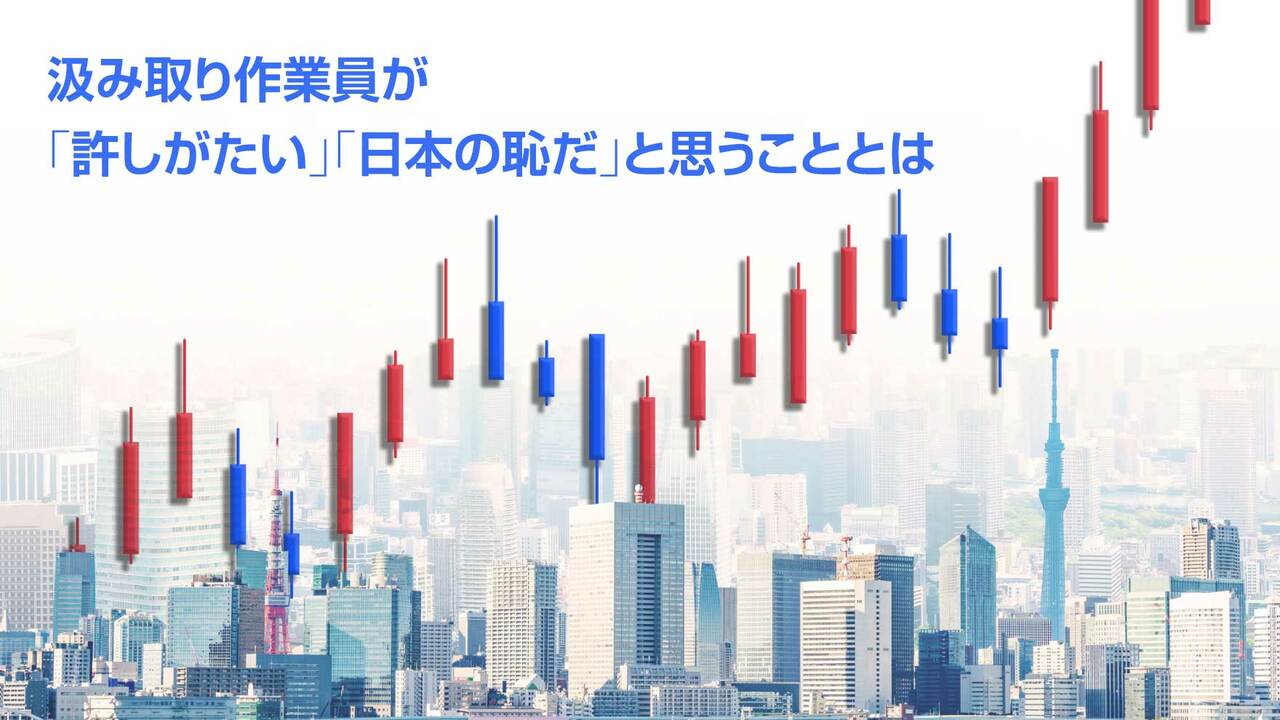【前回の記事を読む】「人の心の密接さと人口密度は、反比例してしまうのかも」
第二章 警察官は怖くない
聴取が始まる前に、刑事の下条からペットボトルのお茶を渡されてホッとした。いくら警察が好きだとはいえ、聴取とあって緊張してか喉が乾いていたので、健一はすぐにペットボトルの蓋を開けると、両手で持って「ゴクゴク、ベチュベチュ」と音を立てて飲んだ。
口元からこぼれているのにも気づかずに、半分ほど飲み干すと、むせて激しく咳き込んだ。下条が、「大丈夫ですか? ゆっくりでいいですよ」と心配げに言うと、健一は、「大丈夫です。失礼しました。始めてください」と、バツが悪そうにハンカチで口元や胸元にこぼれたお茶を拭きながら言った。
健一は仕事先や事務所などで、お茶やコーヒーなどを出されてもほとんど飲まない。というより飲めないのだ。茶碗やコーヒーカップで飲み物を出されると、手が震えて持てない。一度市役所で障害者の相談会に参加したときに、頑張ってコーヒーカップを持って飲もうとしたが、震えの発作は極限に達し、周りの人の机や書類にまで、ばらまいてしまったことがあった。
周りが障害者の関係者ばかりだったこともあって、大げさな反応はなく、何もなかったように処理してくれたが、これが商談の席だったらどうだっただろうと思うとゾッとした。
下条は、健一が落ち着くのを待って聴取を始めた。汲み取り作業を開始した時間や、その具体的な作業工程、赤ん坊の死体は、どの段階で発見したのか? それはどんな状態だったか? 周りに他に誰がいたのか? 警察への連絡はどうやってどこでしたのか? 使用した機材についてや、バキュームカーの積載容量はどのくらいなのか? 発見したとき、住人は在宅だったのか? そのとき、健一自身はどう感じどう思ったか? ということまでこまごまと質問された。
自分の発言が白鳥家の家族の人生を大きく左右することにもなりかねないと思った健一は、それらの質問にできるだけ丁寧に答えていった。家の中に人はいたかどうかだが、現場の白鳥家は、たしか夫婦と子ども三人の五人家族で、家の間取りは六畳二間の借家のはずだ。
あのときは、「汲み取りに来ました」と声をかけても返事がなかったが、中でゴトゴト、ガサガサ、音がしていたので誰かいたのは確かだと思った。それで、「家の中には、誰かいたと思います」と答えた。