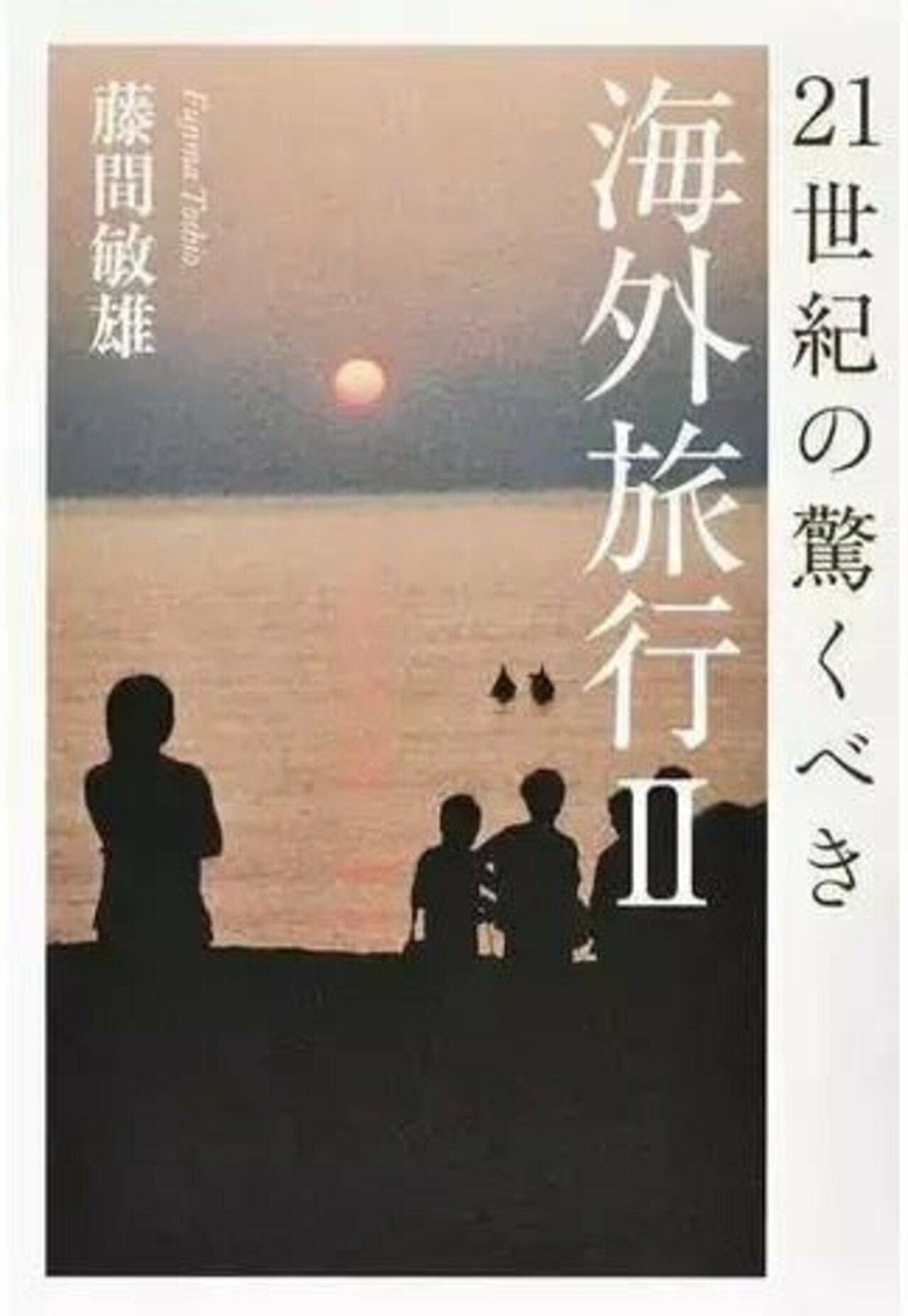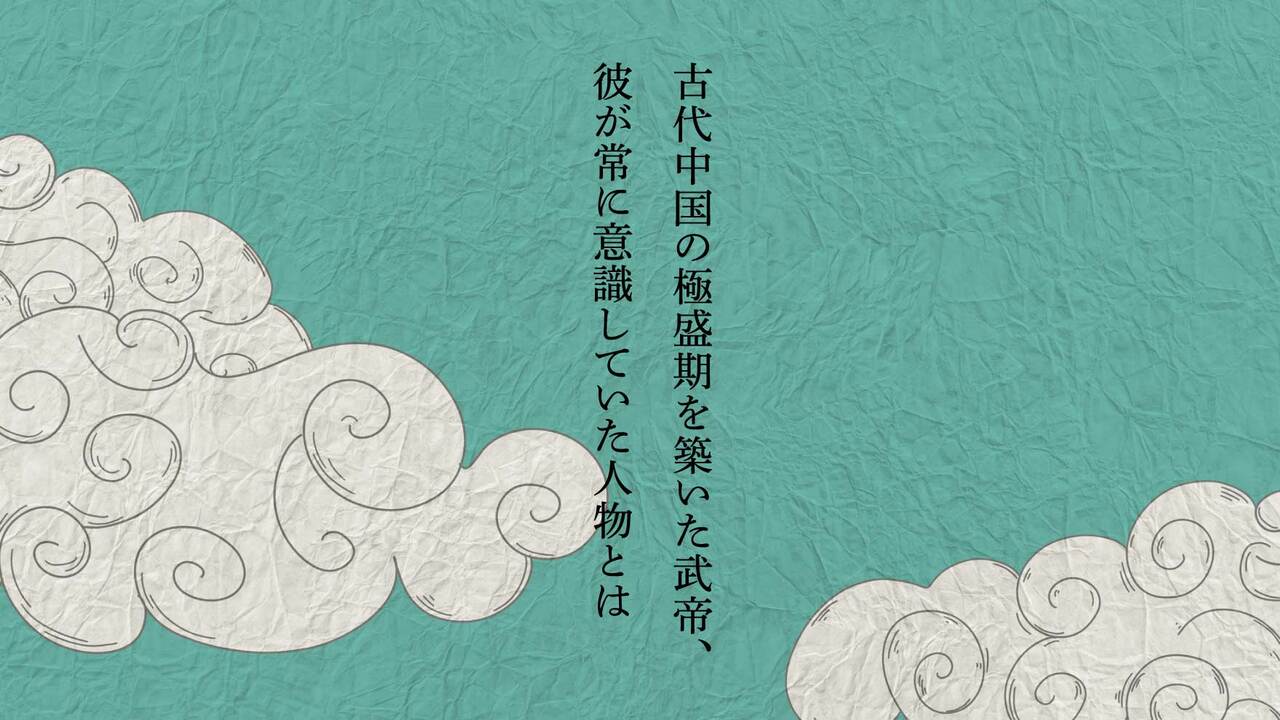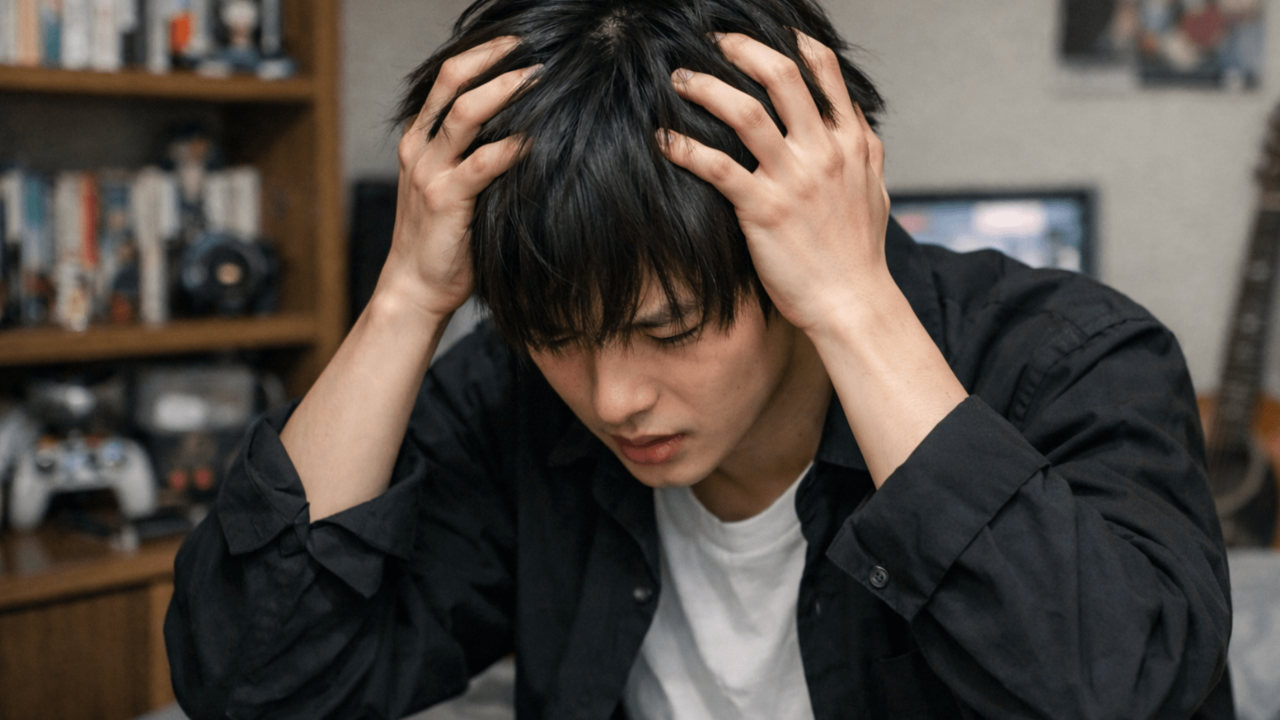故宮の中心にある乾清宮を眺めて、一九世紀の清朝末期と日本の運命をつくづく思い返した。アヘン戦争終結の時点では、日本はまだ開国していなかった。中国としては近代化のチャンスだった。
しかし、王朝末期の頽廃はこの国を立ち上がらせるには、あまりに保守的、専制的の極みに達していた。宦官、弁髪、纏足そしてアヘン吸煙の名残など、風俗面だけでも絶望的な様相を呈していた。そんな中で一八六一年に西太后が故宮の実権をにぎった。彼女は強い愛国心をもっていたが反動的性格がこの国を手のつけられぬものにしていった。

【写真】西太后
当時の世界は西欧列強の帝国主義が熾烈な征服の頂点にいた。日本が一八六七年に明治維新を成功させたのに比し、誠に対照的に清朝は全く後ろ向きになってしまったのである。中国人の思想は元来、春秋戦国時代をモデルとしてきたので、現在と未来を腐敗堕落した世の中と観ずるのが特徴で、従って思想的には悲観的である。
儒教の受容形態としては、日本では哲学、形而上学の思索については漢民族に及ばなかったが、応用的、実際的方面では非常に優れていた。「伊藤仁斎らの儒学者は気一元論をとり、宋儒の静寂な理気二元論をとらず、活動主義の倫理説を唱えた」(中村元『シナ人の思惟方法』)。
これらのことも結果として日本の相対的近代化に役立ったのである。ただし、中国も現状打破の動きが大きい現在の新型コロナが収束すれば、今後の日本の対中国観がこのままでよいかは別問題である。