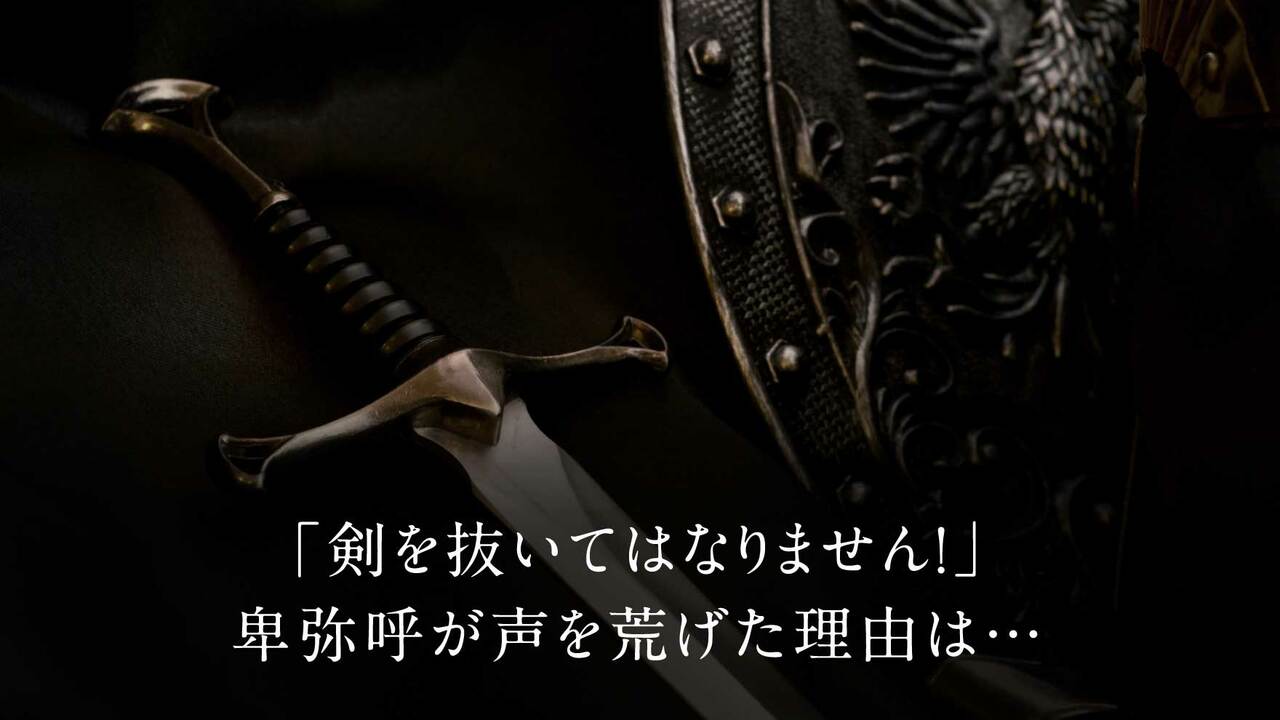遅きに失した感があるが事態の収拾のために彼女が言う。
「怖がらなくてもいいわ。今追い返します」
すると闇が闇の中に吸い込まれるように、音もなく静かに消えていくのだった。獣の臭いがまだ漂っていた。
「あ、あれは何、何なのよー、あんなものいるなんて聞いてないわよ、私を試してんのね。心の準備ってものがあるでしょう、初めから言ってよねー、あーびっくりした!」
そう言いながらも手にある武器を目にして、明日美は自分がとった咄嗟の行動に驚嘆するとともに、感覚が研ぎ澄まされ鋭くなっていることに気づいたのだ。
明日美の中に眠っていた高度の戦闘能力が目覚めようとしていた。
「私って凄い、凄くなってる」
つい自画自賛の言葉が口から漏れてしまっていた。
「あれは古代よりここに住まうものです。ここを守ってくれていたものです。あなたの知らなくてもよいものなのです」
彼女が釈明しても明日美の怒りは再燃してしまう。
「ごまかさないでよ、あんな恐ろしいものに襲われかけたのよ、知らなくていいわけないじゃないの! 私やっぱりあんたとは気が合わないみたい」
「そこまで言うのであれば仕方ありませんね、教えましょう。あれは古えより私を守っていてくれたものです。天見家が代々神として祀っていた者を守っていた守護神のようなものです」
「ええええー! するとやっぱりあなたは神様だったの? そうなのね」
心の片隅に、もしやそうではないかという思いとその逆に、神の存在に懐疑心を持っていたのも事実だ。さりとて今置かれている状況から判断すると、そうとしか考えられず驚いてしまう。これまでの暴言の数々に恐縮し、戸惑いを隠せない。
「神様とはつゆ知らず無礼の数々お許しください。わたくしめに、祟りがあるものでしょうか」
現金なもので、にわかに時代劇調の丁重な言動に変わってしまった。
「明日美、心配しなくても大丈夫ですよ。あなたは私の大切な人です。全身全霊をかけて守ってあげます」
打ち解けてきたものか、こちらも優しい口調に変化している。
「明日美、あなたは実のところ本心で神を信じてはいないわね、私も神とは何なのかわからないでいるのよ。人々がそう信じていれば、それが神様なのでしょうね。私は自分を神とは少しも思っていないわよ。今は」