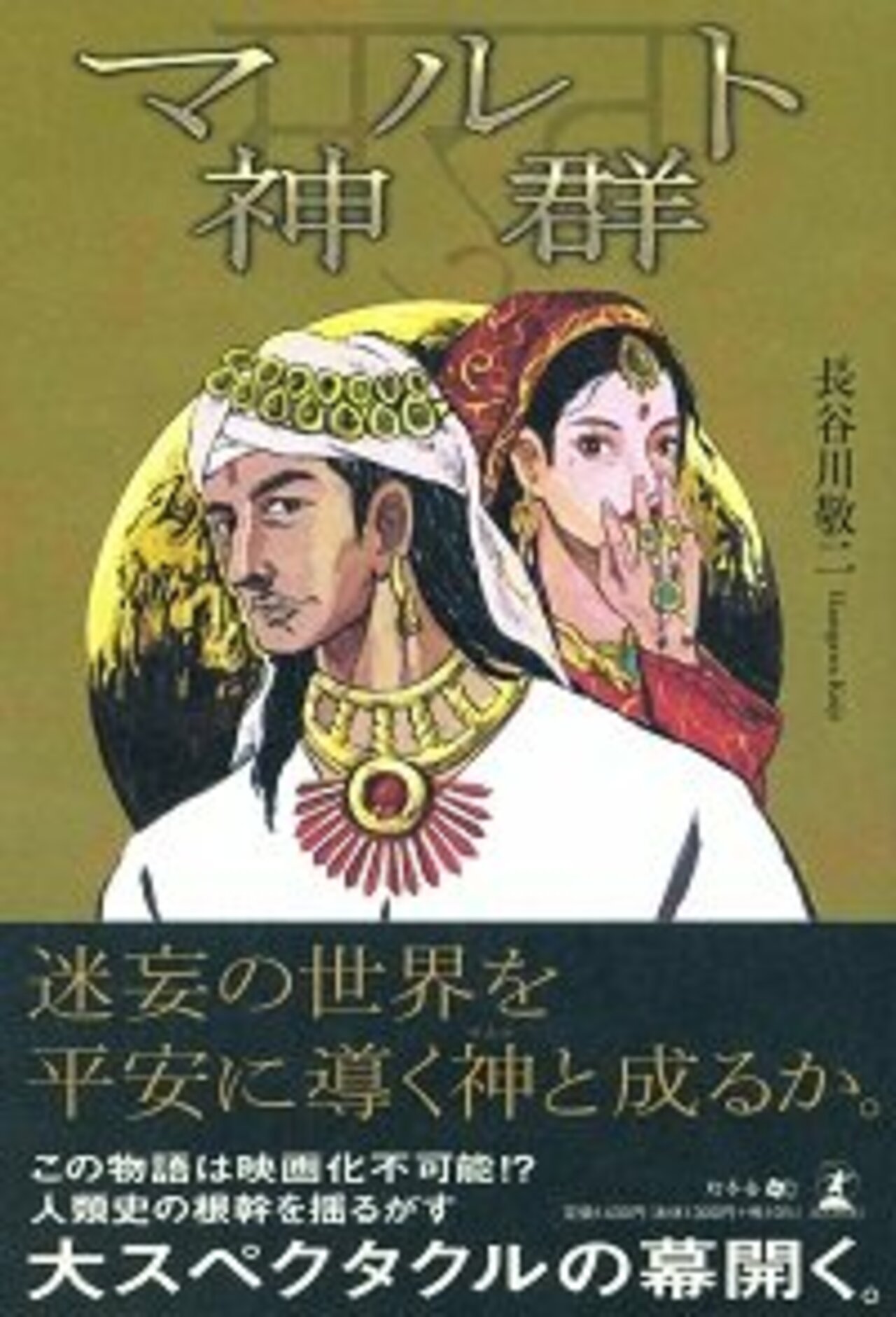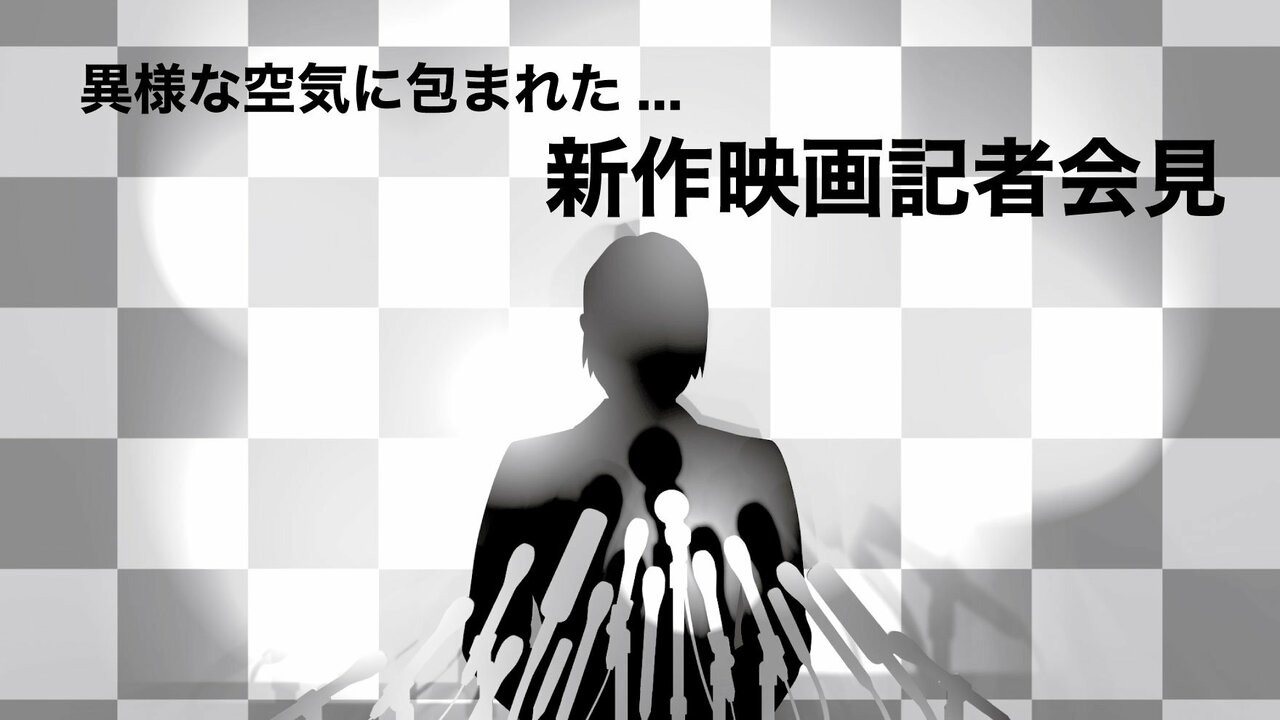【前回の記事を読む】待ちわびた名俳優との再会。かつて異形の存在であった彼は今…
婆須槃頭との再会
タクシー運転手が後部トランクから荷物を降ろし始めた。三個の旅行ケースを婆須槃頭は軽々と取っ手を持ってころがし始め、玄関に入ろうとした。秋山が近寄り会釈を送った。
「このたび放送局の特番にご出演されますが、番組のプロデュースを担当します秋山孝志です。お初にお目にかかります。よろしく」
二人は会話を始めたが意外と短い間だった。周りには報道陣のようなものは見当たらなかった。秋山が私に近づいてきた。
「彼の荷物を一時的に放送局が預かります。早速番組の打ち合わせに入りましょう」
「しかし、新藤監督も中にいれないと……」
「そうですね。では今少し待つことにいたしましょうか」
秋山は腕時計を見ながらそう言った。婆須槃頭は旅行ケースを職員に預けるとホールのソファに身を横たえた。私は近づいて彼の横に座った。秋山は二人の正面に陣取った。
「今日からの宿泊は大丈夫なの」
「ああ、すでに予約済みですよ。マスコミがうるさいんで場所は教えられませんが」
「よく日本映画出演を決心しましたね」
「日本に生まれた以上はそれも致し方ないのかと」
「あれから外国映画出演が続きましたが、どうでした?」
「映画に情熱を傾ける人間は基本的にどの国も同じですよ。ただどこも私の主張を最後まで譲りませんでしたが」
我々の会話に秋山が割って入った。
「私が放送局のこの企画を立ち上げたのは、実はインドと日本のつながりを重視し始めた政府の意向があります。中国との関係が悪化していき彼の国の覇権拡張に我慢がならなくなった日本政府が、敵の敵は味方とばかりインドに目を向け始めたのがこの企画の発端でした」
「その話は伺っていますよ。しかし、敵の敵が味方かというと実際そうではないことのほうが多くてね。インドという国はしっかり中国の関心を引き付けて利権をあさっていますよ。反対に中国だって割り切ってインドと付き合っている。孫子の兵法のがめつさをあまり甘く見ないほうがよろしいのでは」
婆須槃頭は狡知にたけた世界で揉まれてきた自信を披瀝するかのように、秋山の言葉を遮った。秋山はちょっと話の筋道を折られたことで黙り込んだ。そこへ一台の黒塗りのバンが玄関前に到着した。