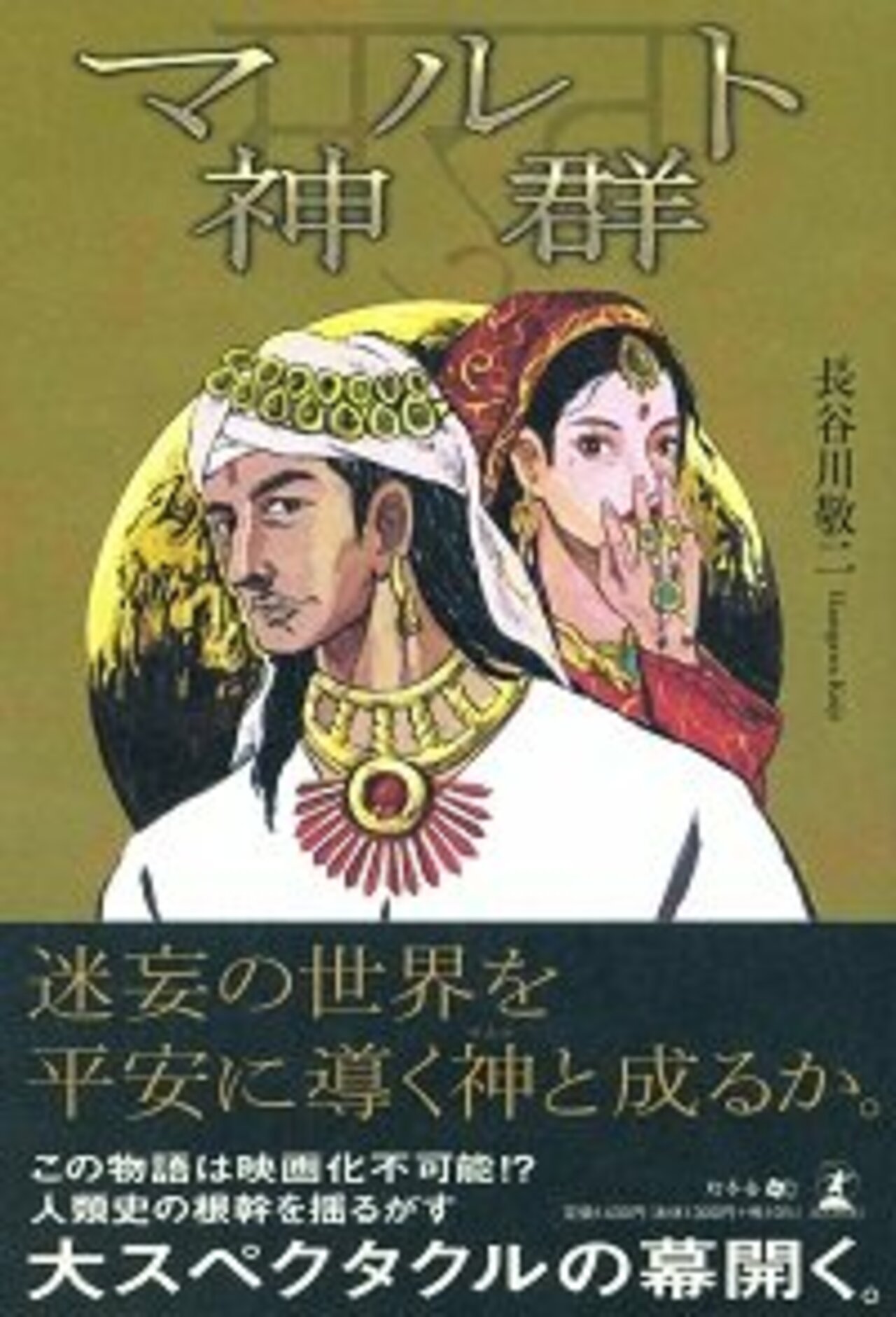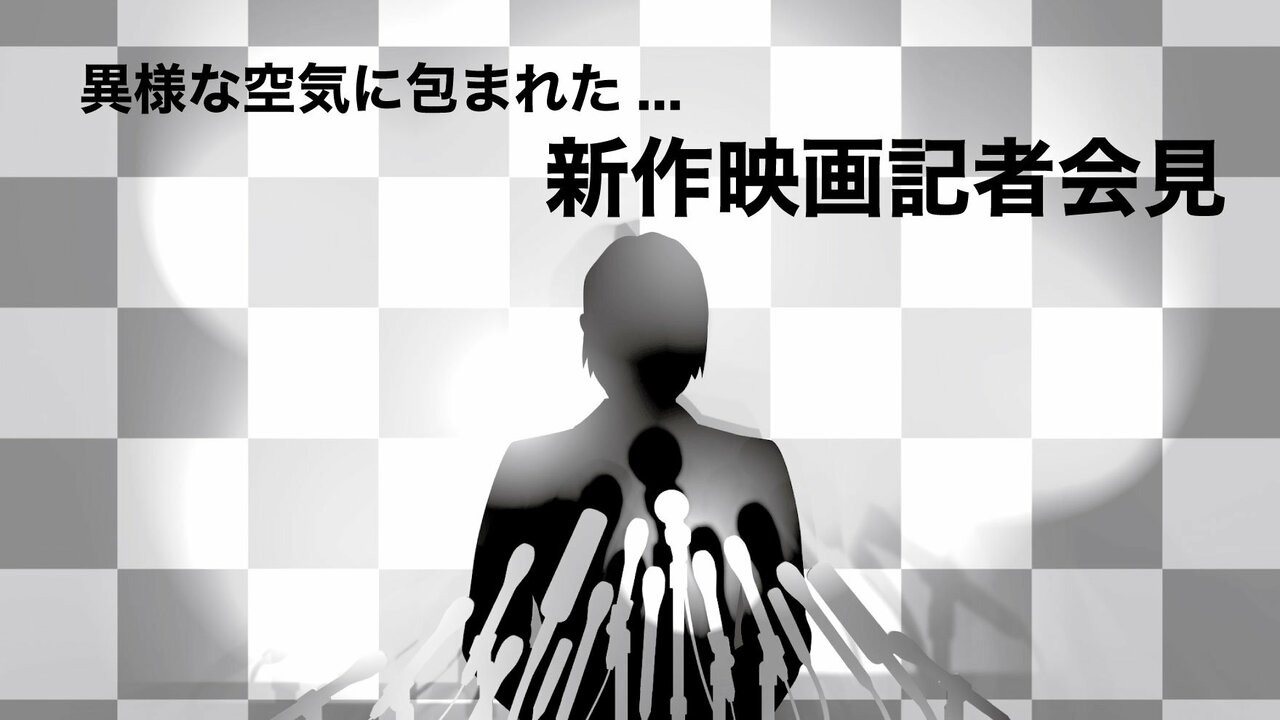車から降りてきたのは新藤由美子と見慣れない一人の男性だった。二人は目ざとく三人を見つけると近寄ってきた。
「婆須槃頭さん、新藤です。このたびは私の監督する映画にご出演承諾ありがとう。決してあなたのキャリアに傷をつけることは致しません。あなたの能力を最大限に発揮してください」
新藤はそう言うと立ち上がった婆須槃頭と握手を交わした。数年前にインタビューした時よりも、ひときわ見事な女性へと変貌していた。年齢だって四十代に入ったばかりだろう。
「婆須槃頭です。女性の監督で映画に出るのは初めてですが、豊かな才能をお持ちの新藤監督なら、と思って日本にやってきました。良い作品になるようお互い最善を尽くしましょう」
「こちらは製作者で私の恩師、佐々木洞海さんです。全面的にあなたをプロテクトいたします」
新藤は連れてきた男性を紹介した。男は緊張したように頭を下げながら婆須槃頭と握手した。私には初顔の男性だった。佐々木という男性は僧侶かと思われるいで立ちをしてみんなに挨拶して回った。偉丈夫という表現がピタリの怪異な容貌だ。どうやら裏社会に通じてもいるらしい人物と見えた。この男なら婆須槃頭の用心棒が務まるのではと思ってもみた。
僧侶といっても日本の仏教僧侶ではない。東南アジア仏教もしくはチベット仏教の僧侶のいでたちだった。あのダライ・ラマを想像してみればわかるだろう。年の頃は六十代に入ったばかりといったところか。ひとしきり自己紹介が終わると佐々木はソファに体を沈め、禿頭をひとしきり撫でまわすと、
「いやー、あの婆須槃頭さんにお会いできてほんとによかった。私の生涯で生き仏といえるのは師父と、河西秀星、ダライ・ラマ、それと、婆須槃頭さんだけだ。由美子が監督する映画は中島みゆきさんの歌じゃないが、名も知れない地上の星たちの働きを描いている。今度の初の時代劇にもそれが出ている。婆須槃頭さんはそれがわかったからこそ出演を承諾なさったのだ。こんなうれしいことはない。私は仏教徒として、一映画人としてもりもり勇気が湧いてきました」
私はその佐々木洞海という男のあけすけで八方破れな人格を、日本男性の素を見たようで好ましいとさえ思った。
「何時までもここにいるわけにはまいりません。皆さん、早速特番の打ち合わせに入るための部屋に参りましょう」
秋山が皆を促して先頭に立ち皆を引き連れだした。