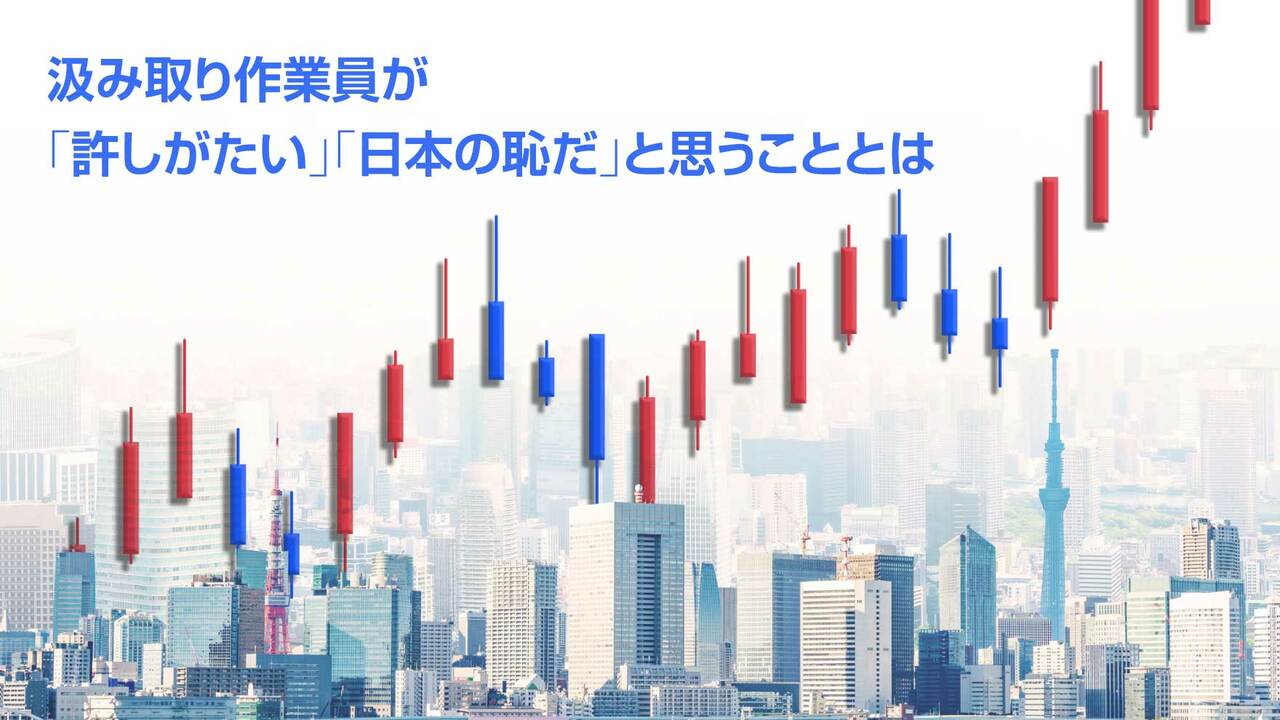紘一は、現場作業は率先してやるが、事務的なこと、特に報告書など文章を書かなければならない書類作成などは、苦手で嫌いだった。それで事務員でもある妻の勝代に、「お前やってくれねえかな。また先生に頼むと高くつくから」と懇願するように言った。先生とは、行政書士の古橋養蔵、八十一歳のことだ。
勝代は、「私に言われても困るわよ。そんなの書いたことないもの」と困惑して言った。そして、
「高井さんに頼んでみたら。現場に居合わせた本人だし。それに一応、大学を出ているんだから」
と、紘一に突っぱねるように言った。
すると紘一は、
「それもそうだな。高井君は、家でワープロも使っているみたいだし、前にも役所に出す作業報告書を作ってもらったことがある。それも一晩ですぐにやってくれたもんな。今回も言えばやってくれるだろう。古橋先生の手書きの書類より、見栄えもいいだろうしな」
と、それはいい案だとばかりにニコニコして言った。
健一は、先天性脳性麻痺のため手が不自由でペンがうまく持てない。そこで、その当時は書類作成が手軽で主流だったワードプロセッサー『ワープロ』(文書作成編集機)を自分で買って独学で覚えて使っていた。
当時、マイクロソフト社からOSウインドウズ95が発売されて、パソコンが普及し始めていた。しかし安い給料で働く健一にとって、三十万以上するパソコンはとても買えるものではなかったし、法学部を出てはいたが、情報処理の知識は、畑違いでまったく未知のものだった。
会社への電話を切った健一は、焦ってバキュームカーを駐めている現場に戻った。すると内村の姿がどこにもない。運転席を見ると、「俺は、関わりたくないので先に帰る」と書かれたメモが置いてあった。
健一は啞然とした。内村は自分を置いて帰ってしまったのだ。普通なら先輩が警察にも会社にも連絡して、状況を説明するべきではないのか。市の仕事をさせてもらっている、委託業者の社員であるという自覚はないのか。
そんなことを考えて、少し腹立たしい気持ちになっていると、けたたましいサイレンの音がして、パトカーや救急車、消防車、バイクや自転車に乗った交番の警察官、そして少し遅れて、ホロ付きの鑑識のトラックもやってきた。