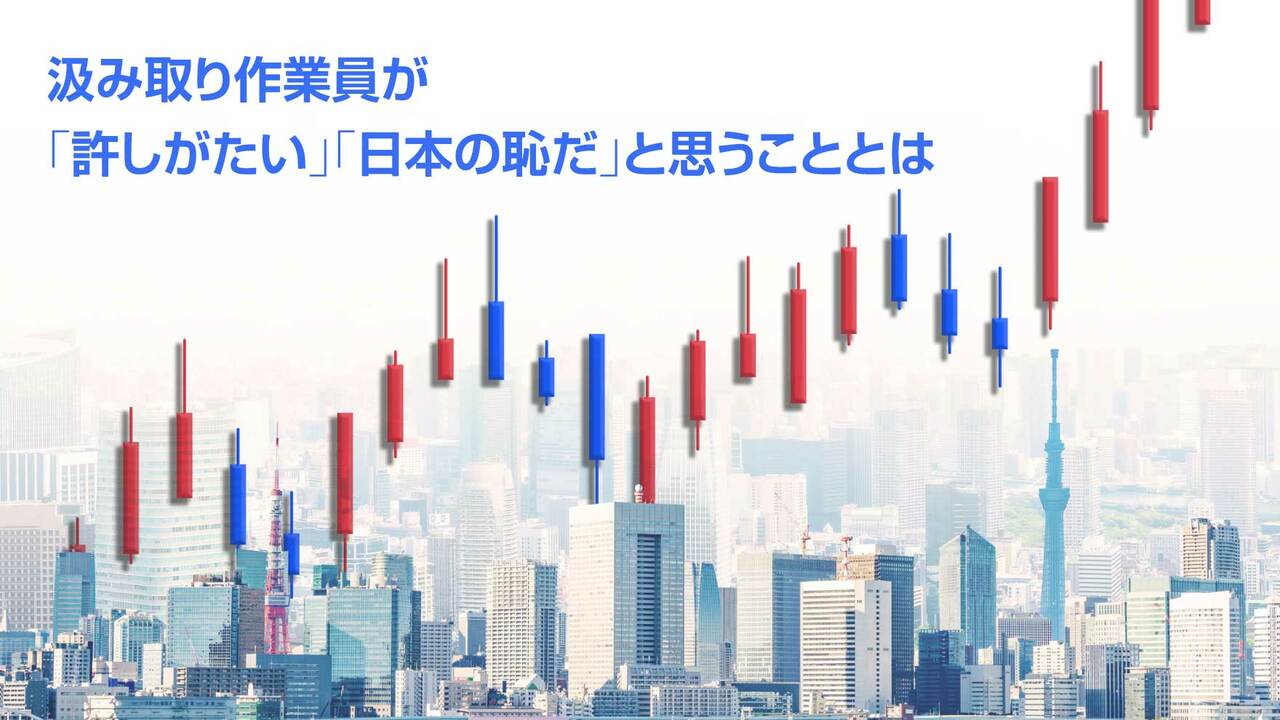バキュームカーは臭くない!
健一は二十年ぐらい前まで、この仕事を六十歳近くの年配で小柄な内村と二人でやっていた。しかしその内村もやがて定年退職した。それからはほとんど健一が一人で汲み取りの仕事をしている。
内村と二人で作業をしていた頃に、忘れられない一つの事件があった。それはある日の午後の三時頃、あと二件で予定の作業が終了するというときだった。
健一が白鳥という平屋の家で、いつものように便槽の中を見ながら汲み取り作業をしていると、人形のようなものが浮いているのが見えた。それは昔流行ったセルロイドの「キューピー人形」のようにも見えた。健一は、内村に、
「また子どもが、おもちゃを落としたみたいです」
と言うと、内村は、
「ホースで吸い付けて、外に引きずり出しておけ。ここは子どもが多いから、しょうがねえんだよ」
と言って、後で処理するためのビニール袋と、つまみ上げるための火ばさみを車に取りに行った。健一が言われたとおりに吸引用のホースを、人形らしき物に吸い付けた途端、その人形らしき物の表面が、まるで和菓子の「玉ようかん」を食べるとき、爪楊枝を刺したときのように、表面がパッと剝がれて、ホースにスルッと吸い取られ、中から赤黒い色をした肉のような塊が現れた。
そのあと表面の皮と一緒にまとわりついていた汚物が、ズルズル、ズリッと吸い取られた。そしてその反動で物体が半回転すると、その正体を現した。
小さな足が見えた。結んだままの手も見えた。そして目をつぶって口をとがらせている顔が見えた。なんとそれは、生まれたばかりであろう赤ん坊の死体だった。
健一は半分腰を抜かしそうになりながら、吸引用のホースを投げ捨てて、後ずさりしながら内村の方に向かって叫んだ。
「大変だ! 赤ん坊が落ちている! 死んでる! 早く来て下さ~い!」
内村は、
「何寝ぼけたことを言っているんだ。どうせ猫か何かが落ちて死んだやつだろう。よく見ろよ」
とニタニタして呆れたような顔で、ビニール袋と火ばさみを持って戻ってきた。それから、「ドレドレ」と言って便槽を覗き込んだ瞬間、「ギャーッ」と言って火ばさみと袋を持ったまま、尻餅をついた。そして、
「サッサと便所の蓋を閉めて、気がつかなかったことにして帰ろう」
と言って、吸引用のホースを電動リールで巻き戻し始めた。健一は、さすがにそれはまずいと思い、
「警察に連絡してきます」
と言って電話ボックスを探しに行った。
この辺りは毎月のように汲み取りに来ていて、地理には詳しいはずの健一だったが、作業中に電話をかけることは滅多にないうえに、気が動転しているのでどこに電話ボックスがあるか思いつかなかった。
焦ってそこいら中走り回ったので、歩道の縁石につまずいて転んでしまったりもした。そして、やっと角の郵便局の近くに電話ボックスを見つけた。