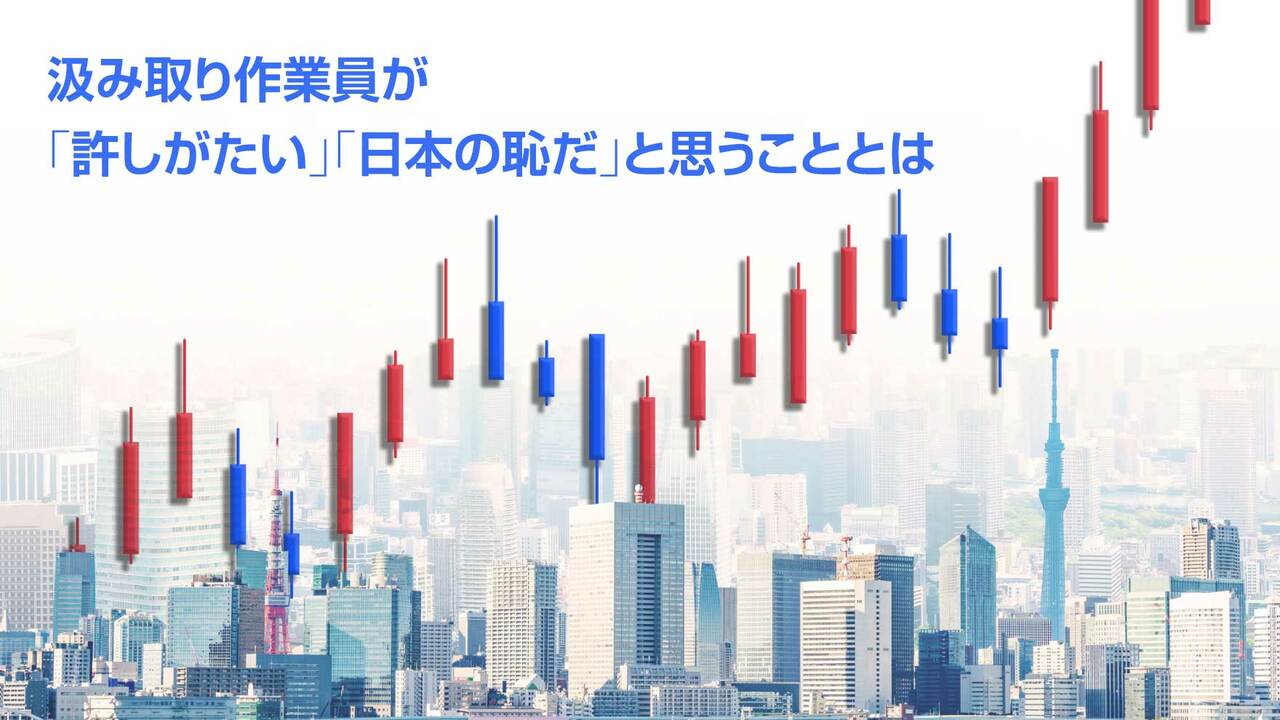「でもね、僕は最近最期に必ず訪れる『死』という課題から目を逸らさないことが、大事だと思うようになってきたんだよ。ある先哲は、『賢い者も愚かな者も、老いた者も若い者も、いつどうなるか分からないのが世の常である。それゆえ、まず臨終のことを習って、その後に他のことを習おう』と言っている。
僕は、この最も恐ろしく、解決が困難で、ほとんどの人が目を逸らし、ごまかしながら生きている『死』という問題に、真正面から取り組もうとしている自分が、誇らしくすら思えて、嬉しくなることがあるんだよ」
当時、二十歳そこそこの健一は、教授がどうしてそんな話をするのか解らずになんとなく聞いていたが、それでも何故か忘れることのできない話だった。
今になって考えると、あれは、みんなの前で自分のことを励ますためのものだったのではないか。社会に出て必ず受けるだろう、他人からのサゲスミや排斥、そこからくる孤独や疎外感、そして重くのしかかるだろう生活苦など、果てしなく続くだろう悩みや困難をなんとしても乗り越えて生き抜いてほしいとの、自分への親心だったに違いない。
そのための思索のヒントと方向性を示そうと、あのとき必死に語ってくれたに違いないと思った。それは牛塚教授が後日、健一のゼミの友人遠藤に、
「高井君には、身近に寄り添う友人が必要だ。遠藤君、宜しく頼むよ」
と言っていたことでも分かる。