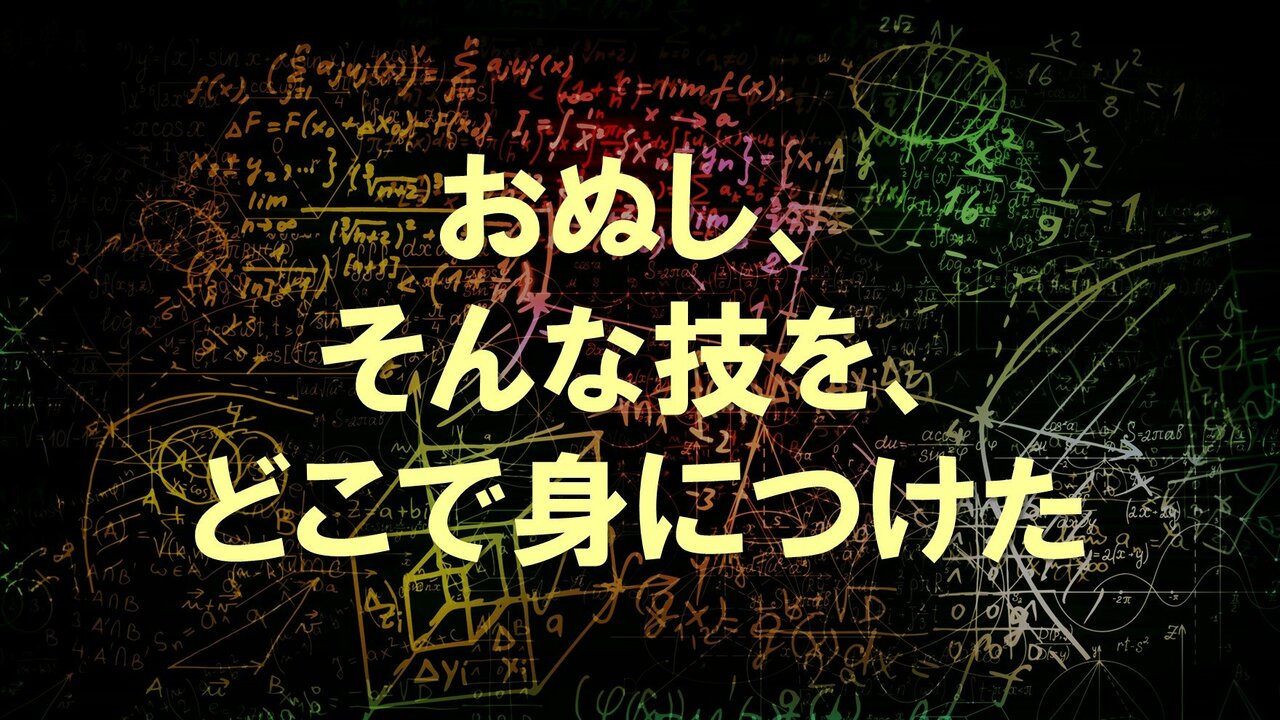壱─嘉靖十年、漁覇翁(イーバーウェン)のもとに投じ、初めて曹洛瑩(ツァオルオイン)にまみえるの事
(2)
「歳は、いくつになる」
「に、二十五にございます」
「少しいっているようだな。その歳まで、何をしていた」
私は、つつみ隠さず、来しかたを申し上げた。
「ほう、諸国を流浪しておったとな」
「豪侠(ハオシャ)ですね。まるで『水滸伝(すいこでん)』のようだ」
となりにすわった色白の宦官が、合いの手を入れた。浅黒いほうは、終始、沈黙を守り、よけいな口をさし挿(はさ)まなかった。
「おぬし、そろばんはできるか」
漁覇翁(イーバーウェン)は、魚の蒸し煮を口にしながら、言った。
「……使ったことがありませぬ」
「なら、ウチで働くのは、無理かもしれんのう」
放浪時代の、門前ばらいが脳裡をよぎった。ともかくも、どこかにやとってもらわねば、お先真っ暗のままだ。
「……お、お待ち下さい。私は、そろばんを使うことはできませぬが、計算はできます。どうぞ、おためし頂きとう存じます」
「湯祥恩(タンシィアンエン)」
「はっ」
即興で、問いかけて来た。
「三万六千五百掛ける百十七は」
「四百二十七万五百也」
即答する。
湯祥恩(タンシィアンエン)とよばれた色白の宦官は、懐中からそろばんをとりだし、パチ、パチと石をはじいていたが、指がとまると、大きく目をみひらいた。
「では、十八万五千から、二千三百九十の三十八倍を引いたら?」
「九万四千百八十也」
「全問正解です」
漁覇翁(イーバーウェン)は、驚きの表情をみせた。
「複雑な計算を、そろばんも使わず、しかも瞬時にやってのけるとは、異能というべきか。おぬし、そんな技を、どこで身につけた」
「私は、数に、興味がありました。放浪中、食べるものが得られなかったときなど、空腹をまぎらわすために夜空を仰いで、星の数をかぞえたり、昼間に、木の葉の数をかぞえたりしておりました。そのときに編み出したものです」
「フム、野に、遺賢(いけん)はいるものだ。計算にかけては、この、湯祥恩(タンシィアンエン)よりも上だの。コイツは、ウチの番頭だ」
色白の宦官が、苦笑した。
「よし、叙達(シュター)、おれのところに来い。当代随一の計算の達人をむかえるには、安いかもしれぬが、給金は、月に銀一両二分でどうだ」
「おぼし召しの通りに」
否(いな)やはなかった。これまでの人生で、永楽銭を数枚、身につけるのが精いっぱいだった私にとっては、途方もない大金にちがいなかった。
漁覇翁(イーバーウェン)は、酒をそそいでくれた。
「さあ、飲め。あたらしい人生の門出だ」
「……ありがとうございます」
こうして、私は、漁門で働くことになったのである。
(3)
私は、二重に勘ちがいをしていた。酒の席での口ぶりから、気に入られたと思い込み、もろ手をあげて迎えてくれるだろうと――また、計算のわざをみとめられ、すぐにも帳簿をまかせてもらえるのではないかと。
ところが翌朝、衚衕(まち)の人々の教示をたよりに来てみると、かんじんの漁覇翁(イーバーウェン)はどこにいるのか、所在すらもわからぬしまつであった。
(このあたりのはずだが……)
路地と平行にながれている水路のほとりで、婦人が洗濯をしている。
「漁覇翁(イーバーウェン)という人のおたくをたずねて参ったのですが……もし知っておられたら、教えて頂けませんでしょうか」
「漁覇翁(イーバーウェン)? 彼に、何の用?」
四十歳前後だろうか。小太りで、白髪のめだつ髪を無造作に結い上げている。たるんだ頰に刻まれたほうれい線が深かった。
「はあ、ここへ来るようにと言われたもんですから。今日からご厄介になることになっておりまして」
「ふーん。新入りってわけね。でもめずらしいねえ、一人でたずねて来るなんて」
婦人は、青く塗られた門を指さした。
「そこに青いとびらがあるでしょ。ここらじゃ『漁門(ぎょもん)』で通ってるんだけど」
「はい」
「そのむこうの一画は、ぜんぶ漁覇翁(イーバーウェン)の長屋なのよ」
「えっ……」
ということは、この街区がまるごと、あの鱷(わに)みたいな老宦官の、所有物なのか?
「ここから先は、漁師の海ってとこだわね。だから扉も青く塗ってあるんだよ。中に入って、さがしてみたら? 会えるかどうかは、わからないけど」
礼を言って、門をくぐった。
せまい路地の両側には、長屋がびっしりと建ち並んでいる。その路地が右へ左へと入り組んでいるものだから、まるで迷路である。
しばらく行くと、脇道が階段になっていて、階上へあがれるようになっている。のぼってみると、眺望がひらけ、あらためて建物の複雑さが目にとびこんで来た。
一軒一軒は、何のへんてつもない、昔ながらの民家である。しかし、それらが集合離散、まるで寄せ木細工のように組み上げられているのを見れば、その造形に舌を巻く。
(すごいなあ)
建物は、古いものもあれば、建て増しされたものもあって、つぎはぎが目立つけれども、柱も梁も太くて、安普請ではないことがうかがえる。
寄らば大樹の陰――これは、ひょっとすると、いい働き口なのではないか? 建物だけを見て、私は早合点してしまった。
だが不思議なことに、どこにも人影がない。これだけの長屋なら、人も大勢いるはずだ。ここら一帯の長屋は、漁覇翁(イーバーウェン)一門ではたらく人たちの住居ではないのだろうか?
「たのもう」
扉をかたっぱしからたたいてみたが、どこからも返事がない。
よし、叙達(シュター)、おれのところに来い――昨晩、そう言われたはずなのだが。
誰も、いないのか?
手すりから身を乗り出して、目を凝らした。そして、ようやく気づいた。
壁の凹みや、柱の影に、人が立っていることに――ひとり、ふたり、三人。みな、年端もゆかぬ少年である。
飛蝗(バッタ)が草むらにかくれるように、彼らは壁とおなじ色の着物を着て、まわりにとけこんでいた。
「おーい」
呼びかけると、これまた飛蝗(バッタ)のように、雲散霧消してしまった。