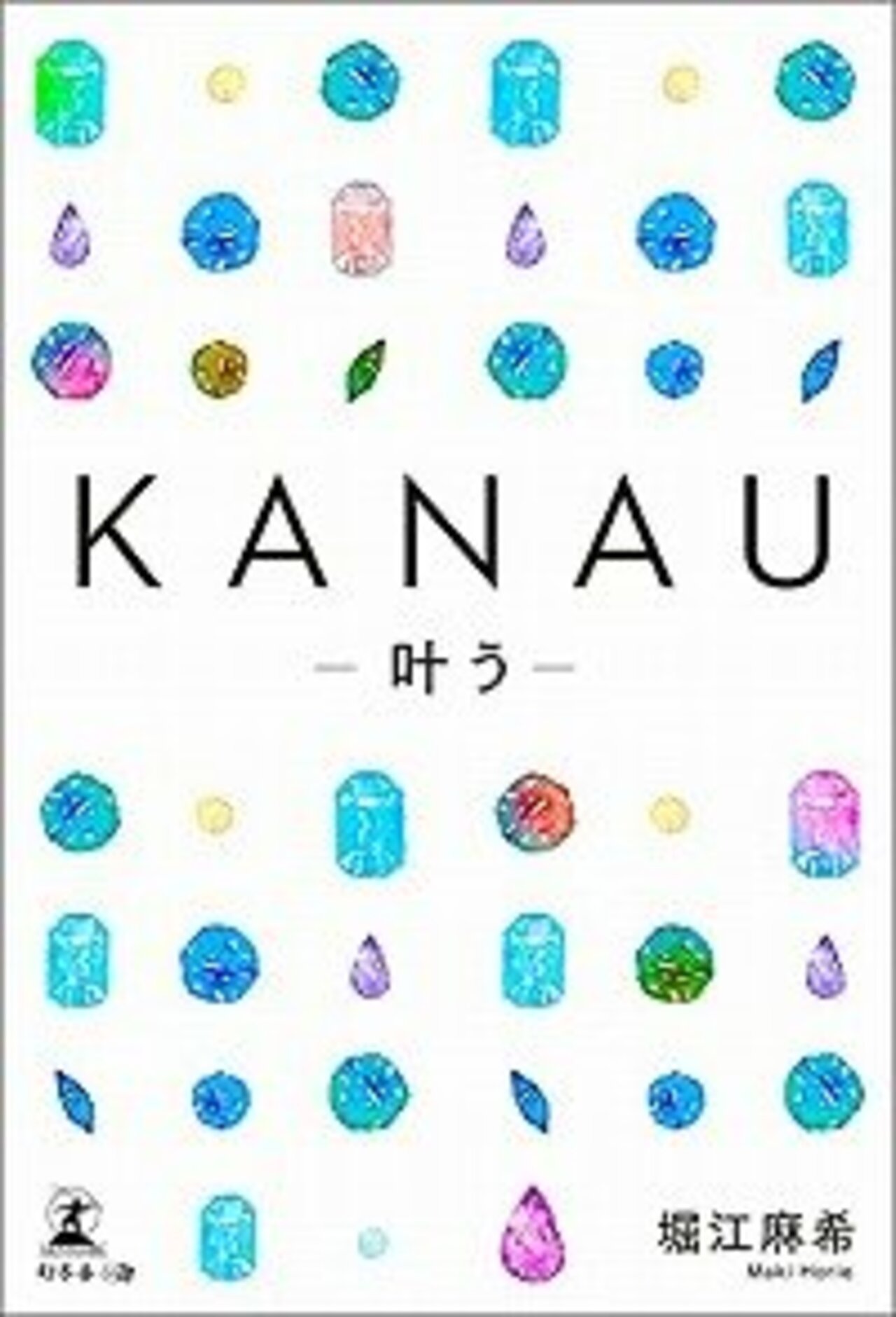その朝の海岸は薄暗く、雨のせいか、いつもより肌寒く感じた。その寒さは、望風の決心をさらに強くしてくれた。武士のメロディーに負けないいい詩を書こうと。必ずいい曲にしてやると。その気持ちを武士に伝えたくて奏多へ来た。
赤い傘に隠れた望風の顔を、武士が横から覗き込む。望風が一文字になった唇をした顔を上げる。武士の顔を見るなり、武士が黒い傘の中に抱き寄せてくれた。望風の気持ちなどお見通しだ。
望風は、甘えながら武士の顔を見上げ、優しく真っ直ぐに武士の目を見つめた。武士もほっとしたように望風の目を優しく見つめた。望風が微笑むと、武士もまた微笑んで、もう一度、武士の手が望風の頭を武士の胸におしつけた。抱きしめあって、お互いの気持ちを確かめ合い、望風が最後に、武士の短い髪をぐしゃぐしゃにして笑った。
武士も笑いながら望風の髪の毛をそっとくしゃっとして、でも武士はそのまま望風のヘアスタイルを自分の指で整えてあげた。望風は、放していた自分の赤い傘を手に取りなおした。武士がゆっくり歩きだしたので、望風もゆっくりついていった。
望風の目にうつる武士の後姿は大きくて、でもなんとなく頼りなくて、守ってもらいたいような、でも守ってあげたいような。ひたむきさも若さも頼りなさも制服で隠されていた。朝焼け残る海岸と制服。神様、この景色を守ってください。
優理:行くぞー
望風:うんうんw
その夜、望風は自宅で夕食を済ませ、入浴をためらっていた。望風が元気のない日は大体、優理からジョギングのお誘いがある。その日は、作詞がうまくいかなくて、少し煮詰まっていた。優理から連絡があると予感していた。
「こんばんはー」
一階の方から優理の声がした。そう言いながらランニングシューズを脱ぎ、多分優理はそのままリビングにいるはずだ。望風が部屋で支度をしている間に、自然にリビングで家族の一員のように振る舞っているはずだ。一階からママの笑い声がする。とても楽しそうな若返った笑い声だ。
「さよさん聞いてよー。今日さー、放課後さー」
リビングのテーブル上の手のひらサイズのハート型のクッキーを、家族みたいに当たり前のようにむしゃむしゃと食べながら、今日の出来事を話している。
文の句読点が目に見えるようなはっきりとした語り口調で話している。ハート型のクッキーは、下部を半分ほど溶かしチョコにくぐらせて冷ましてあるようだ。
ママが夕食の後に「あとでホットミルクと一緒に食べよー。マシュマロいれてあげるから」と言っていた。優理は馴れ馴れしくママと談笑していた。ソファにあったクッションを彼女の肩を抱くかのように抱いて元気な声で演説している。