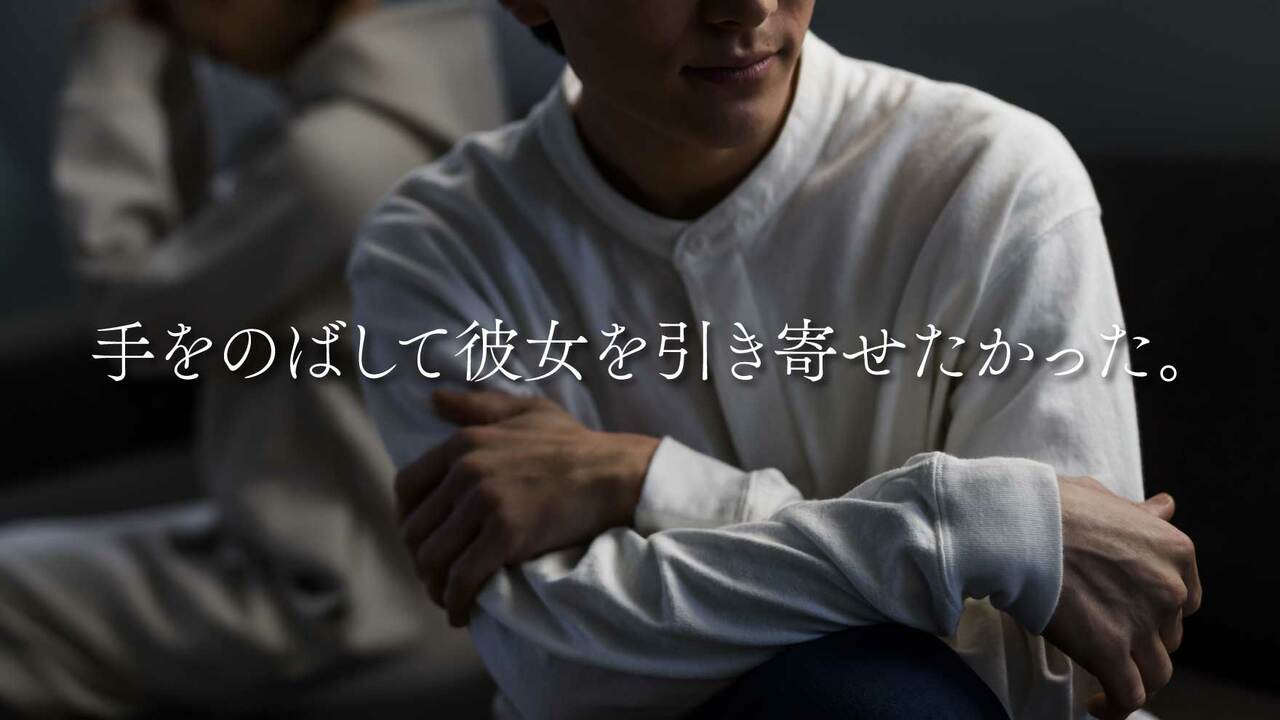「高齢者の感染重篤」
そういえば渋谷のヤマシタさんどうしているだろう? ヤマシタさんは、ご高齢で数年前に腰を悪くされてからは、俺からご自宅に訪問してカットをするようになっていた。
「あら、ケンさん? 嬉しいわぁ声が聞けて」
電話越しに聞こえるいつもの穏やかな声にほっとした。体調はどうだろうか。
「感染したら年寄りは危ないでしょう。もう死ぬのが怖くてずっと外に出ていませんよ」
「ええ、今は出ない方がいいですね」
「もう、いつもケンさんが髪を整えに来てくださるのを楽しみにしていたのにね」
「状況が良くなったらすぐに伺います。元気でいてくださいよ」
ヤマシタさんはどことなく故郷の母親に似ていた。いつも外で畑仕事をしていた母は、日焼けして身体も大きくて、ヤマシタさんのように小柄で上品な感じではない。それでも重なるのは、髪を切った時の笑顔だ。
子供のころ、母が朝から化粧して服もめかしこんでいると、美容院に行く日だとすぐわかった。帰ってくると鼻歌混じりに夕飯をつくって、何度も鏡をのぞきにいっていた。その笑顔が俺も嬉しくて、髪切って色んな人を笑顔にできたらいいなと思った。
ケープを外して、鏡をチェックする時のヤマシタさんの目が三日月のように笑う瞬間が目に浮かぶ。母さんも、次帰ったらカラーをしてあげないとな。
夜になるとネット予約の通知が携帯に入った。恵比寿に住む友人の昌太郎で、三十分もしないうちに来店した。
「おっす」
「おっす。テレワークなんて俺ムリだよ。もう尻が痛いし、やりながら寝てしまうわー」
「お前、家にデスクはないのか?」
「ないからベッドの上でやってる」
「そりゃあ寝るだろ」
「酒は飲んでねえよ」
「当たり前だ」
昌太郎ときたら。大手のセレクトショップの店長として働いていたが、マーチャンダイジングを任されるようになり、本社で働くようになった。お店が休業している間は、自宅でビデオ越しに商品のトレーニングをしたり、企画書を作ったりしているというが、接客好きで在宅には向かないタイプだ。
この状況に耐えかねたのだろう。会えて嬉しいと言わんばかりに、ずっとニコニコしている。髪を切るほど伸びていないので、スタイルはそのまま毛先だけ少しカットした。
右手の痛みは、前よりも軽くなっていた。あともう少しだ。あともう少しすれば手も完治して、お客さんがたくさんきても大丈夫になっているだろう。