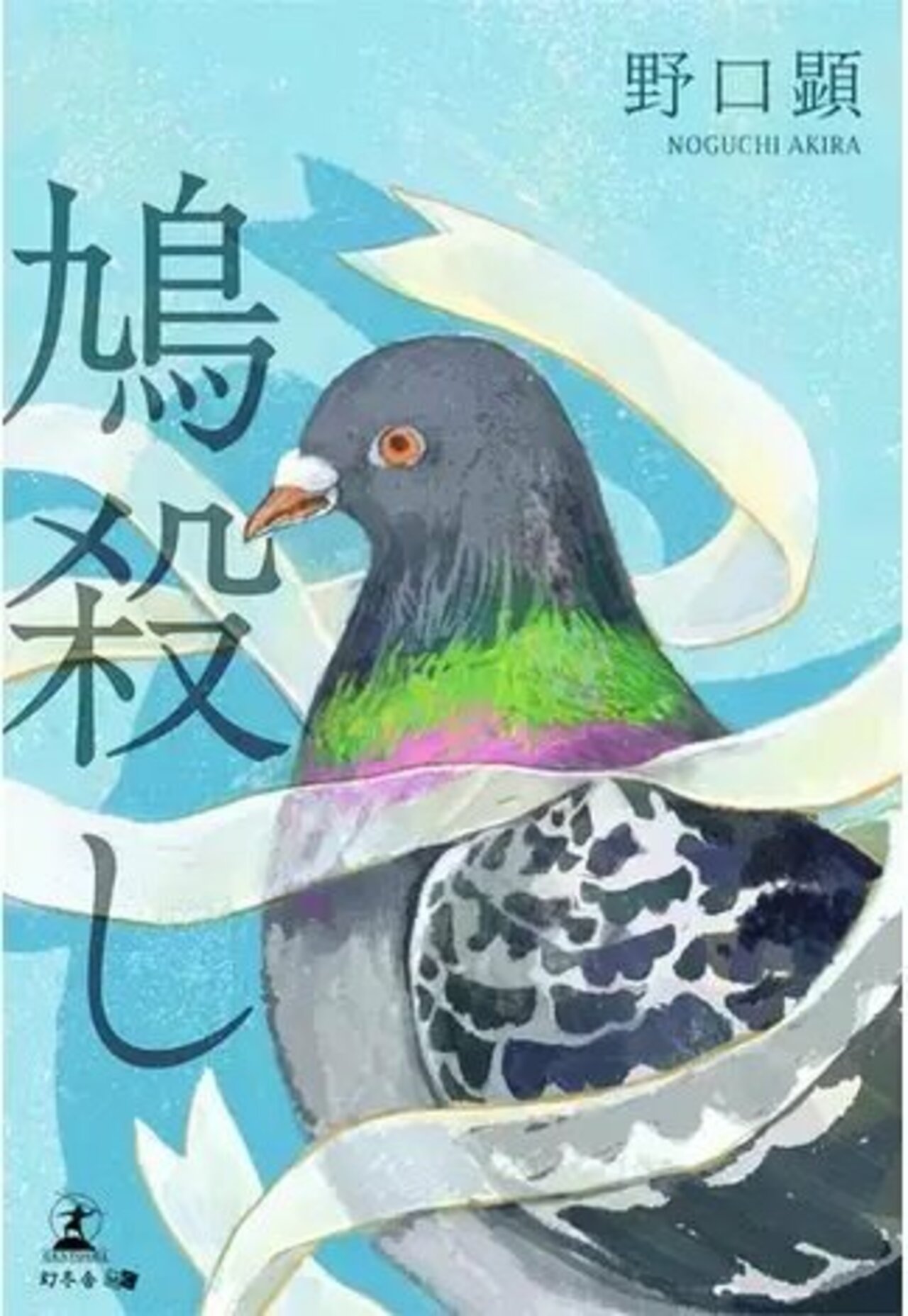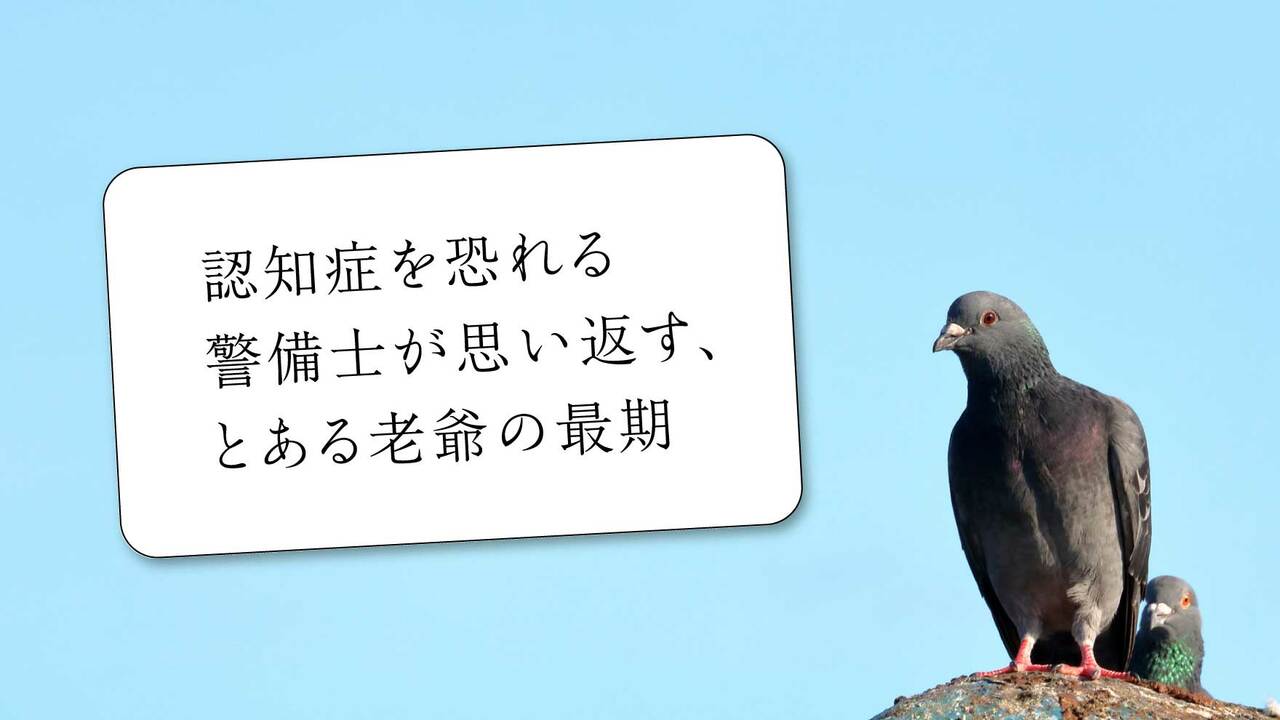少し陽があたってきた。時計を見ると十時になっていた。心の中で小原係長に詫びを言って自転車に乗った。
美代子シェフの中華料理店は、まだ暖簾を出してなかったが、中に人の気配がしたのでドアを開けてみた。美代子シェフが驚いたように眼を見開き、それから笑顔を見せてくれた。
事情を説明して、何か良い品物はないだろうかと尋ねると、しばらく考えてから中華粥はどうだろうかとの答えがかえってきた。
「おお、それそれ、前に中華街で食べたことがある。あれはいい。美味しいし消化に良い身体にやさしい食べ物だ」
「はい」
にっこり微笑んで、
「よろしければ、おつくりしますよ」
「驚いたな、貴女は何でもできるんだ」
「いえ、そんな」
美代子シェフは視線を宙にとばして考えていたが、
「本格的につくると丸一日かかってしまいますが、それは圧力鍋を使うから大丈夫として、問題は保存ですね」
「保存といっても、向こうへ行ってすぐ食べれば……」
「あちらさんで、夕食をご用意されているのではありませんか?」