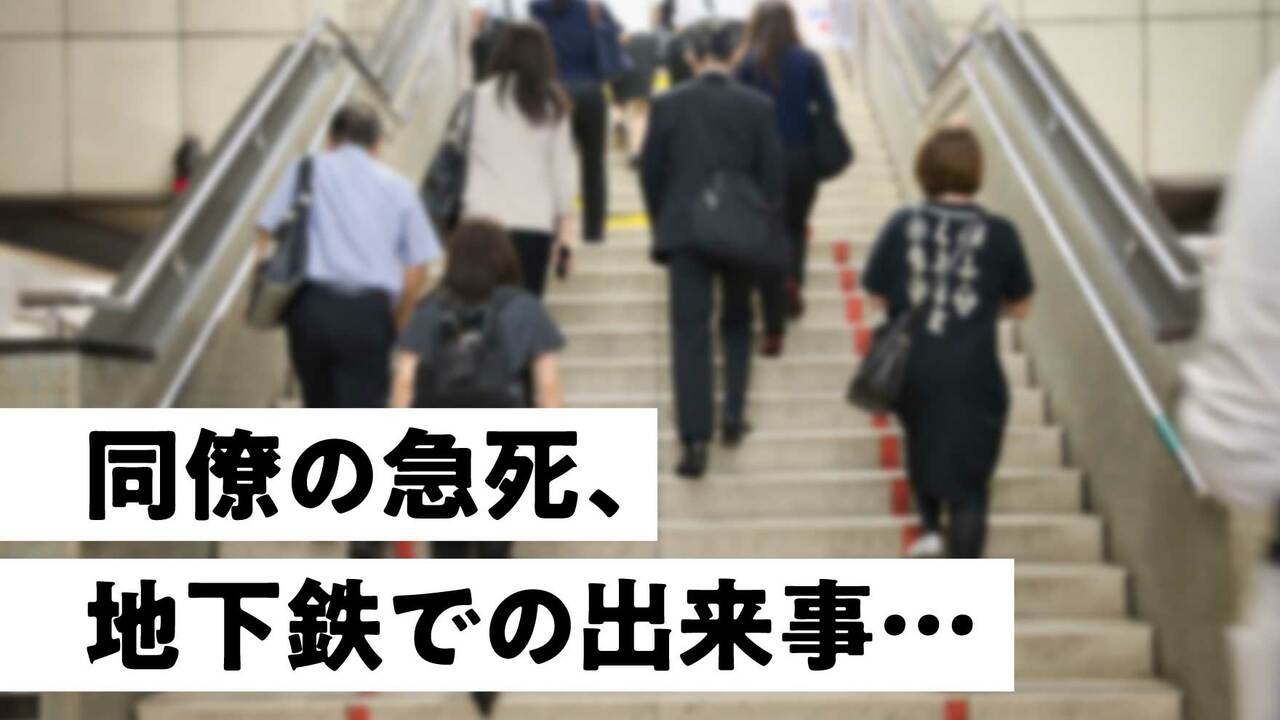双頭の鷲は啼いたか
いつもと同じ一日が終わったかのような、そうでないような。
早い帰宅時間に疲れはなく、コンビニで買った弁当を食べた。いつもは見ないテレビをつけたタケルは夜の十時に始まるニュース番組を見ようとした。
さっと風呂に入り、ジャージを着て髪を拭きながらソファに座るとリモコンを操った。あ、これか。本当だ。彼女はタケルの隣の区に住んでいたようだった。知らなかったなとタケルは思った。家族と同居だったようだ。
犬の散歩に出たあと、戻らぬ人になったようだった。昨夜から行方不明だったのか……。タケルは篠原さんのことを、役立たずだとか、いなくなればいいのにと瞬間でも思っていた自分のことを忘れたかった。
自分がそう思ったから、こんなことになったのではないかと、誰かが亡くなった時、人は誰しもそう思うのだろうか。
校舎にいた時は愚直な彼女のイメージしかなかったが、人間らしくない自分の感情を少し反省した。
気がとがめたタケルは、食事も途中でやめてしまった。
ただの偶然? 悪夢のシーンが不鮮明にフラッシュバックする。そうだ、こんな時は誰かに聞いてもらおう。浩介に電話した。
「浩介、タケルだ。こんな時間にごめん。今、いいかな?」
「うん、今帰り道。歩いている、もうすぐ家だ」
少し、息が切れていた。
「先日は楽しかった、ありがとう」
「ああ、こちらこそ。メールでいいのに。なんかあった?」
「実は、聞いてほしくて。あとでかけなおすわ」
タケルは話すのは後でもいいと通話を切ろうとした。
「いいよ、言えよ。上司ともめたか?」
「ちがうよ、実は一緒に仕事していた女子社員が殺されたみたいなんだ」
「え! 今朝のあれか?」
浩介はちょっと待てよと言いながら、家に到着した様子だった。
「ごめん、かけなおす」
タケルはそう言った。返事はなく真空状態のスマホは、タケルの不安を受け止めたまま、黙り込んだ。
「大丈夫だ、家に着いた。で、今朝のニュースの女性殺人事件な」
「そう」
「これで何人目だったかな?」
浩介は間延びした声で答えた。
「何? それ! 何人って? そんなことがあったのか?」