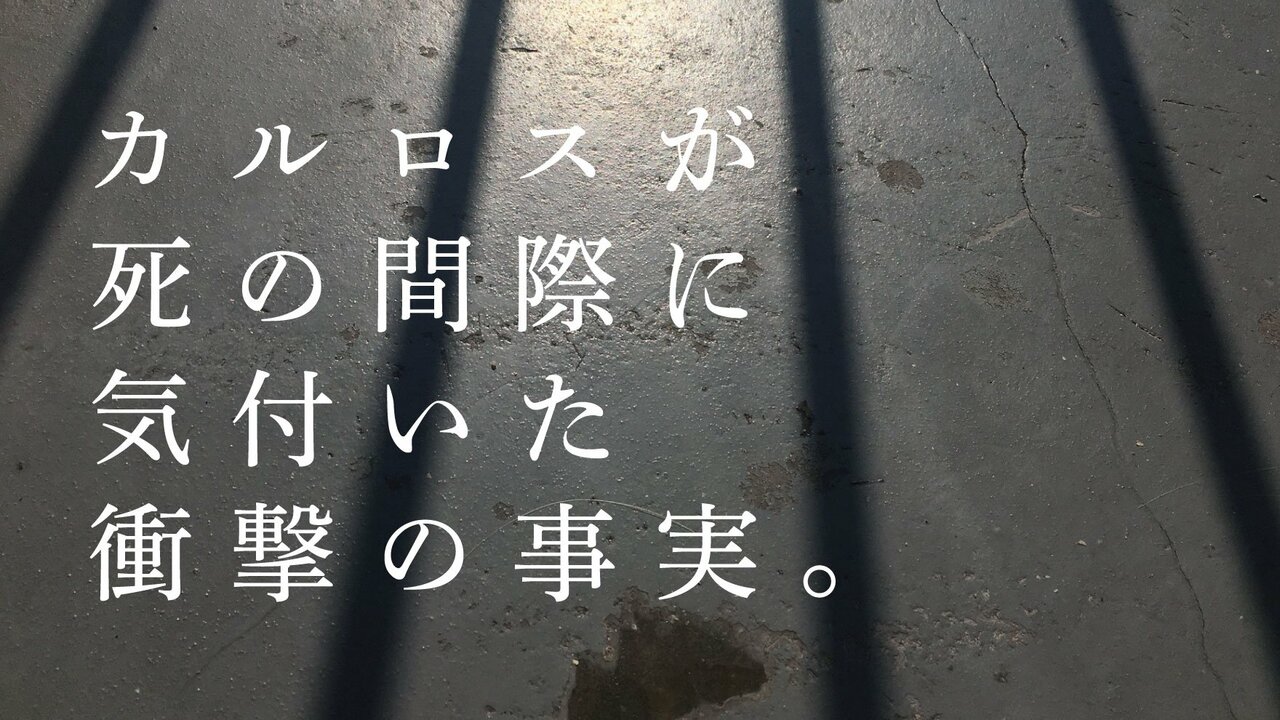ここは、車や人通りの多いにぎやかな町だった。しかし、一歩通りを曲がると、そこには昼でも暗く、通るのが怖いような裏町がいくつもあった。白髪の男がフィオリーナを抱いて向かったのは、そんな裏町に建つ古びたビルだった。玄関(げんかん)の扉(とびら)はさび、光の届かない暗い廊下(ろうか)にはゴミがあふれ、くさくて不潔だった。白髪の男はその廊下に並んだ汚(よご)れたドアの一つを開け、中に向かって声をかけた。
「カルロス。いい犬を見つけてきたぜ」
すると、ごそごそと音がして、白衣を着たやせた若い男が現れた。ボサボサのうす茶色の髪が、はれぼったい顔を半分かくしている。人を恐れることを知らないフィオリーナは、こんな怪(あや)しげな所で、怪しげな男二人に囲まれているというのに、平気な顔でしっぽをふっている。
「もっと大きい犬を探せと言っただろう、アントニオ」
低い声で言いながら、フィオリーナの柔らかい毛にふれたとたん、カルロスと呼ばれた男はなぜか、なつかしいような気持ちになった。彼はそのなつかしさが何であるのか思い出そうとしたが、頭の中に霞(かすみ)がかかったようで、それ以上考えることができない。
「まだまだ足りないぞ。もっと集めてこい。金はいくらかかってもいいから、いい犬を集めてくるんだ」
カルロスは低い声で言った。白髪のアントニオはフィオリーナに缶詰(かんづめ)のドッグフードと水を与(あた)えてから、となりの部屋のドアを開けた。いきなり、真っ暗な中から、ワンワン、キャンキャンと犬の鳴き声がひびいてくる。部屋の隅に囲いが作ってあり、その中でラブラドールレトリバー(11)、ビーグル(12)、バセットハウンド(13)の子犬が動き回っていた。
アントニオがフィオリーナを囲いの中に入れると、すぐに三びきがフィオリーナの周りに集まってきた。
「新入りだ。けんかするんじゃないぞ」
それから二、三日のうちに、アントニオは次々と子犬を連れてきて、囲いの中の子犬は十ぴきになった。